3月17日(火)、13:00~17:30、標記の会が実施されました。卒業式の快い疲れも残ったままですが、さらに充実した時間を送りました。「阿波学事始め」は四国大学が3年前から進めてきた学際的研究プロジェクトの一つで、ここの地元である阿波について様々な専門分野の教員が共同して研究し、それを地域の皆さんにも適宜発表していこうとするものです。私も含めたメンバー6名が、様々なテーマで共同研究しましたが、3年間をもって一応の区切りとなります。この日は、その研究内容の発表と、関連の講師を招聘しての講演会でした。最初に講演していただいたのは、國學院大学文学部教授の上山和雄先生です。その地元である東京都渋谷の研究である「渋谷学」の話でした。渋谷の歴史と共に、若者に人気のある現代の渋谷の文化についても興味深い研究がされていました。

次には、2年前に研究メンバー5名で訪問した高知県立坂本龍馬記念館の学芸員である三浦夏樹氏による、ジョン万次郎の紹介でした。彼とはその時にお会いしてお互いに覚えていました。万次郎の話を河田小龍が聞き取って絵入りで書いた『漂巽紀略』という本の紹介が主でしたが、パワーポイントを上手に使ってわかり易い発表をしてくださいました。

この後は、私と、萩原八郎先生、須藤茂樹先生が続けて、幕末の長尾初太郎のメキシコ漂流に関する概要とスペイン語と絵画の話をしました。これは、3年間メンバーが取り組んできた共同テーマです。四国大学図書館にこの漂流事件を記録した『亜墨漂流新話』と『亜墨竹枝』という本が所蔵されていることから始まったものです。最後にこの初太郎の現在の子孫の代表である長尾啓太郎氏のお話で締めくくりました。現在は、長尾産業株式会社監査役であるとともに徳島日本ポルトガル協会理事です。
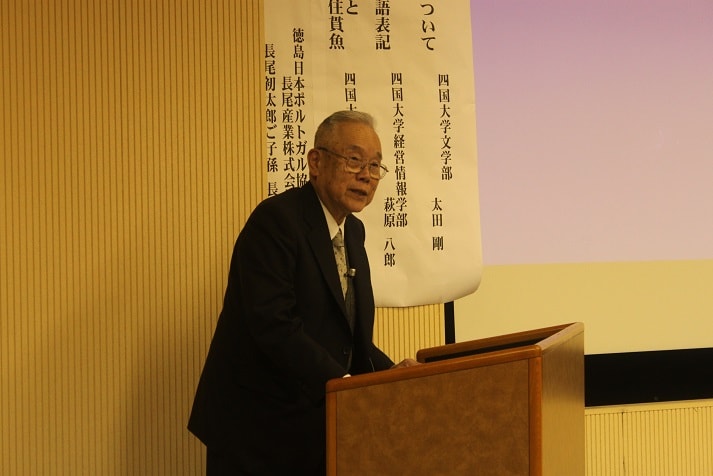
初太郎の孫娘のカメと結婚した養子の伝蔵が徳島に出て興した「長尾染織工場」が発展し、戦前は徳島で最大の企業でした。さらにその娘婿の新九郎は、何度か欧米を訪問して国際感覚に優れ徳島市長となって活躍します。さらにそのお孫さんが啓太郎さんです。偶然起きた漂流によって幕末にメキシコに行ってホームステイして帰ってきたその経験は、子孫に「国際感覚」を植え付け、有能な人物を多く輩出しました。この出来事は全国的にはジョン万次郎ほどは広く知られていません。漂流先が英語圏のアメリカでなくスペイン語圏のメキシコであったし、漂流から帰国までの期間が圧倒的に短かったことがその要因ですが、徳島に与えた影響は実はかなり大きなものがあります。プロジェクトは今年度で一旦終了しますが、この研究に関しては個人的にまだ続けていこうと思っています。










