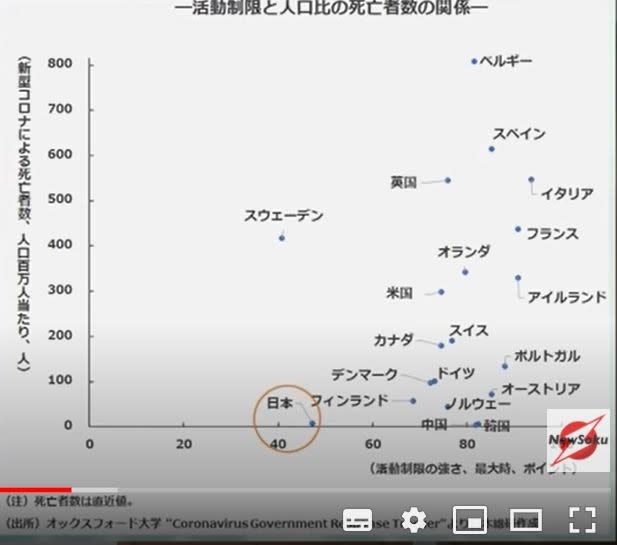沖縄戦史の再検証のため過去ブログ集団自決:極左が監修する公的刊行物!2010-05-16
を一部編集して再掲します。
★
沖縄戦史に関する一般書籍や公的出版物にも捏造部分が多い。
その理由は、その執筆者が左翼的発言で知られる沖縄の知識人が多いからだ。
例えば自分の父親を米兵に虐殺された知念勇さんの証言を採録し、『那覇市史』に記述した嘉手川重喜氏とはどんな人物だったのか。
■米兵を日本兵に入れ替えた人物-琉球新報の元記者
沖縄戦史に「残虐非道の日本軍」というイデオロギーを吹き込んでいるのが沖縄タイムスと琉球新報の地元2紙であることは周知のこと。
知念勇さんの証言の「米兵」と「日本兵」を作為的に入れ替えた犯人の嘉手川重喜氏が、沖縄戦史の捏造で悪名高い琉球新報の元記者であることを知れば、驚くというより、さもありなんと思う人が多いだろう。
さらに集団自決の研究者が一度は手にすると思われる『渡嘉敷村史』や『座間味村史』の編纂に関わった沖縄の識者の正体を知れば、今度は逆に驚きを越して笑ってしまうだろう。
先ず『渡嘉敷村史』の監修者は「反日」「反天皇」のあの人物。
以前星雅彦氏が県(琉球政府)の依頼で渡嘉敷の聞き取り調査をした時の調査報告を「検閲」し星氏が取り上げた「日本兵の善行」を県史から削除した、あの安仁屋政明沖国大名誉教授なのだ。
安仁屋教授は、「大江・岩波集団自決訴訟」の被告側証人として陳述書を提出した「軍命あり派」のリーダーであるが、これだけで驚いてはいけない。
なんと一方の『座間味村史』の監修者は、安仁屋教授の愛弟子であり、集団自決訴訟の被告側証人として法廷に立ったあの宮城晴美氏であるから、今度も驚きが転じて、思わず笑ってしまう。 まるで師弟漫才ではないか。
これでは集団自決研究の原典とも言える「渡嘉敷村史」と「座間味村史」を安仁屋、宮城の極左師弟コンビが検閲するという最悪のパターンになる。
前述の知念勇さんの例でもそうだが、これらの極左知識人の手口は、あらかじめ結論が出来上がっており、記述あるいは監修の過程で捏造をそれとなく織り込んで物語を作り上げるのが常套手段である。
文科省の歴史教科書検定意見に沖縄の歴史学者の研究成果が反映していないという意見を良く聞くが、このようなイデオロギーまみれの沖縄の学者達の「研究の成果」を教科書に反映させることこそ歴史の捏造につながるのではないか。
■「母の遺した遺言」を書き換えた宮城晴美
宮城晴美氏が法廷証言のわずか一ヶ月前に、集団自決の証人である母の遺言を踏みにじり、イデオロギーの呪縛に平伏した話はあまりにも有名だが、前言を翻した恥ずべき新旧二種の『母の遺したもの』を読むまでもなく、裁判が提訴される前までは、宮城氏は正直に「軍命はなかった」と、あの沖縄タイムスの紙面で述べているではないか。 読者をバカにするのもいい加減にしろといいたくもなる。
「軍命派」の総本山沖縄タイムス記事をコピーしてアップしているので、引用する。
宮城晴美氏がいかに嘘つきであるかが分かる。

■沖縄タイムス 1995年(平成7年) 6月22日 木曜日
母の遺言 (上)
証言の独り歩きに苦悩
手記の書き直し託される 宮城 晴美
その年、母は座間味島の「集団自決者」の名簿を取り出し、一人ひとりの屋号、亡くなった場所、使用した"武器"、遺体を収容したときの状況など、これから自分が話すことのすべて記録するよう、娘の私に指示してきた。座間味島の地図を広け、「自決者」のマップをつくりながら、母は知りうる限りの情報を私に提供し、そして一冊のノートを託したのである。
元号は変わっても・・・
それから間もなく、元気よく一週間の旅行に出かけたものの、母は帰ってきてから体の不調を訴えるようになり、入院後、とうとう永遠に帰らぬ人となってしまった。 一九九〇年(平成二年)十二月六日であった。
母の死後、遺品を整理しているなかで、日記帳の中から一枚のメモ用紙を見つけた。前年の一月七日、つまり昭和天皇が亡くなったその日に書かれたものであった。(省略)
"事実"を綴ったノート
そして、私に托された一冊のノート。それは字数にして四百字詰め原稿用紙の約百枚におよぶもので、母の戦争体験を日を追って詳しく綴ったものであった。母は「いずれ時機を見計らって発表しなさい。でも、これはあくまでも個人の体験なので発表するときには、誤解がないよう、客観的な時代背景を加えるように」と言葉を添えて手渡したのである。
ただ、母はこれまでに座間味島における自分の戦争体験を、宮城初枝の実名で二度発表している。まず、六三年(昭和三十八年)発行の『家の光』四月号に、体験実話の懸賞で入選した作品「沖縄戦最後の日」が掲載されたこと。それから五年後の六八年に発行された『悲劇の座間味島-沖縄敗戦秘録』に「血ぬられた座間味島」と題して体験手記を載せたことである。
ではなぜ、すでに発表した手記をあらためて書き直す必要があったのかということになるが、じつは、母にとっては"不本意"な内容がこれまでの手記に含まれていたからである。
「"不本意"な内容」、それこそが「集団自決」の隊長命令説の根拠となったものであった。
自責の念にかられる
とくに、『悲劇の座間味島』に記載された「住民は男女をとわず軍の戦闘に協力し、老人子供は村の忠魂碑前に集合、玉砕すべし」と梅澤部隊長から命令が出されたというくだりが、『沖縄県史10 沖縄戦記録』をはじめとして、多くの書籍や記録のなかで使われるようになり、その部分だけが切り取られて独り歩きをしだしたことに母の苦悩があった。あげくは、その隊長命令説を覆そうと躍起になるあまり、曽野綾子氏に代表される、自決者を崇高な犠牲的精神の持ち主としてまつりあげる人々が出てきたとなると、母の気持ちが穏やかであるはずがなかった。
そしてもう一つの"不本意な理由、それは、自分の証言で「梅澤部隊長」個人を、戦後、社会的に葬ってしまったという自責の念であった。これが最も大きい理由であったのかもしれない。
(沖縄女性史研究家)
◇みやぎ・はるみ 一九四九年 座間味生まれ。雑誌編集者を経て、フリーライターになる。集団自決を中心とした戦争体験を追いながら、女性史とのかかわりを調査。九〇年から、那覇市で女性史編さん事業にたずさわる。
■沖縄タイムス 6月23日 金曜日
母の遺言 (中)
切り取られた"自決命令"
「玉砕」は島民の申し出
援護法意識した「軍命」証言
宮城 晴美
母は、どうして座間味島の「集団自決」が隊長の命令だと書かなければならなかったにか、その真相について私に語りだしたのは、確か一九七七牢(昭和五十二)だったと思う。戦没者の三十三回忌、いわゆる「ウワイスーコー」と呼ばれる死者のお祝いを意味した最後の法事があると私は聞き、「島の人は何を孝えているのだろう」という気持ちから座間味島の取材に出かけたときのことである。
「援護法」とのはざまで
話は一九五六年(昭和三十一)にさかのぼった。沖縄への「援護法」(正確には戦傷病者戦没者等遺族援護法)の適用を受け、座間味村では一九五三年から戦没者遺家族の調査が着手されていたが、それから二年後、村当局は、戦争で数多く亡くなった一般住民に対しても補償を行うよう、厚生省から来た調査団に要望書を提出したという。この「援護法」は、軍人・軍属を対象に適用されるもので、一般住民には本来該当するものではなかった。
それを村当局は、隊長の命令でで「自決」が行われており、亡くなった人は「戦闘協力者」として、遺族に年金を支払うべきであると主張したというのである。つまり、国のシステムから考えれば、一般住民に対して「勝手に」死んだ者には補償がなされず、軍とのかかわりで死んだ者にだけ補償されるといういう論理を、住民たちは逆手にとったことになろうか。
その「隊長命令」の証人として、母は島の長老からの指示で国の役人の前に座らされ、それを認めたというわけである。母はいったん、証言できないと断ったようだが、「人材、財産のほとんどが失われてしまった小きな島で、今後、自分たちはどう生きていけばよいのか。島の人たちを見殺しにするのか」という長老の怒りに屈してしまったようである。それ以来、座間味島における惨劇をより多くの人に正確に伝えたいと思いつつも、母は「集団自決」の箇所にくると、いつも背中に「援護法」の"目"を意識せざるを得なかった。
軍と運命を共に(省略)
一九四四年(昭和十九)九月、この島に日本軍か駐屯するようになったころから、住民は兵隊たちと運命を共にすることになる。(省略)
忠魂碑の前に
一九四五年(阻和二十)三月ニ十五日、三日前から続いた空襲に代わって、島は艦砲射撃の轟音(ごうおん)に包みこまれる。方々で火の手かあがり、住民は壕の中に隠れていても、いつ砲弾が飛び込んでくるか、ただおびえているだけであった。そんな夜おそく、「住民は忠魂碑の前に集まれ」という伝令が届いたのである。伝令が各壕を回る前に、母はこの伝令を含めた島の有力者四人とともに、梅澤隊長に面会している。有力者の一人から一緒に来るようにいわれ、意味もわからないまま、四人についていったのである。
有力者の一人が梅澤隊長に申し入れたことは、「もはや最後のときがきた。若者たちは軍に協力させ、老人と子どもたちは軍の足手まといにならぬよう忠魂碑の前で玉砕させたい」という内容であった。
母は息も詰まらんばかりのショックを受けていた。
■沖縄タイムス 6月24日 土曜日
母の遺言 (下)
「集団自決」時の社会背景
戦争は「終戦」で終わらない
島の有力者たちがやってはきたものの、いつ上陸してくるか知れない米軍を相手に、梅澤隊長は住民どころの騒ぎではなかった。隊長に「玉砕」の申し入れを断られた五人は、そのまま壕に引き返していったが、女子青年団長であった母は、どうせ助からないのだから、死ぬ前に仲間たちと軍の弾薬運びの手伝いをしようと、有力者たちとは別行動をとることになった。その直後、一緒に行った伝令が各壕を回って「忠魂碑前に集まるよう」呼びかけたのである。
軍国主義の象徴
伝令の声を聞いたほとんどの住民が、具体的に「自決」とか「玉砕」という言葉を聞いていない。「忠魂碑」の名が出たことが、住民たちを「玉砕思想」へと導いたといってもいいだろう。(省略)
元隊長との再開
この場所に集まれというのだから、住民としてはすぐさま「自決」と結びつけざるを得なかった。結果的には、住民は激しい艦砲射撃のため、忠魂碑に集まることができず、それぞれの壕で一夜を明かしたものの、翌日、上陸した米軍を見た住民がパニックを起こして、家族同士の殺し合いが始まったのである。(省略)母とともに、梅澤隊長のもとを引き揚げた四人全員が「集団自決」で亡くなってしまったため、戦後、母が"証言台"に立たされたのもやむを得ないことであった。
一九八〇年(昭和五十五年)の暮れ、母は梅澤元隊長と那覇市内で再会した。本土の週刊誌に梅澤隊長が自決を命令したという記事が出て以来、彼の戦後の生活が惨憺(さんたん)たるものであるということを、島を訪れた元日本兵から聞かされていた母は、せめて自分か生きているうちに、ほんとのことを伝えたいと思っていたからである。
皇民化教育の本質
その後の彼の行動については、あえてここでは触れないことにしよう。しかし、一つだけ言わせていただくとしたら、梅澤元隊長が戦後なお、軍人の体質をそのまま持ちつづけている人であることに変わりはない、ということである。母は、私がモノ書きとして生活するようになってからは、いつも思い出したように言いつづけたことがあった。
「いまは事実を書かなくてもいい。でもウソは絶対に書いてはいけない」ということ。そしてもう一つは、「『集団自決』を論ずるとき、誰が命令したか個人を特定することにこだわっていると皇民化教育の本質が見えなくなってしまう。当時の社会背景をしっかりおさえなさい」と。
母は「事実」を元隊長に話したことで島の人との間に軋轢(あつれき)が生じ、悩み苦しんだあけくとうとう他界してしまった。
母の死を通して、戦争というのが決して「終戦」でおわるものではないことをつくづく思い知らされている。
◆
文中の「有力者」とは、住民を自決に誘導したといわれる宮里盛秀助役のことだが、宮城晴美氏が法廷証言の一ヶ月前に「軍命あり」に宗旨替えした根拠が、宮里助役の実の妹である宮平春子氏の「兄擁護」のための証言だというから驚きだ。
こんな大嘘つきが『座間味村史』の監修をしている沖縄研究者の実情をオカシイと思う方、応援のプチッ!を、 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします