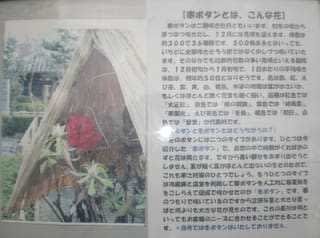北葛城郡王寺町(おうじちょう)は奈良県の同郡内では北端に位置し、奈良県内における大和川水系の最下流に位置する町です。北は大和川を境に三郷町・斑鳩町と接し、東部は河合町・上牧町、南部は香芝市、 西部は大阪府柏原市に隣接。町名は、聖徳太子が建立した放光寺(片岡王寺)に由来するとされ、延喜式内・片岡神社や、聖徳太子が建立したと云われる達磨寺があります。「町の木:梅」「町の花:サツキ」を制定。
キャッチフレーズは「人にやさしい和(やわらぎ)のサイト 豊かで文化の薫り高い都市 水と緑と人がきらめく、風格ある生活環境都市」

明治22年(1889)、町村制の施行により葛下郡王寺村が発足。
1926年、王寺村が町制を施行し葛下郡王寺町が発足。
1957年、香芝町大字畠田(字尼寺を除く)を編入、現在に至っています。
マンホールには、中央に「和の鐘」、左右に「町の木:梅」「町の花:さつき」がデザインされています。(王寺駅前のメイン道路歩道に設置)






王寺本町1丁目交差点の角に設置された「和の鐘」。名称は聖徳太子の「以和為貴(和をもって尊しと為す)」の精神を尊重して命名されました。

昭和32年(1957)9月28日制定の町章は「頭文字の「王」「O」を組み合わせて、平和を愛好する精神とかぎりない将来の発展を意味づけ、現代の交通機関は「○即ち車輪」であり交通に恵まれている事を表現しています。」公式HPより




近畿日本鉄道マンホール。中央の社章は「円の内側の図形は、社名の頭文字「近」と「人」の文字を図案化し、社名と「人の和」を表現。さらに、全体の図形は、コロナを発する日輪と転動ばく進する車輪をかたどった紋様図形。」公式HPより

「近畿日本鉄道 王寺駅」

撮影日:2009年4月19日&2018年5月21日