22日(月)。わが家に来てから今日で2263日目を迎え、米人権団体によると、米国内では昨年3月以降 アジア系市民に対する差別的言動が3795件確認されたが、トランプ米大統領が新型コロナを「チャイナウイルス」「武漢ウイルス」と呼び、人種と結び付けた結果との見方が強い というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプの残した”負の遺産”はあまりにも大きい 4年後に復帰するなど言語道断





昨日、東京文化会館小ホールで東京・春・音楽祭 「東京春蔡チェンバー・オーケストラ」を聴きました オール・モーツァルト・プログラムで ①ディヴェルティメント ニ長調 K.136、②ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 ”トルコ風” 、③交響曲第25番 ト短調 K.183です
オール・モーツァルト・プログラムで ①ディヴェルティメント ニ長調 K.136、②ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 ”トルコ風” 、③交響曲第25番 ト短調 K.183です 演奏はヴァイオリン=堀正文(元N響コンマス)、枝並千花、北田千尋、城戸かれん、城所素雅(千葉響)、坪井夏美(東京フィル)、外園萌香、三輪莉子、山内眞紀、ヴィオラ=佐々木亮(N響首席)、中恵菜、山本周、チェロ=辻本玲(N響首席)、中条誠一、宮坂拡志(N響)、コントラバス=吉田秀(N響首席)、オーボエ=荒絵理子(東響首席)、森江繭子、ファゴット=水谷上総(N響首席)、佐藤由起(N響)、ホルン=日橋辰朗(読響首席)、熊井優(神奈川フィル)、矢野雄太(読響)(同)、山岸リオです
演奏はヴァイオリン=堀正文(元N響コンマス)、枝並千花、北田千尋、城戸かれん、城所素雅(千葉響)、坪井夏美(東京フィル)、外園萌香、三輪莉子、山内眞紀、ヴィオラ=佐々木亮(N響首席)、中恵菜、山本周、チェロ=辻本玲(N響首席)、中条誠一、宮坂拡志(N響)、コントラバス=吉田秀(N響首席)、オーボエ=荒絵理子(東響首席)、森江繭子、ファゴット=水谷上総(N響首席)、佐藤由起(N響)、ホルン=日橋辰朗(読響首席)、熊井優(神奈川フィル)、矢野雄太(読響)(同)、山岸リオです

自席はE列17番、左ブロック右から3つ目です 座席は市松模様配置ですが、後方のセンターブロックは空席が目立ちます
座席は市松模様配置ですが、後方のセンターブロックは空席が目立ちます
16人の弦楽奏者が配置に着きますが、女性陣は思い思いのカラフルな衣装で「春」の音楽祭を演出します 左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、その後ろにコントラバスという並びで、指揮者を置かないためコンマスの堀氏が座ったまま弾き振りします
左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、その後ろにコントラバスという並びで、指揮者を置かないためコンマスの堀氏が座ったまま弾き振りします
1曲目は「ディヴェルティメント ニ長調 K.136」です この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756‐1791)が1772年に作曲した3曲の作品(K.136 ~ K.138)の一つです
この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756‐1791)が1772年に作曲した3曲の作品(K.136 ~ K.138)の一つです モーツアルトが生まれたザルツブルクで作曲されたことから「ザルツブルク交響曲」とも呼ばれています
モーツアルトが生まれたザルツブルクで作曲されたことから「ザルツブルク交響曲」とも呼ばれています 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「プレスト」の3楽章からなります
第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「プレスト」の3楽章からなります
堀氏のリードで演奏が開始されますが、軽快な演奏を聴きながら 私は ある詩を思い出していました それはこういうものです
それはこういうものです
誰が風を見たでしょう
僕もあなたも見やしない
けれど木の葉をふるわせて
風は通りぬけてゆく
誰が風を見たでしょう
僕もあなたも見やしない
けれど樹立が頭を下げて
風は通りすぎてゆく
これは英国の女性詩人クリスティナ・ロゼッティ(1830‐1894)の「風」という詩です 日本では西城八十が和訳し、草川信が作曲しています
日本では西城八十が和訳し、草川信が作曲しています 出典は当ブログの読者みなみさんから教えていただきました
出典は当ブログの読者みなみさんから教えていただきました
初めてこの詩に接した時、「モーツアルトは風だ」と思いました モーツアルトの音楽は目には見えません。しかし、人の心に特別な感情を呼び起こして消えていきます
モーツアルトの音楽は目には見えません。しかし、人の心に特別な感情を呼び起こして消えていきます 演奏を聴きながら、耳の傍らを爽やかな風が通り抜けていくように感じました
演奏を聴きながら、耳の傍らを爽やかな風が通り抜けていくように感じました
2曲目は「ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 ”トルコ風” 」です この曲は1775年にまとめて作曲された4曲のヴァイオリン協奏曲(第2番~第5番)の最後の作品です
この曲は1775年にまとめて作曲された4曲のヴァイオリン協奏曲(第2番~第5番)の最後の作品です 第3楽章のロンドにトルコ風の楽想が用いられていることからこの呼び名があります
第3楽章のロンドにトルコ風の楽想が用いられていることからこの呼び名があります 第1楽章「アレグロ・アペルト」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「ロンド:テンポ・ディ・メヌエット」の3楽章から成ります
第1楽章「アレグロ・アペルト」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「ロンド:テンポ・ディ・メヌエット」の3楽章から成ります
堀氏が舞台中央で立奏し、弦楽奏者の後方にホルンとオーボエが2人ずつスタンバイします この曲だけ2008年ミケランジェロ・アバド国際ヴァイオリン・コンクール第1位、東京藝大大学院修了の城戸かれんがコンマスを務めます
この曲だけ2008年ミケランジェロ・アバド国際ヴァイオリン・コンクール第1位、東京藝大大学院修了の城戸かれんがコンマスを務めます 堀氏のリードで第1楽章に入りますが、終盤のカデンツァは聴きごたえがありました
堀氏のリードで第1楽章に入りますが、終盤のカデンツァは聴きごたえがありました 演奏は全体的に速過ぎもせず、遅すぎもせず、適切なテンポで進み、愉悦感溢れる演奏が堪能できました
演奏は全体的に速過ぎもせず、遅すぎもせず、適切なテンポで進み、愉悦感溢れる演奏が堪能できました
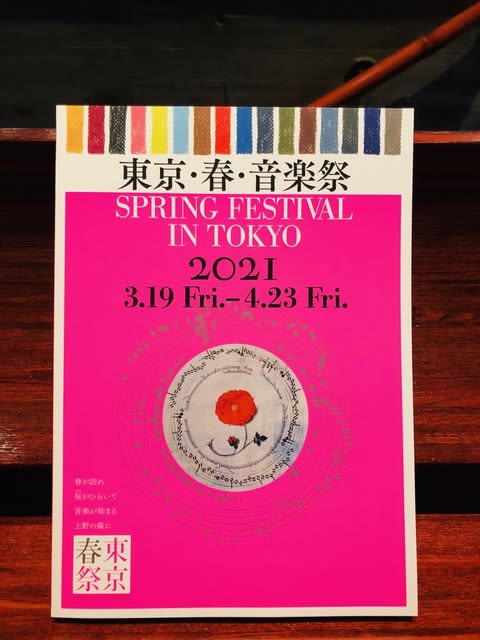
プログラム後半は「交響曲第25番 ト短調 K.183」です この曲は1773年に作曲された作品ですが、短調の交響曲はこの曲と第40番ト短調の2曲しかありません
この曲は1773年に作曲された作品ですが、短調の交響曲はこの曲と第40番ト短調の2曲しかありません 第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット&トリオ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります
第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット&トリオ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります
木管・金管奏者全員(8人)が加わり、堀氏のリードで第1楽章が開始されます 冒頭から緊迫感に満ちた音楽が展開しますが、この音楽を聴いて かつて舞台で、そして映画で観たピーター・シェーファーによる「アマデウス」を思い出しました
冒頭から緊迫感に満ちた音楽が展開しますが、この音楽を聴いて かつて舞台で、そして映画で観たピーター・シェーファーによる「アマデウス」を思い出しました 言うまでもなく、モーツアルトのミドルネームを採った「アマデウス」は、作曲家サリエリによるモーツアルトの暗殺をテーマにしていますが、作品の冒頭場面で衝撃的に使われているのがこの交響曲の冒頭の音楽なのです
言うまでもなく、モーツアルトのミドルネームを採った「アマデウス」は、作曲家サリエリによるモーツアルトの暗殺をテーマにしていますが、作品の冒頭場面で衝撃的に使われているのがこの交響曲の冒頭の音楽なのです 弦楽合奏に管楽器が加わって緊張感あふれる音楽が展開しますが、東響首席・荒絵理子のオーボエが素晴らしい
弦楽合奏に管楽器が加わって緊張感あふれる音楽が展開しますが、東響首席・荒絵理子のオーボエが素晴らしい この曲の悲劇性を際立たせていました
この曲の悲劇性を際立たせていました 管楽器ということでは、第3楽章の後半「メヌエット」におけるオーボエ、ファゴット、ホルンによる「トリオ」が素晴らしい演奏でした
管楽器ということでは、第3楽章の後半「メヌエット」におけるオーボエ、ファゴット、ホルンによる「トリオ」が素晴らしい演奏でした 終楽章は短調特有のデモーニッシュな音楽が緊迫感を増大させ、19歳のモーツアルトの複雑な心情を表しているかのようでした
終楽章は短調特有のデモーニッシュな音楽が緊迫感を増大させ、19歳のモーツアルトの複雑な心情を表しているかのようでした
満場の拍手にカーテンコールが繰り返され、アンコールにモーツアルト「交響曲第33番変ロ長調K.319」から第3楽章「メヌエット」が演奏され、再度大きな拍手を浴びました
この日のコンサートは、モーツアルトが16歳から19歳までの青年期に作曲した作品が演奏されましたが、とても10代で作曲したとは思えないほど充実し、天才が際立っていました この日限りの臨時編成オケ「東京春蔡チェンバー・オーケストラ」はそのことを演奏で表しました
この日限りの臨時編成オケ「東京春蔡チェンバー・オーケストラ」はそのことを演奏で表しました
















