8日(火)。今回は最近観た映画の紹介を。ポーランド映画「ショパン~愛と哀しみの旋律」をシネスイッチ銀座で観た。昨年がショパン生誕200年だったことに因んで制作された。ショパン役は滝沢秀明似のイケメン俳優。女性の観客が圧倒的に多かったのも頷ける。最初に1つだけ注文をつけるとすれば、台詞は英語でなくポーランド語にしてほしかった。英語を話すショパンにはどうも違和感がある。
ショパンの生きた19世紀のポーランドは帝政ロシアの専制政治下にあった。彼は自由な芸術活動を求めてポーランドを離れるが、パリの社交界は彼の音楽を受け入れてくれない。その後、人気作曲家フランツ・リストの紹介でパリ・デビューを果たし、人気作家ジョルジュ・サンドと出会う。静かな音楽環境を求めてサンドと彼女の長男モーリス、長女ソランジュとともにスペイン・マヨルカ島、フランス・ノアンへと移り住んでいく。
この映画はもちろんショパンが主人公であるのだが、見方によってはジョルジュ・サンドを中心に物語が展開している印象を受ける。彼女は”男装の麗人””恋多き女”と言われたが、その存在感は圧倒的だ。彼女は肺病のショパンの生活と音楽活動を支えたが、映画では子供たち(と言っても大人に近い)とショパンの間に立たされ、両方から「どっちが大切なのか」と迫られ、親の立場と恋人の立場との間で心が揺れ動くナイーブな面も描かれている。
当時圧倒的な人気があったリストがサロンで「ショパンの練習曲第12番「革命」を弾いて「これはショパンの曲」と彼を紹介し、ショパンが聴衆に応えてノクターン第20番嬰ハ短調を弾くシーンがある。これをきっかけにショパンはパリ・デビューを果たすのだが、こうしたことが実際にあったのかもしれない。ちなみに「革命」エチュードは横山幸雄の演奏が使われている。
ピアノ協奏曲第1番、練習曲第13番「エオリアン・ハープ」、同23番「木枯らし」、夜想曲第20番、同21番、同7番、ワルツ第19番、マズルカ第23番、同11番、チェロ・ソナタなど20曲以上の名曲が全編を通して流れる。エンディングにピアノ協奏曲第2番の第2楽章が静かに流れる。とても印象的だ。これこそ「愛と哀しみの旋律」ではないか!
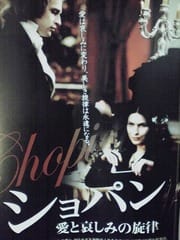
ショパンの生きた19世紀のポーランドは帝政ロシアの専制政治下にあった。彼は自由な芸術活動を求めてポーランドを離れるが、パリの社交界は彼の音楽を受け入れてくれない。その後、人気作曲家フランツ・リストの紹介でパリ・デビューを果たし、人気作家ジョルジュ・サンドと出会う。静かな音楽環境を求めてサンドと彼女の長男モーリス、長女ソランジュとともにスペイン・マヨルカ島、フランス・ノアンへと移り住んでいく。
この映画はもちろんショパンが主人公であるのだが、見方によってはジョルジュ・サンドを中心に物語が展開している印象を受ける。彼女は”男装の麗人””恋多き女”と言われたが、その存在感は圧倒的だ。彼女は肺病のショパンの生活と音楽活動を支えたが、映画では子供たち(と言っても大人に近い)とショパンの間に立たされ、両方から「どっちが大切なのか」と迫られ、親の立場と恋人の立場との間で心が揺れ動くナイーブな面も描かれている。
当時圧倒的な人気があったリストがサロンで「ショパンの練習曲第12番「革命」を弾いて「これはショパンの曲」と彼を紹介し、ショパンが聴衆に応えてノクターン第20番嬰ハ短調を弾くシーンがある。これをきっかけにショパンはパリ・デビューを果たすのだが、こうしたことが実際にあったのかもしれない。ちなみに「革命」エチュードは横山幸雄の演奏が使われている。
ピアノ協奏曲第1番、練習曲第13番「エオリアン・ハープ」、同23番「木枯らし」、夜想曲第20番、同21番、同7番、ワルツ第19番、マズルカ第23番、同11番、チェロ・ソナタなど20曲以上の名曲が全編を通して流れる。エンディングにピアノ協奏曲第2番の第2楽章が静かに流れる。とても印象的だ。これこそ「愛と哀しみの旋律」ではないか!
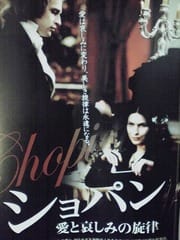














 飲んでいると、ケータイにメールが入った。娘からだ。「今度の日曜の13時から空いてる?サイ・イエングアンっていうコロラトゥーラ・ソプラノ歌手のコンサートがあるんだけど、行きませんか?」という内容。
飲んでいると、ケータイにメールが入った。娘からだ。「今度の日曜の13時から空いてる?サイ・イエングアンっていうコロラトゥーラ・ソプラノ歌手のコンサートがあるんだけど、行きませんか?」という内容。 コースがあるから、それに行かないかということだった。「何だ、ランチが目的じゃないか?」と思ったが、そうでもないかな、と思い直した。というのは、娘は機嫌がいいとモーツアルトの歌劇「フィガロの結婚」のケルビーノのアリアやヘンデルのアリアなどをイタリア語で歌ったり
コースがあるから、それに行かないかということだった。「何だ、ランチが目的じゃないか?」と思ったが、そうでもないかな、と思い直した。というのは、娘は機嫌がいいとモーツアルトの歌劇「フィガロの結婚」のケルビーノのアリアやヘンデルのアリアなどをイタリア語で歌ったり しているからだ。どうも美大の時に何かの授業で習ったらしい。北海道の長万部の大学寮で1年生を過ごした息子
しているからだ。どうも美大の時に何かの授業で習ったらしい。北海道の長万部の大学寮で1年生を過ごした息子 も誘って行くことにした。
も誘って行くことにした。 夜の女王役においてはコロラトゥーラ・ソプラノとして他の追随を許さない圧倒的な存在感と歌唱力で国際的な評価を得る」とあった。レストラン内の会場で歌うらしいから歌手と観客は近いはずだ。これは楽しみなコンサートになりそうだ。プログラムの内容は不明だが、是非、夜の女王のアリア
夜の女王役においてはコロラトゥーラ・ソプラノとして他の追随を許さない圧倒的な存在感と歌唱力で国際的な評価を得る」とあった。レストラン内の会場で歌うらしいから歌手と観客は近いはずだ。これは楽しみなコンサートになりそうだ。プログラムの内容は不明だが、是非、夜の女王のアリア を歌ってほしい
を歌ってほしい






