21日(土).昨夕,地下の串焼きRでS監査役,E部長,T君,K君と飲みました


 店長が自衛隊出身の元気な人に替わりました
店長が自衛隊出身の元気な人に替わりました さんざん飲んで,今朝はまた頭痛です.何の話をしたのだろうか?よく覚えていません
さんざん飲んで,今朝はまた頭痛です.何の話をしたのだろうか?よく覚えていません

 閑話休題
閑話休題 

真理幸子の「ふたり狂い」(早川文庫)を読み終わりました ご存知「殺人鬼フジコの衝動」の著者による期待作です.
ご存知「殺人鬼フジコの衝動」の著者による期待作です.
女性誌「フレンジー」の人気連載小説「あなたの愛へ」の同姓同名の主人公が自分だと思い込んだ川上孝一は,思い余って著者の榛名ミサキを刺してしまいます 裁判を通していろいろな事件が明らかになっていきますが,その背後にはマイコという一人の女の存在があります.最初から最後まで読んで?と思って,再び最初に戻って読んでしまいました
裁判を通していろいろな事件が明らかになっていきますが,その背後にはマイコという一人の女の存在があります.最初から最後まで読んで?と思って,再び最初に戻って読んでしまいました 誰が加害者で誰が被害者か・・・・わけがわからなくなってきます.「殺人鬼フジコの衝動」よりも明るい内容なので安心して読めます
誰が加害者で誰が被害者か・・・・わけがわからなくなってきます.「殺人鬼フジコの衝動」よりも明るい内容なので安心して読めます

さて,その本の中の「ホット・リーディング」と題する物語の中に「ソース・モニタリング・エラー」という言葉が出てきました。
「こうやって取材させてもらっていると、記憶違いや思い込みっていうのが多くて混乱することが多いんですよ。人の記憶って、あいまいなものでしょう?他からの影響で記憶そのものが捏造されてしまうこともあるわけで。えっと、確か、・・・・そうそう、ソース・モリタリング・エラーっていうんですって」
これを読んで、そう言われてみれば自分にもそういう経験があったな、と思い出しました
あれは、高校を卒業してから20年以上経った頃のクラス会での出来事でした 授業をボイコットした時の話になり、首謀者のSをはじめ、そこに居合わせた男たちが「新米女性教師Wの担当する”世界史”の授業をボイコットした」と言うのです
授業をボイコットした時の話になり、首謀者のSをはじめ、そこに居合わせた男たちが「新米女性教師Wの担当する”世界史”の授業をボイコットした」と言うのです 私の記憶とは違うので「それって音楽の授業じゃなかったっけ?」と口をはさんだのですが、皆は「世界史だ」と言います。どうも自分だけが記憶違いをしていたようです
私の記憶とは違うので「それって音楽の授業じゃなかったっけ?」と口をはさんだのですが、皆は「世界史だ」と言います。どうも自分だけが記憶違いをしていたようです
どうしてそのような記憶違いをして、長い間勘違いしたまま過ごしてきたのか、よく考えてみた結果、「自分は新米の女性教師をいじめるような行為には加担していない、と思いたい」、一方「普段、自ら顧問を務める吹奏楽部の部員だけを”えこ贔屓”している音楽のM教師の授業をボイコットしたい」という願望があって、いつか、その願望が「音楽の授業をボイコットする」という夢の形で結実し、その夢を現実と思い込んで記憶していた、ということのようです
ついでに言えば、中学の時は音楽が大好きでした それはH先生が音楽の楽しさを教えてくれた素晴らしい先生だったからです
それはH先生が音楽の楽しさを教えてくれた素晴らしい先生だったからです 今でもよく覚えているのは中学3年の時の音楽の成績です。1学期=2、2学期=4、3学期=5とグングン上がっていきました。H先生のお陰でわがクラスは学校代表として合唱コンクールにも出場しました
今でもよく覚えているのは中学3年の時の音楽の成績です。1学期=2、2学期=4、3学期=5とグングン上がっていきました。H先生のお陰でわがクラスは学校代表として合唱コンクールにも出場しました それが、高校に入った途端、上に書いたような理由で、音楽が大嫌いになってしまいました。その当時は「何がベートーヴェンは偉大だ
それが、高校に入った途端、上に書いたような理由で、音楽が大嫌いになってしまいました。その当時は「何がベートーヴェンは偉大だ 何がクラシック音楽は素晴らしいだ
何がクラシック音楽は素晴らしいだ 」と反発していました
」と反発していました 今の自分からはとても考えられない状況でした。
今の自分からはとても考えられない状況でした。
つくづく思うことは,いつの時代でも変わらないのは,いかに教師の影響力が大きいか,ということです












 「音楽家たちの饗宴2011-2012・第4回」で,早くも前半最後のコンサートです.プログラムはチェロ合奏による①クレンゲル「4本のチェロのための4つの小品から」,②カザルス「東方の三賢人」,③同「サルダナ」,④ブラームス「ホルン三重奏曲変ホ長調」の4曲です
「音楽家たちの饗宴2011-2012・第4回」で,早くも前半最後のコンサートです.プログラムはチェロ合奏による①クレンゲル「4本のチェロのための4つの小品から」,②カザルス「東方の三賢人」,③同「サルダナ」,④ブラームス「ホルン三重奏曲変ホ長調」の4曲です 今回の出演者は昼間,金曜,土曜に定期公演で演奏するマーラーの交響曲第9番のリハーサルをこなしてから夜の演奏会に望んでいるという話でした.楽員の皆さんも大変ですね
今回の出演者は昼間,金曜,土曜に定期公演で演奏するマーラーの交響曲第9番のリハーサルをこなしてから夜の演奏会に望んでいるという話でした.楽員の皆さんも大変ですね 2曲目の「東方の三賢人」はキリストの降臨をテーマにした詩をもとに書かれました.今度はチェロが6本です.最初のメロディーをフーガで追いかけていく面白い曲です.気のせいか,途中で”カオス”を感じたのですが,終わると首席奏者の川上徹の提唱でフィナーレ部分を(”61から”と言っていたので61小節から?)アンコール演奏しました.前半のプログラムの時間があまりにも短いので時間延長のサインが出たのでしょうか?まあ,楽しめました
2曲目の「東方の三賢人」はキリストの降臨をテーマにした詩をもとに書かれました.今度はチェロが6本です.最初のメロディーをフーガで追いかけていく面白い曲です.気のせいか,途中で”カオス”を感じたのですが,終わると首席奏者の川上徹の提唱でフィナーレ部分を(”61から”と言っていたので61小節から?)アンコール演奏しました.前半のプログラムの時間があまりにも短いので時間延長のサインが出たのでしょうか?まあ,楽しめました


 これで楽員の顔をよく覚えて,定期演奏会に臨めばコンサートの楽しみが倍増します.新日本フィルの楽員の皆さま,これからも良い演奏を聴かせてください.いつも応援しています.頑張ってください
これで楽員の顔をよく覚えて,定期演奏会に臨めばコンサートの楽しみが倍増します.新日本フィルの楽員の皆さま,これからも良い演奏を聴かせてください.いつも応援しています.頑張ってください
 最初に結論を言います.凄い映画です.感動しました
最初に結論を言います.凄い映画です.感動しました これは将来の明るい展望がない前2作とはまったく違う作品です.なお,ヒミズとは”日不見”(不と見は漢文でいうレ点でひっくり返る)で,土の中で日のめを見ない”もぐら”のことです
これは将来の明るい展望がない前2作とはまったく違う作品です.なお,ヒミズとは”日不見”(不と見は漢文でいうレ点でひっくり返る)で,土の中で日のめを見ない”もぐら”のことです 住田は,借金を作って蒸発していた父親が帰ってくると,口のききかたが悪いと言われ殴る蹴るの暴行を受けます
住田は,借金を作って蒸発していた父親が帰ってくると,口のききかたが悪いと言われ殴る蹴るの暴行を受けます おまけに母親は中年男と駆け落ちして一人ぼっちになってしまいます.茶沢も親から虐待を受け,家に居られない状況下にあります.住田は,父親から「お前はいらないんだよ」と罵られて,ついに切れて父親の頭をブロックで殴りつけて死なせてしまいます
おまけに母親は中年男と駆け落ちして一人ぼっちになってしまいます.茶沢も親から虐待を受け,家に居られない状況下にあります.住田は,父親から「お前はいらないんだよ」と罵られて,ついに切れて父親の頭をブロックで殴りつけて死なせてしまいます



 という面持ちです.
という面持ちです.


 チョンならではのタクトさばきです.終盤ではホルン8人を立たせて演奏させますが,これはマーラーの指示どおりです.そして弦,管,打楽器総動員による圧倒的なフィナーレを迎えます
チョンならではのタクトさばきです.終盤ではホルン8人を立たせて演奏させますが,これはマーラーの指示どおりです.そして弦,管,打楽器総動員による圧倒的なフィナーレを迎えます


 でしたが,それはロベール・ルパージュという演出家によるものでした
でしたが,それはロベール・ルパージュという演出家によるものでした
 寅さんではありませんが,「おい,そこの青年!元気出せや
寅さんではありませんが,「おい,そこの青年!元気出せや
 とくに弱音が素晴らしく,これは彼の演奏の特性かも知れないと思います.ゆったりとしたテンポで朗々と歌わせるのも彼の特徴かもしれません
とくに弱音が素晴らしく,これは彼の演奏の特性かも知れないと思います.ゆったりとしたテンポで朗々と歌わせるのも彼の特徴かもしれません



 混沌とした靄の中から明るいロマン的なメロディーが立ち昇るところは、新しい時代の夜明けを感じさせます
混沌とした靄の中から明るいロマン的なメロディーが立ち昇るところは、新しい時代の夜明けを感じさせます
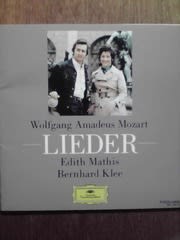
 ”冷え込み”といえば思い出すことがあります。
”冷え込み”といえば思い出すことがあります。





