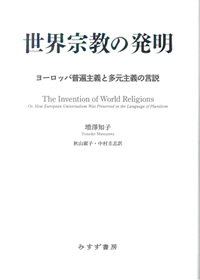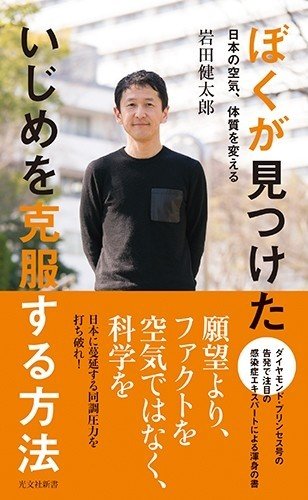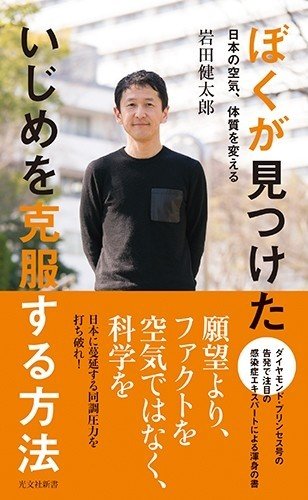
「いじめの構造そのものを、ぶっ壊す可能性を提示しなければならない」―――岩田健太郎 教授に聞く
光文社新書
2020/04/14 10:35
「子供のいじめがなくならないのは、そもそも日本の大人社会が、いじめ体質だからだ――。」先日、「あとがき」と「目次」を先行公開した光文社新書の新刊『ぼくが見つけたいじめを克服する方法――日本の空気、体質を変える』が、本日発売となった。刊行に際し、著者である神戸大学の岩田健太郎教授に、話を聞いた。
なぜいま注目の感染症の専門家が、「いじめの本」なのか。岩田氏がこの本に込めた思い、そして今こそ読者に伝えたいこととは?
写真・野澤亘伸/聞き手・光文社新書編集部
画像8
・・・・・・・・・・・・・・・・・
目次
「世の中こんなもんだ」といじめを受け入れる日本の空気
いじめの前提である構造そのものをぶっ壊さなければならない
本を書く、論文を書くということは、世の中の前提を揺さぶること
空気は、何の役にも立たない。少なくとも感染対策にとっては有害無益
同調圧力の強いところでは、科学的な態度は育まれない
プロではないから、異論が出ると混乱する
いじめの構造は、滅びへの道
党派性ありきで、利用されるデータ
自分が変わる覚悟がない討論は、たんなる演説にすぎない
こういう態度だったらいじめていい、という根拠はない
すべて表示
「世の中こんなもんだ」といじめを受け入れる日本の空気
――いじめについて書こうと思った理由を教えてください。
岩田 はい。本にも書きましたが、ぼく自身、ずっといじめにあっていたというのが一つの理由です。それから身近にも、いじめにあって苦しんでいる人がいました。
これまでにも、「いじめの克服法」的な本はたくさん出版されています。
今回ぼくは、日本でいじめについて扱っている本は、ほぼ全部読みました。それから外国の本も読んだのですが、どれもまあ、全然ピンとこなかった。「こんなんでいじめなんてなくなるわけないな」と思いながら、読みました。
それで、やっぱり、自分で書くしかないなと思ったんです。
――どんな人に向けて書かれたのでしょうか。
岩田 想定読者はとくにないです。というより、これも本にも書いたように、日本は、基本的に社会の構造そのものが「いじめ社会」なので、たぶん、ほぼ全員が関係者なんです。
だから、自分は「いじめに関係ない」って思っている人も、実は関係している。気づいていないだけで。
あらゆる社会構造に、いじめの構造が蔓延しているんです。
だから、いじめと無縁でいる人ってほとんどいないと思います。それに気づいてほしい。そういう意味では、誰が読んでもいいと思いますし、誰にでも読んでもらいたいです。
――医学界や医療現場のことも書かれています。「この空気を変えなければ」というような思いは常にあるのでしょうか。
岩田 はい。さっきも言いましたように、いじめは構造問題なのですが、その構造を、多くの場合は「仕方がない」と思っているんですね。世の中こんなもんだから、って、みんな言う。で、世の中こんなもんだって受け入れる人が、なんかエライ人、みたいになってしまっているじゃないですか。
ぼくが、クルーズ船に入ったときも、何か、みんなを混乱させたとか、みんなの空気を乱したなどと言われましたけれども、そもそも、感染対策の専門家が船に入って、「ここの対策の仕方がおかしい」って指摘して、混乱する現場が悪いんです。その程度で混乱するというのは。
これは本当に、同調圧力そのものでして、「これまでやってきた空気を乱すな」「みんなと同じことを言わないと全部排除」みたいな、まさにあれは排除の論理なんですけど、その論理がそもそもおかしいだろうっていう話だと思うのです。
画像2
いじめの前提である構造そのものをぶっ壊さなければならない
岩田 日本では常識と言われていること、みんなが「こうしなきゃだめだろ」って言うノーム(norm)、つまりまさに「規範」みたいなものですが、それがそもそもいじめの構造の正体そのものなんです。その「常識だろ」って言っているものが、じつは「非常識」かもしれない、っていうことに、気がつかない。
この日本特有の構造があるので、たぶん、同じ悲劇がずっと繰り返されると思うんですね。
いじめで自殺する子が出る。ニュースで報じられる。また出ました、また出ました、また出ました……そして今度は、学校がいじめを隠蔽していました、教育委員会も看過していました……こんなことがずっと繰り返されているじゃないですか。
もう、延々と続きますよ。いつまでたってもなくならない。だってそれは、この「いじめの構造」を壊すっていう、前提をやろうとしていないからです。
神戸でもつい最近に問題になりましたけど、教師のあいだでもいじめはあるし、教育委員会の中でもいじめはあるし、自治体でもいじめはあるし、政府の中でも当然いじめはある。
いじめが構造化されていて、常識化されていて、そしてその構造を受け入れないと排除するという、さらにまた二重のいじめが起きる。だから、構造そのものをぶっ壊すっていう可能性を提示しないとならないと思うんです。
本を書く、論文を書くということは、世の中の前提を揺さぶること
岩田 本を書くというのは、常に、可能性を提示する行為だと思います。我々が常識だと思っていて、ここから一歩も動かなくていいって思っているのを、動かすべきだって言うのが、たぶん、本だと思うんですよね。それが、ものを書く根拠になっています。それで、この本も書きました。
これは学術論文でも普通の本でも全部そうだと思うんですけど、「世の中がこうなっていますよ」っていうところを揺さぶらないと、たぶん、ものを書く根拠っていうのはない。
2011年に出版した『1秒もムダに生きない――時間の上手な使い方』(光文社新書)という本も――あれは他者のまなざしに規定されずに生きることが、時間を、そして自分と周りの人を大切にすることになる、ということを書いた本なのですが、――あの本を書いたばかりのときは、相当、何バカなことを言ってるんだ、というような意見のほうが多かったんですね。
最近になって、好意的な感想をいただくことが増えてきました。十年近くたって、ようやく、理解されてきたのかな、と思います。
画像4
空気は、何の役にも立たない。少なくとも感染対策にとっては有害無益
――マレーシア在住のライターの野本響子さんが、岩田先生の告発と、それに対するバッシングをきっかけに『cakes』に書いた記事(「日本でコミュ障とよばれる人が、海外で活躍できる理由」)が話題になりました。その記事の中で、日本でコミュ力があるとされる人が、海外では全く役に立たないことが多く、逆に日本で「コミュ障なんです」と言う人が、海外で大活躍している、という指摘がありました。野本さんは、日本特有の同調圧力についても、繰り返し指摘されていますね。
岩田 あ、あれについては、すごく同意しました。
あのクルーズ船に関する動画をめぐっては、本当にいろいろな人からいろいろなことを言われたのですが、海外の方――これはべつに英語圏の方だけではなくて、フランス、デンマーク、中国、韓国……まあいろんな国の人からいろいろな言葉をいただいたのですが、「コミュニケーションの仕方が悪い」って言われたのは日本人からだけです。
では、日本でコミュニケーションの仕方が良いっていうのは、どういう意味かというと、反対意見を言わない。みんなに合わせる。黙ってる。これがコミュニケーション・スキルだと勘違いしている。
でも、他の国々の人の言うコミュニケーション・スキルは全然違っていて、ちゃんと意見を言う。で、間違っていれば、指摘する。これがコミュニケーションなんです。何が間違っているのか、なぜ間違っているのかまで、きちんと説明できる。
日本の場合は、意見や説明能力というのは、コミュニケーション能力とは全く関係がなくて、単に、空気を乱さない、みんなに合わせる、それがコミュニケーション能力だと勘違いされているんですね。
だから会議が退屈で、生産性がないんです。
日本でコミュ力が高いとされる、場の空気を読むだけの人は、日本の外ではまったくコミュニケーション能力とは評価されません。それは空気を醸造しているだけですから。
日本では、空気さえ醸造していればそれでいい、というところがあるんです。
でも、空気は、実質的に何の役にも立たない。少なくとも感染対策にとっては有害無益です。
画像5
同調圧力の強いところでは、科学的な態度は育まれない
岩田 本にも一部書いていますが、基本的に日本の医学界は、同調圧力はもうめちゃめちゃ強いです。いじめも多いですし。
とはいえ、世界すべての医療界を知らないので、すべての国々については分からないですけれど、たとえばアメリカでも、同調圧力はあります。
ただ、アメリカの場合は、同調圧力に抗う力も結構大きいのです。
まあでも、イギリスなんかではさすがに、「みんなの意見を一致させなきゃだめだ」とか、そういう前提はぜんぜんないですね。必ず異論を言う人はいますし、異論、つまり、自分と意見が違うというのは、べつに否定の条件ではないので、そこで人格否定などをされることはまったくない。
イギリスでは、今回のCOVID対策として、当初、多くの人に感染させて、新型ウイルスへの免疫を持つ人を増やすことで集団免疫を形成して、冬の感染をスローにしよう、という話がありました(「集団免疫」戦略)。
ところが、あっちこっちから大反対が出たんですよね。で、結局、ボリス・ジョンソンたちは、意見を変えた。やっぱり方針を変えますと言って朝令暮改にしたんです。
あれが、正しいやり方なんです。
科学的であるっていうのは、首尾一貫していることではなくて、間違っていることが分かったらそれを認める。そしてちゃんと議論をして、反対意見も出て、それについて、また反論するか同意するかして、で、やり方を変えるときは変える。
これが、基本的に論理的な考え方だし、コミュニケーションの仕方なんです。
プロではないから、異論が出ると混乱する
岩田 ところが日本の場合は、もう決めたことだから、とか、みんながやるって言ってるのに、なんでおまえは文句言うんだみたいな感じで、一度決めたことは変更できない。
これも繰り返し言っていることですが、プランAばっかりで、プランBがない。で、プランAがうまくいかなくても、そのまま突き進んでしまう。
これは、ノモンハンとか、インパール作戦とか、あのへんの失敗と同じパターンです。プランが1つしかなくて、それがポシャっても、全滅するまで進みつづける。
『失敗の本質』っていう本がありますけど、あの本で問題にされているのと同じ、硬直した考え方です。まさに構造的な失敗のパターンですよね。間違いは早く見つけて方針転換するというイギリスのやり方は、正しいやり方です。
したがって、異論はどんどん言うべきです。
クルーズ船の件でも、何かイワタが現場を混乱させたとか言われましたが、先ほども言いましたけれど、そもそも反対意見言ったぐらいで混乱する現場が悪いんですよ。「その程度で混乱すんな」って言いたいですよね、プロなんだから。
まあ、アマチュアだったのかもしれないですが。本来はプロが入っているべきで、プロだったら意見の衝突があっても混乱なんてしないはずなんです。
これは、スポーツの世界でも何でもそうだと思うのですが、サッカー選手が、たとえばある選手が「こうするべきだ」って主張して、そこで混乱したら、それはプロのサッカー選手ではないですよね。
現場を混乱させたっていう指摘は、まったく事実だったようですし、そういう意味では申し訳なかったなとは思うんですけど、でもぼくに言わせると、なんでそんなことで混乱するんだって思いますね。その程度のことで混乱するっていうのは、もうアマチュアそのものじゃないかと思うんです。
画像4
いじめの構造は、滅びへの道
岩田 みなで合意して進んでいるものに異議が出て、止められること、空気を乱されることに抵抗が強い。これはいじめの構造の前提になっている同調圧力でもあるのですが、これこそが、滅びのパターンです。
たとえば、3月に、消費税の減税を求める声が上がったときに、自民党の二階幹事長が、「消費税というものをつくった時にどれほどの苦労があったか」「仮に下げた場合に、いつ元に戻すのか、責任は誰が負うのか」などと発言しました。
ぼくは経済学者じゃないんで、消費税を下げるべきなのか、このままでいくべきなのか、にわかに判断がつかないのですが、ただ、「みんなで頑張ってつくったものだから変えられない」っていうその論理は、極めて間違っているなと思いました。一番やばいパターンだと思います。でもこれは日本では本当によく見られることです。
ぼくは島根県の人間なんで、中海・宍道湖の干拓・淡水化事業の記憶が焼き付いています。あの干拓事業は、意味がないって分かっていたのに、二十何年間ずーっと計画が続いてました。もうまさに、走り出すと引き返せない。
間違っていたら、撤回して、直すっていうことは、いちばん初歩的な、小学生ぐらいで覚えるべきことです。それを大人ができない。日本は本当に、大人が子供です。それはやっぱり、ディベートとかディスカッションみたいな訓練を全然されていないからだと思います。
だから、ある意味では、日本人の大多数がコミュ障なのではないかと思います。コミュニケーションというスキルがなくて、単に、みんなに合わせることで、コミュニケーションをとったつもりになっている。
議論によって前に進むんじゃなくて、声のでかい人の一喝とか、みんなの雰囲気とかで、ものが決まっていくんです。だから、非理性的で、理不尽なものごとの決まり方になるんです。
党派性ありきで、利用されるデータ
――空気を乱さないことばかりを考えて、自分自身で何が正しいかを考える習慣がないということですか。
岩田 はい。つまり、何が正しいかっていうよりも、「みんながこれで乗っかれるか」とか、「みんながそれで怒らないか」とか、そういうのを基準にものが決まるんです。
東京オリンピックに関しても、3月中旬に、「いま開催すべきでない」ということをブログで書きました(「2020年夏に東京オリンピックを開催すべきでない理由」楽園はこちら側)。
たとえば、開催すべきか開催すべきでないか、という議論をするからには、どういう基準以上だったら開催して、どういう基準以下だったら開催できないっていう、その基準線を引くべきなんです。
それをしないで、「やる」「やらない」っていうところからまず議論をすると、ただのイデオロギーの主張になって、意味がない。だから、「ここまでならば開催」「これ以下だったらしない」っていう、科学的で論理的な線を引くべきなんですよね。
で、その線を引いてみると、感染症屋的には「開催は無理やな」って思ったから、開催すべきでない、って書いたんです。べつに最初から「開催しないありき」ではない。
つまり、大事なことですが、「○○をすべき」「すべきでない」は、結果であって、前提ではないわけですね、本来は。
だけど日本の場合は、すぐに党派性を出して、まずは「どっち派だ」っていう派閥を決めて、で、結局自分の議論に都合のいいデータをくっつけて、なんとなくそれっぽい主張にしてしまいます。
画像6
自分が変わる覚悟がない討論は、たんなる演説にすぎない
岩田 『朝まで生テレビ』っていうテレビ番組がありますね。あれがそうなんですけれど、あの番組に出てくる人たちって、始まってから終わるまで、首尾一貫して、意見が変わらないでしょう。
意見が変わらないっていうことは、進歩がないってことで、同じことをずーっと言い続けているわけです。
っていうことは、あの人たちは、議論をしているんじゃなくて、単に演説を繰り返しているだけで、それで朝まで過ごしている。いちばん非生産的な時間の使い方です。
「番組が始まったときはこう思っていたけど、おまえの意見聞いて、やっぱ俺、意見変わったわ」っていう人が一人も出ないっていうのは、何も進歩がないっていうことです。
哲学者の鷲田清一先生がよくおっしゃることですが、自分が変わる覚悟がなければ、対話というのは成立していないんですよ。だけど、多くの日本人は、変わることはしないという前提で、演説を繰り返して、それを議論だと勘違いしています。
それは主張の連打であって、議論ではない。議論というのは、自分が変わるというのが前提ですから。
こういう態度だったらいじめていい、という根拠はない
――それでは最後に、もういちど読者にメッセージを。
岩田 はい、そうですね。この本を読んだ人からの、ありがちな反応として、「おまえがそういう態度をとるから、みんなに文句言われるんだ」というようなことを言う人が、ぜったいに出てくると思うんです。
で、ぼくが言いたいのは、「こういう態度だったらいじめてもいい」っていう前提がそもそも間違っている。その言い回しそのものが、そもそもいじめの正当化の一番の遠因で、相手がどういう態度であろうと、それはいじめていい根拠にならないのだということです。
子供のいじめの場合でもそうです。多くの学校の先生は、「ああ、それは、あなたにも悪いところがあったでしょ」みたいな指導をするじゃないですか。
だから、それがそもそも、前提としてあかん。
本の中でも、愛子さまのエピソードでも出しましたが、「仕方がない」「いじめていい」という前提とか根拠っていうのは、まったくないんですよ。そんなものは、全部否定です。それは、すべてリンチなんです。
それが、たとえどんなに有名な人であろうが、芸能人であろうが、あるいは、まったく無名の人であってもそうなんですけど、これこれこういう理由があるから、いじめは許容されるとか、差別が許容される、というのが、その語調そのものが、そもそも間違っているっていうことです。
それは絶対にいじめることの根拠にならないし、してはいけない、っていうところだけは、分かってもらえればいいなと思います。
画像7
岩田健太郎(いわたけんたろう)
1971年島根県生まれ。島根医科大学(現・島根大学医学部)卒業。沖縄県立中部病院、ニューヨーク市セントルークス・ルーズベルト病院、同市ベスイスラエル・メディカルセンター、北京インターナショナルSOSクリニック、亀田総合病院を経て、2008年より神戸大学。神戸大学都市安全研究センター感染症リスクコミュニケーション分野および医学研究科微生物感染症学講座感染治療学分野教授。著書に『予防接種は「効く」のか?』『1秒もムダに生きない』『99・9%が誤用の抗生物質』『「感染症パニック」を防げ!』『サルバルサン戦記』『ワクチンは怖くない』(以上、光文社新書)、『インフルエンザ なぜ毎年流行するのか』(ベスト新書)、『「患者様」が医療を壊す』(新潮選書)、『絵でわかる感染症 with もやしもん』(講談社)など多数。
☆過去の記事はこちら → 岩田健太郎『ぼくが見つけたいじめを克服する方法』あとがき&目次を先行公開 「あとがき」と「目次」が読めます!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画像9
『ぼくが見つけたいじめを克服する方法――日本の空気、体質を変える』4月14日(火)発売
ダイヤモンド・プリンセス号の告発で注目の
感染症エキスパートによる渾身の書
願望より、ファクトを
空気ではなく、科学を
日本に蔓延する同調圧力を打ち破れ!
【内容紹介】
子供のいじめは一向に減る気配がない。それはそもそも、日本社会、それも大人の社会がいじめ体質だからだ。大人の社会でいじめが普遍的で常態化しており、「世の中そんなものだ」と多くは納得すらしている。本書では、どうしたらこの悪循環を断ち切り、いじめが蔓延しない社会にできるかを提案する。
自らもコミュ障で、いじめられっ子だったという著者。さまざまな経験の末に、それに立ち向かい、克服する方法を導き出している。「いじめの正体は『空気』だ」とする著者の姿勢は一貫している。大事なのは、空気よりもファクト。いじめを認知し、オープンにする。医療においても、空気によるいじめはある。大事なのは科学であり、事実である。空気なんてどうでもよい。あえて空気を読めないふりをすればよいのだ。ファクトを無視したフェイクな社会において、多くの人が健康を損ない、苦しむことになるのだ――。
厚労省の体質の問題点や、注目を集めた新型コロナウイルス流行時のクルーズ船の感染対策告発にも言及する。