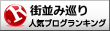しばらく迷ったのですが、オリンパスE-PL9を買いました。
EZダブルズーム・キットで、色はブラウンです。E-PL9は2018年3月の発売、既にその後継機のE-PL10が、2019年11月に出ていますが、カタログでは両方記載されているので、型落ち品ではないようです。
PL9とPL10の違いはわずかな機能面の変更と色合いぐらいしかありません。現状PL9の価格はPL10の半額ぐらいまで下がっていて、在庫があればPL10を買うまでもないでしょう。
もともとこの時期にカメラを買う予定は全くありませんでした。
フィルムスキャナの適当な奴があれば買おうかなとか、考えていたのですが、それを覆したのは6月のオリンパス社の発表です。同社の映像部門を分社化し、事業再生を専門とする会社に譲渡するという話、以前にここでも取り上げたことがあります。
オリンパスの発表では製品開発、メンテナンスは引き続き継続していくので、安心して製品を買ってほしいとのこと。ただ、同じ再生会社に事業譲渡したソニーのパソコン部門の例を見ると、ソニーのブランド名は使われなくなり、販路や製品分野を絞って事業を再開しています。
想像に過ぎませんが、現行のオリンパスカメラも、ある程度ラインナップを絞り込み、限られたターゲット向けに製品をフォーカスしていくことが考えられます。
そうなると、おそらくベーシックブランドとなっているペンシリーズなどは、このさき作られつづけるのかどうか、わからない気がします。
また、もし継続したとしてもオリンパスペン、とは呼ばなくなるでしょう。
もともと僕はペンシリーズに少し思い入れがあり、10年前にE-PL1を買ったのがMFTの最初です。その後Lumixも買っていますが、7年ほど前に買ったPen E-P3を今でも使っています。
MFTはペンタックス(Kマウント一眼レフ)を買ってからは使う頻度が減りましたが、サイズと画質がちょうど見合っていて、使い続けています。
僕はフルサイズ至上主義?というか、小さいフォーマットはフルサイズの廉価版、みたいな考え方はどうかしらと思っていて、小さいフォーマットには独自の存在意義があるものと思っています。APS-CとMFTだと大してサイズは変わらないのですが、それでも室内での撮影のとき、取り回しの面でMFTは便利です。
本当は1/1.7とかの小サイズもいい(ペンタックスQシリーズとか)のですが、そうなるとスマホとの競合が入ってきちゃうのか、あまり流行らないようです。
話が脱線しましたが、E-P3の代わりになるカメラ、探してはいたのですがなかなか手が回りませんでした。LumixGX7MK3あたりも考えてはいたのですが、まだE-P3も使えるし(というか、古いLumixG3も現役です。あの系列は本当に便利です)、そんなに急ぐことないかなと。
オリンパスのほうは4年前にかなり力の入ったPen Fというのが出ましたが、つくりもお値段もかなり立派過ぎて、なかなか手が出なかった。時折価格を調べたりはしてましたけど。Penシリーズは本家E-P系が5で途絶えてしまい、先のPen Fを除くとベーシック版のE-PLシリーズがモデルチェンジを繰り返していました。
のですが、PLシリーズはなんとなく興味がわかなくて、ニュースを追うこともしていませんでした。量販店で偶に手にすることもありましたが、特に欲しいとも思わなかった。売り方も、カタログなんかすごい女子カメラ的だしねえ。。
ああ長くなった。
ですが、とにかくもしかしたら、今がオリンパスペンを買う最後のチャンスかもしれないとなると、一応手に入れておこうかと。
そのあともかなり迷いましたけどね。。
E-P5の中古を探そうとか(玉数が少ない)、Pen Fの中古を探そうとか(意外と使いこんだものが多く、良品は高い)、PL9でもレンズはいらないんじゃないかとか(これはかなり検討した。最初は付属の電動ズームも、望遠も要らないと思った)。
ただこういうときの通例で、在庫が残っているのはたいていダブルズーム・キットなんですよね。それもかなり割安で、差額で計算するとレンズが1万円するかしないかという状態。それだったら。。
というわけで、3色の中で値段の安かったブラウンのダブル・キットと、液晶保護フィルム、128GBのカードをご注文。。
開封の儀ってやつですね。
ブラウンは新型になって少し色味が変わっていますが、これはこれでいい感じです。ストラップはなぜか白なんですね。
ストラップは他機種で多用しているAki-Asahiのを注文しようかなと思っっていたのですが、付属品もそんなにシャビーなものじゃないので、しばらくこれで使うことにします。
ジャケットは買わなかったけど、あったほうがいいかも。その際色はストラップに合わせて白にしようかしら。。
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZというレンズです。
電動ズームで、電源を入れるとちょうどコンデジのように自動的に鏡胴が出てきます。焦点距離が合わせにくい感じがするし、ボディだけ買って手持ちのPanasonicの12-32mmを付けておこうか、とも思ったのですが、あればあったで案外便利に使えるかもしれないと、思いなおしてキットにしました。。
ちょっと鏡胴が太い感じがしますね。全体的にはこれでボディとのバランスが取れて、おさまりが良い印象もあります。
ちなみにGR2とはそれほど大きさの差はありません。ちょっとPL9は重たいかな。。
レンズを繰り出すとこんな感じ。ごくふつうのコンデジっぽい感じで、違和感ないです。
右に回すと焦点距離が伸びるのですが、どうも感覚的に間違えます。
ふだんそういうことは意識しないんですけどね。。
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
キットに入っているもう一本のレンズです。これも、要らないと思っていました。というのは昔のLumixG3のダブルキットに入っていた、45-200mmという望遠ズームを持っているからです。
ただ、45-200mmは380gと、40-150mmの倍の重さがあり、ペンシリーズには似合わないかもしれない。実際E-P3につけたことはないです。。なので、着いているならそれもいいかなと。
実はこれの前身のレンズ(末尾にRがついてないほう)は暫く持っていたことがあります。E-PL1の時代に使っていました。現行のレンズとは光学系は全く同じみたいです。
そうとは気がつかなくて・・、店頭でPL9の展示品を触った時、ズームリング回しても鏡胴が伸びませんでした。
あれ?、インナーズームに変わったのか、これなら使いやすそうだな、と思ったのですが、たぶん展示品は壊れてたのかもしれません。。
実際は鏡胴がながーく伸びてしまいます。だから安っぽいということはないのですが、見ればわかるけどなんかださい。
40-150mmの装着姿。こういうのはコンパクトにまとまっていると勝ちみたいな感じがあって、その点Lumix 35-100mmはいいですよね。
ただこちらは軽いのが取り柄で、重くて手に余るということはなさそう。
それと前持ってたやつの記憶で言うと、描写性能はかなり悪くないというか、なかなか良かった記憶があります。
PLシリーズは途中からアクセサリーポートを廃止してしまい、EVFがつけられなくなりました。外付けEVF自体、もうカタログに載っていないのですね。
いちおう、17mm F2.8と外付け光学ファインダーは取り付け可能ですし、ちゃんとファインダーとして役に立ちます。17mm F2.8自体がもうディスコンですが、これはこれでカッコいい感じです。
17mm F2.8というの一時期はほとんど風評被害と言っていいぐらい、ネットで叩かれたレンズですが、実際そこまで悪くない、というか結構好きなレンズです。これとLumixの20mm F1.7は、MFT初期のカジュアルなムードを思い出させてくれる、お気に入りのレンズたちです。
長くなってしまったので、今日出かけて試し撮りした話はまた次回に。