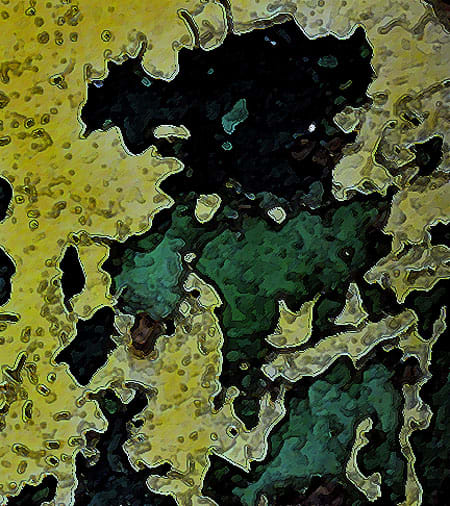78: 『黄表紙』から「心学早染草」
『黄表紙』から「心学早染草」
「心学早染草」山東京伝
日本古典文学大系 59
岩波書店
昭和44年 8刷 1000円(P,533)
昨日テレビで歌舞伎舞踊『俄獅子』を見た後、浅草三社祭斎行700年祭奉納舞踊『三社祭』の舞踊とようすがかいつまんで流される。
浅草三社祭斎行700年祭奉納舞踊『三社祭』では、七之助さんたちはりりしく、また、おもしろおかしく素顔で舞われている。
『三社祭』といえばわたくしの場合は「善」と「悪」の面を思い浮かべる。
以前から「善」と「悪」と記されたタンバリン型の面をつけての踊りには関心があった。
『三社祭』は劇場でもテレビでも見たことがあるが気にかかるので 『名作歌舞伎全集 第十九巻』「三社祭」「解説」 東京創元社を読む。
文字だと短い。
だが、読み出すと文字はおどけて踊り出し、おかしみときれを味わった。
『名作歌舞伎全集 第十九巻』「三社祭」の解説に、善玉悪玉のことが書かれていた。
善玉悪玉の趣向は、山東京伝の黄表紙『心学早染草』からとり込んだもだという。(『名作歌舞伎全集 第十九巻』「三社祭」200ページ)
明け方書棚から『黄表紙』を取り出し「心学早染草」を読む。
この時代に書かれた物としては珍しくも引用はほぼないが根本的なところを大きくひいている。
単純で明瞭で、起承転結がはっきりしていて、読み初めるとすぐに役者の声が聞こえてくる。
今回の場合は、真っ先に聴こえたのは、故意に声を裏返された吉右衛門さん。この一声で芝居(実は『黄表紙』「心学早染草」)が大いに盛り上がりをみせ、観客(実は読者)に期待を呼び起こさせる。
中程 別役で染五郎さん。理(理太郎)のある一場面は、藤十郎さんか翫雀 で味わいたい。故 芝翫さんや七之助さんも目に浮かび、台詞を楽しむ。『黄表紙』「心学早染草」の方に出てくる大勢の悪玉の中には、市蔵さん、彌十郎さんの姿や言い回しも思い浮かぶ。あの萬次郎さんの特徴ある声で、犬の鳴き声まで聞こえてくるから不思議だなと ほくそ笑む。
読んでいくうちに台詞不の内容によっては一役で何人もの役者さんの入れ替えあり。こんな風に勝手気ままに遊べることを考えると、わたしは歌舞伎のことは知らないとはいえ 芝居が好きで良かったなとつくづく思う…。
『黄表紙』「心学早染草」の筋書きはここでは省略。
歌舞伎の「三社祭」が『黄表紙』「心学早染草」をひいて創作されたことを知り、伝統芸能とは趣深いなとあらためて感じた。