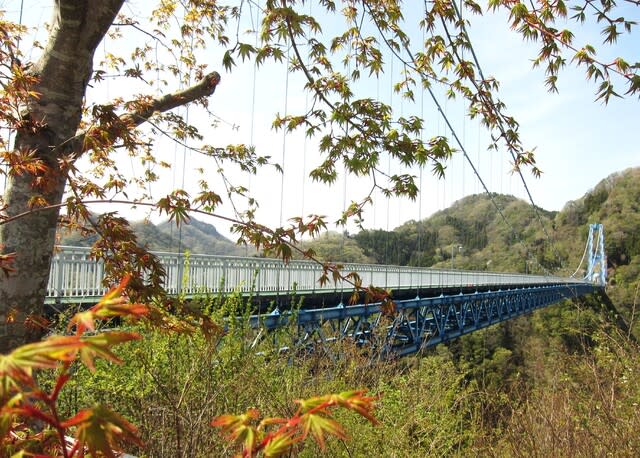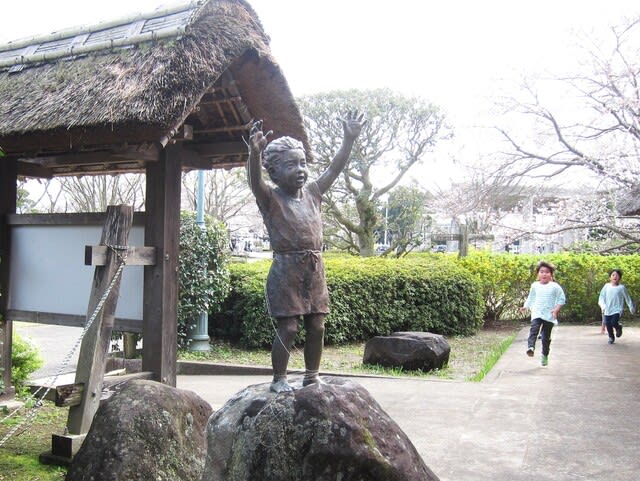最大10日間にもなる今年のゴールデンウイークが始まりました。現役のころより人混み苦手でしたが、さすがに仙人ともなればステイホームが日常になっています。そういうことで渋滞のニュースに同情しながら、ショボつく眼で狭庭の草花を撮ってみました。

ナニワイバラ(難波茨)は中国原産の原種に近いバラです。丈夫なバラで野性化している所もあるようですが、鋭い棘が多く手入れが大変、花期も短く蕊がすぐ黒くなってしまいます。

棘が無く育てやすいので人気のモッコウバラ(木香薔薇)は、中国原産で江戸時代から栽培されました。我が家の黄色い花の方はほとんど匂いません。近所でも挿し木してあげた子孫たちが花を咲かせています。

釣鐘形の花が可愛いブルーベリーは、同じ木の花粉では実が生りにくい「自家不和合性」なので、違う種の木を隣に植えています。

似たような釣鐘形の花は、秋の紅葉が美しいドウダンツツジ(灯台躑躅)です。名前の由来は、枝の分かれ方が宮廷などの夜間行事に用いた「結び灯台」(上図右)の脚に似ているからといわれ、それが訛ってドウダンになりました。

こちらは下向きの小さなツバキの花、エリナカスケードです。中国原産の野性種の変異株で品種登録されている植物です。

ライラック(紫丁香花)の花、リラの花咲く~ころ♫と歌われるリラはフランス語です。香水の原料としても有名です。

50年以上前、山を造成した団地にある我が棲家は粘土質で水捌けが悪いのですが、このエビネ類には好かれているようで、ジエビネ(地海老根)、タカネエビネ(高嶺海老根)が毎年顔を出します。

イカリソウ(碇草)も同じ条件の下で、他の植物を追いやる勢いで増えています。

子供のころからヤグルマソウ(矢車草)という名で親しんできましたが、最近ではヤグルマキク(矢車菊)という名前にしているのを見かけます。というのはユキノシタ科の矢車草という植物があるので混同を避けるためにキク科の植物は「矢車菊」の名で統一するようです。
鯉のぼりの柱の先で回る矢車に、花が似ているのがヤグルマキク、葉が似ているのがヤグルマソウということ、なにかややこしいですね。(※ヤグルマソウの写真はwikipediaからお借りしました)

小さな手鞠のような花クリーピングタイムはシソ科のハーブです。creeping (這う) という名の通り、地面を這って低く広がっていくので雑草防除にも役立つと載っていました。

あまり気にしていませんでしたが、雄しべの数が5本なのでこれはサツキ(皐月)のようです。

ワスレナグサ(勿忘草)はヨーロッパ原産ですがいつの頃か日本に渡来し、詩歌に詠まれるようになったのは明治以降といわれます。英名ではそのままforget-me-not、これには中世ドイツの悲恋の話が残っています。ドナウ川の岸辺を散歩していた騎士ルドルフと恋人ベルタが小さな花を見つけ、ベルタのためにその花を摘もうとしたルドルフうっかりと足を滑らせ、急流に落ちてしまいます。重い鎧を身につけていたルドルフは這い上がれず花をベルタに投げて、「私を忘れないで(forget‐me‐not)」と叫んで流れに飲みこまれてしまいました。

30年近く前に小さな鉢植えで買ったシャクナゲ(石楠花)は、3m近くにもなり持て余し気味になってきました。

小さなアヤメ(菖蒲)が咲きだしました。この仲間の区別は分かりづらいのですが、花弁の真ん中にあやめ(綾目)という網目模様があります。

ついに我が家にも攻めてきました、ナガミヒナケシ(長実雛芥子)…地中海沿岸原産の外来植物で可憐な姿に見えますが、1個体から15万粒の種子がこぼれるという繁殖力の強さから、いま各地で問題になっています。

近所の空き地にも広がってきました。アルカロイド性の有害物質が含まれているので、手がかぶれることもあるそうです。国の駆除対象となる「特定外来生物」にはまだ指定されていないようですが…。