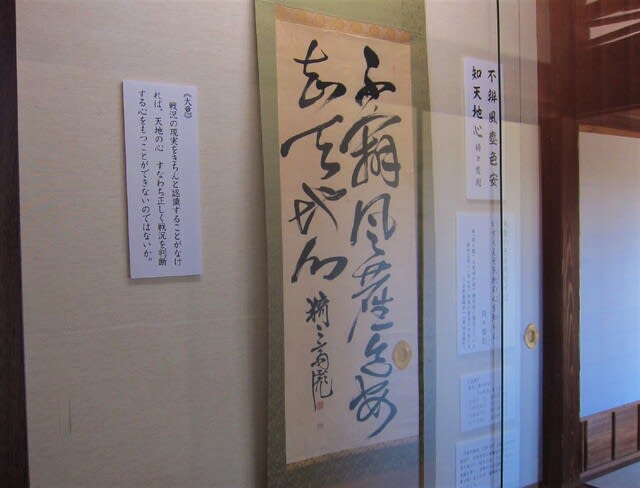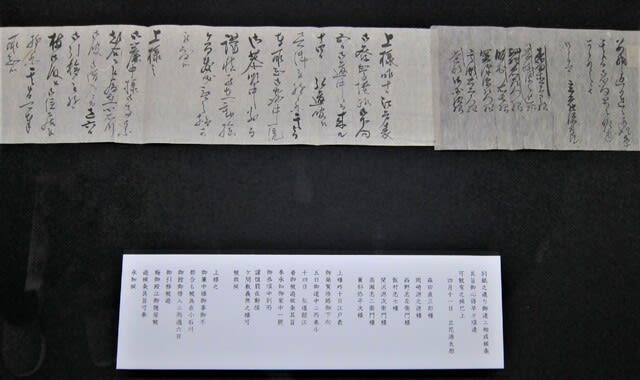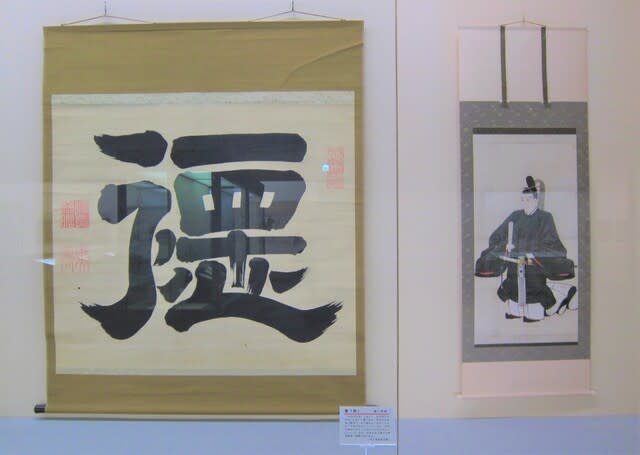茨城県独自の非常事態宣言が2月23日で解除になり、中止されていた梅まつりも3月1日から21日まで開催されることになりました。

コロナに関係なく例年通りに花を開き始めている梅の花、偕楽園では通常100種といわれていますが、実際の品種は成木前の状態の木などを含めると200種近くなっているという話も聞きます。

偕楽園公園センターの枝垂れ梅の大木「白滝枝垂」が咲き始め、大屋根をのぼる白い滝のような姿を見せていました。

小さめの紅梅「日光梅」、横に出る小枝は錦性になると図鑑には出ています。

清香が強いとされている「麝香梅」、マスク外して鼻を近づけても匂いを感じません。

花の真ん中に紅い筋模様が入る「底紅」という咲き方の「関守」、李系紅材性の結実種です。遠方に好文亭を入れてみましたが…。

同じ白梅でも青白い花で人気の「月影」はまさに名前通りのイメージで、命名者の感性の深さに脱帽です。

芳香が強いという「文殊」は難波性の結実品種、淡紅色の花は知恵をつかさどる文殊菩薩のイメージがあるでしょうか。

「内裏」とは天皇の宮殿のことでひな祭りの歌にも、お内裏様とお雛様~♬と出てきます。外側の花弁の裏が紅い「裏紅」という咲き方で、透けて見える淡い紅色がまるで頬紅を付けたように見えます。

「内裏」にとまる翅がぼろぼろの蝶、調べてみると越冬して早春に活動するヒオドシチョウ(緋縅蝶)のようですが、まるで歴戦の勇者、こんな翅でもしっかり飛び立っていきました。

見て驚くという命名由来の「見驚(けんきょう)」は結実しない花梅の代表種、咲き進むと花の色がだんだん白くなる「移り白」という性質です。

「筑紫紅」は大宰府天満宮にあるので九州で産出した種という説もあります。写っている橋の名前はなんと!「花追い橋」です。

後水尾天皇(1596~1680)が「花も香りもよく果実も佳なりとの意にて命じ給いしもの」と伝わる「花香実(はなかみ)」は、その通りの銘花で大きな実も生ります。

まだ小さな木ですが「曙枝垂」がやっと花を咲かせていました。日本人は枝垂れを好んだので江戸時代から約40種の枝垂れ梅がつくられたといいます。

同じく窈窕梅林にデビューしたての「玉垣枝垂」です。野梅系の「玉垣」の枝垂れ品種で白色もあるそうです。なお、玉垣とは皇居、神社の周辺などの垣のことをいいます。

偕楽園の梅林は、洪積層台地上にある本園(約13ha)の他に台地下の沖積層地に「田鶴鳴梅林」「猩猩梅林」「窈窕梅林」など3つの梅林があり、今回の梅はその周辺で撮りました。
窈窕梅林の南側には、梅品種見本園が3面あり、約220種の梅が植えられているそうです。