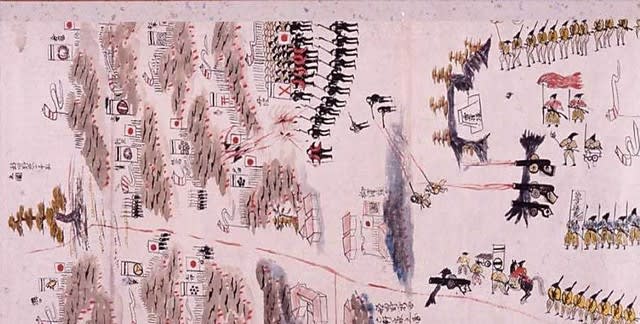偕楽園の表門を入ってすぐの門、「一の木戸」は、竹林と杉林の幽玄な一画への入り口です。公園全体を陰と陽に分けた、徳川斉昭公の陰の世界がここから始まります。この門は、補強、補修がなされていますが、開園当初のもので、当時は門扉がついている構造だったようです。

この門の屋根は、いわゆる板葺きの一種、杮(こけら)葺きです。厳密に言うと杮葺きの板厚は2~3ミリ、これは約6ミリあるので、木賊(とくさ)葺き(4~7ミリ)とか、栩(とち)葺き(10~30ミリ)になるのでしょうが、昨年暮に葺替えしていた職人さんは、杮葺きと言っていましたので、細かい分類はしないのかもしれません。

この杮葺きは好文亭の屋根にも使われています。亭内に置かれた屋根見本で測ると、厚みは2ミリ、この薄さがあるからこそ、室生寺や金閣寺などの文化財の屋根の微妙な曲線も表現でき、使用されています。一方、一の木戸は直線的な切妻屋根なので、板の厚い葺き方が合っているのでしょう。

杮葺きは、約40年位の耐久性とされていましたが、大気汚染の現在では10から20年くらいの間隔で葺き替えるようです。寺社建築などに用いられ、国の重要文化財に指定されている建物4,676棟のうち、353棟が杮葺きです。しかし、杮葺の文化財の少ない地方なので、去年暮れの一ノ木戸の葺き替えには、職人さんを遠方から呼び寄せたと聞きました。

写真は葺き替え後10年目になる好文亭の屋根ですが、すでに古色蒼然となっています。
なお防火上の問題から板葺きの屋根は、離れて建てる東屋など以外の一般住宅には使用できないそうです。

さて、その好文亭奥御殿の庭も最後の紅葉を迎えていました。斉昭公の正室、貞芳院が明治2年から6年まで、水戸城下柵町の中御殿を移築して住んでいたのもこの空間…、晩秋の侘しさがさらに強く感じられました。
障子しめて四方の紅葉を感じをり 星野立子
奥御殿ふすま紅葉は散りもせず 顎髭仙人
奥御殿ふすま紅葉は散りもせず 顎髭仙人