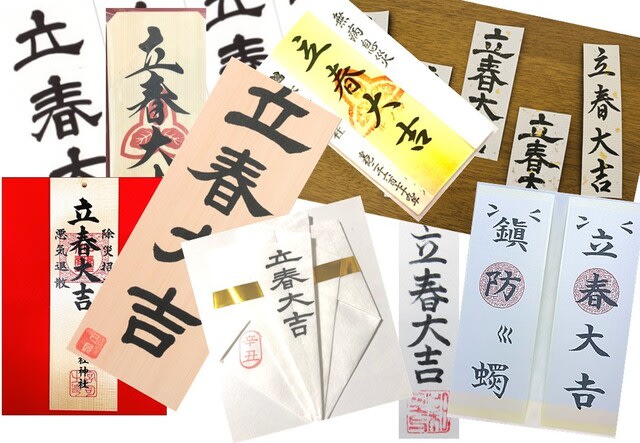わが終の棲家から5キロくらい先にある涸沼自然公園で早春の花を探してみました。以前はサイクリングで一走りでしたが、自転車も埃をかぶってしまい車での訪問です。

涸沼は全国で29番目の大きさの面積935ha、満潮時に太平洋の海水が涸沼川と那珂川を経て流れ込む汽水湖です。その北側の湖畔に開設された涸沼自然公園は、面積34.5haの広大な山野の自然をいっぱい取り込んだ野趣あふれる公園です。

管理棟のパステルカラーの屋根が、周りの自然に溶け込んでいます。

湿地に敷かれた木道の先は広大なキャンプ場、250張設営できるテントキャンプサイトのほか、1区画83㎡の広さのオートキャンプサイトが56区画(AC電源付き)あります。右手の高台の建物は涸沼荘という老人保養施設でしばらく前から閉鎖されています。

ここの魅力はいたるところから涸沼を見下ろせるところです。左手の対岸は大洗町になります。

木立の先の対岸は鉾田市、県営の宿泊施設「いこいの村涸沼」が見えます。

休みの日は子供たちの歓声が聞こえる遊戯施設「わいわい広場」も平日はひっそりしています。

広場のそばで見つけたカンボケ(寒木瓜)です。

その先にある小さな梅林では早咲きの梅が咲き始めていました。

早咲きの代表はこの八重寒紅、水戸の偕楽園でも一番先に花を開きます。

同じく冬至梅も早咲きの白梅です。一般的には早咲きの梅は残念ながらほとんど結実しないようです。

緑色の蕾がいっぱい、名花「月影」の開花はもう少し先のようです。

梅林のそばにある十月桜は10月頃に花が咲いて冬の間もすこしずつ咲き続け、桜の時期に他の桜が咲くころになると一緒にまた咲きだします。

河津桜も冬の眠りからやっと目を覚ましつつあるようです。

枯れた景色の中に赤いイトトンボ橋がいちだんと存在感を出していました。昭和46年(1971)に涸沼で発見された新種ヒヌマイトトンボに因んで名づけられました。

サザンカ(山茶花)の多い公園です。さすがに寒さに縮んだ花ばかりでした。

冬でも緑色を保っているのは山菜のノビル(野蒜)です。禅寺の門によく「不許葷酒入山門」(臭い野菜と酒は修行の妨げだから山門から入ってはいけない)と書かれている五葷のうちのひとつともいわれます。
しばらく暖冬が続きましたが、今年の冬は寒かったですね。偕楽園の梅の花も1か月近く開花が遅れているとか、それでもやっと咲きだしましたので、間もなくいつもの春に追いつくことでしょう。