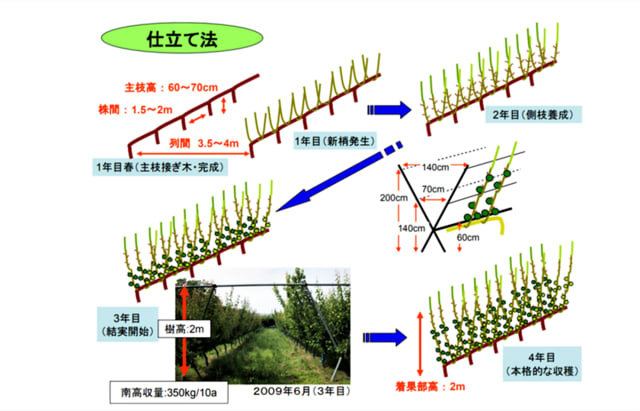伊勢神宮は125社の神社から構成され、その正宮は、皇大神宮(こうたいじんぐう)」と豊受大神宮(とようけだいじんぐう)の二つで、それぞれ内宮(ないくう)、外宮(げくう)と呼ばれています。
※写真は伊勢神宮のホームページより借用いたしました。
この伊勢神宮の内宮と外宮の御分霊を奉遷した二つの神社が、茨城県東海村の直線で2キロの距離の地に鎮座しています。
因みに国内で初めて原子力の火が灯った東海村は、人口約37,000人、村としては全国2位、人口密度も4位で町制施行要件は満たしていますが、まだ「村」です。
内宮の皇大神宮を奉遷し、茨城のお伊勢さんとよばれる村松大神宮は、和銅年中(西暦700年頃)創立と伝わります。神社明細帳によると 「和銅元年(708)4月7日平磯前浦の巨巌怪光を発射しその光眞崎の浦に留る。住民畏れて占う。『伊勢の神なり』と。垂示に従って奉斎。祀職伊勢より来りて奉仕す。」 と記されています。
水戸藩2代藩主徳川光圀公が、元禄7年(1694)新たに神殿を造営、あらためて伊勢皇大神宮より御分霊を奉遷、神宝、神器を奉納し、参拝されました。9代藩主斉昭公も、安政4年(1857)に神殿を造営され、また桜田門外の変の志士も参拝し成就を祈願したと伝わります。
伊勢神宮の内宮と同じ「天照皇大神(あまてらすおおみかみ)」他2柱を御祭神としています。
斉昭公造営の本殿は明治32年(1899)火災により焼失し、2年後に建てられた現在の本殿の屋根には、伊勢神宮と同じに鰹木が10本、内削ぎの千木が載っています。
火伏せの愛宕神社や病気平癒の晴嵐神社などの境内社が並んでいます。
光圀公腰掛の石というものもありました。
葵の紋入りの神輿は徳川斉昭公より下賜されたもので、金箔を張り詰め唐破風の豪華な造りですが、担がれることはない飾り神輿だそうです。
こちらも茨城のお伊勢さん、同じく光圀公が神鏡を奉納し伊勢豊受皇大神宮を奉遷したと伝わる豊受皇大神宮にも同じ伝説が残っています。
東海村観光協会のホームページには、「和銅2年(709)年4月7日、平磯(現ひたちなか市)前浦にある巨巌が怪光を発射し、その光が白方の郷を射しました。村人に乗り移った神様が、「伊勢の神をお迎えせよ。」と言ったので、この土地に祀った」と出ています。
(村松大神宮と1年違いの同じ日なので、同じ話ではないでしょうか)
本殿の千木は、男神といわれる外削ぎで、伊勢神宮と同じです。
祭神は伊勢神宮の外宮と同じ「豊受大御神(とようけのおおみかみ)」で、天照大御神の食事をつかさどり衣食住、産業の守り神とされますが、女神と男神の両方の説があるそうです。
多数の境内社があり、二十六社、三十四柱の神様が祀られています。
この辺りはかつて、埴田(はなだ、半田、花田)といったことから、埴田宮・花田五所大神宮とも云い、村松大神宮が伊勢の内宮に相当するのに対し、こちらは外宮に当たると言われてきました。
豊受皇大神宮下の池の畔に一の鳥居があり、左手の台地の上に豊受皇大神宮があります。
伊勢神宮の分霊を標榜している神社は、全国に18000社ともいわれます。
この地に、内宮と外宮の分社が同じ伝承により建立された関連性は不明で、神職の方に聞いても分からないというお返事でした。最初はどちらも天照大神を祭神とする内宮を奉遷した神社だったのが、光圀公の時代に一方を外宮の分霊社に分けたのかもしれないという説もあるようですが…。