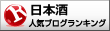伊能忠敬北海道測量開始記念公園
伊能忠敬北海道測量開始記念公園
カヌー
 で道内上陸
で道内上陸
 江戸時代の測量家・伊能忠敬(1745~1818年)は、1800年(寛政12年)第1次測量で蝦夷地を訪れた際、北海道福島町吉岡に上陸、道内で初めて測量を行った
江戸時代の測量家・伊能忠敬(1745~1818年)は、1800年(寛政12年)第1次測量で蝦夷地を訪れた際、北海道福島町吉岡に上陸、道内で初めて測量を行った この銅像は福島町吉岡の国道沿いにある。伊能忠敬北海道測量開始記念公園として整備された
この銅像は福島町吉岡の国道沿いにある。伊能忠敬北海道測量開始記念公園として整備された
 福島町から道内測量が開始されたことはあまり知られていない
福島町から道内測量が開始されたことはあまり知られていない 。腰の曲がった爺さんの像
。腰の曲がった爺さんの像 という方もいるが、真剣に測量調査している銅像である
という方もいるが、真剣に測量調査している銅像である
 伊能忠敬は、正確な地図を作ったことは有名だが、名前は「ただたか」より「ちゅうけいさん」とも呼ばれ親しまれていた。
伊能忠敬は、正確な地図を作ったことは有名だが、名前は「ただたか」より「ちゅうけいさん」とも呼ばれ親しまれていた。 忠敬は、千葉県九十九里町で生まれたが、結婚して千葉県香取市の造り酒屋に婿養子に。地域の飢饉を乗り越え、農民を救いながら家業を発展。指導者として成功し幕府の役人から刀を持つことを許された。そして商売を長男にまかせ50歳になった隠居後に、自分が本当にやりたいことをやろうと江戸に出て、忠敬の師として知られる
忠敬は、千葉県九十九里町で生まれたが、結婚して千葉県香取市の造り酒屋に婿養子に。地域の飢饉を乗り越え、農民を救いながら家業を発展。指導者として成功し幕府の役人から刀を持つことを許された。そして商売を長男にまかせ50歳になった隠居後に、自分が本当にやりたいことをやろうと江戸に出て、忠敬の師として知られる 高橋至時(よしとき)という20歳も若い先生に天文学(暦学・星学)と測量学を学ぶ。猛勉強の末、金星の南中日時や日食月食の日時を割り出すなど、学問でも輝きを放つ。至時と忠敬は、地球の正しい大きさを知るために、緯度1度の長さを測る測量に出かけた。56歳で蝦夷地に向かい、以後は列島各地を測量。この結果できあがったのが、あの日本全図である。
高橋至時(よしとき)という20歳も若い先生に天文学(暦学・星学)と測量学を学ぶ。猛勉強の末、金星の南中日時や日食月食の日時を割り出すなど、学問でも輝きを放つ。至時と忠敬は、地球の正しい大きさを知るために、緯度1度の長さを測る測量に出かけた。56歳で蝦夷地に向かい、以後は列島各地を測量。この結果できあがったのが、あの日本全図である。 忠敬は、20年間近く日本各地を歩き続け
忠敬は、20年間近く日本各地を歩き続け その距離は、地球を一回りする以上にもなった
その距離は、地球を一回りする以上にもなった 1818年に亡くなった、測量の結果は弟子たちの協力で、1821年に
1818年に亡くなった、測量の結果は弟子たちの協力で、1821年に
 大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)という名の日本全図として完成させた。
大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)という名の日本全図として完成させた。 伊能忠敬を主人公とした小説家・劇作家の井上ひさしの長編歴史小説も面白かったな。
伊能忠敬を主人公とした小説家・劇作家の井上ひさしの長編歴史小説も面白かったな。 忠敬の銅像は富岡八幡宮(東京)や九十九里町(千葉)にもある・・・
忠敬の銅像は富岡八幡宮(東京)や九十九里町(千葉)にもある・・・