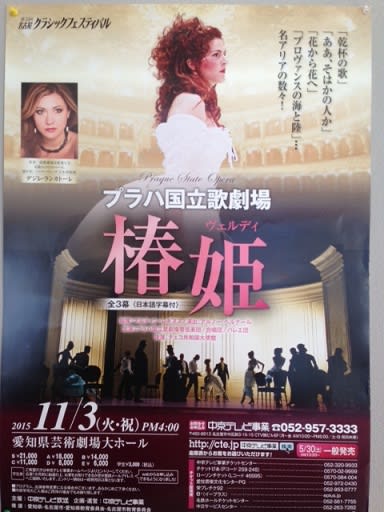先日小澤征爾塾の歌劇「カルメン」を見てきました。
カルメンは美貌のジプシー男の心を悪魔のようにとりこにする美女
そしてまじめ男ドンホセがそのカルメンにのぼせ上がった!
伍長としての兵隊の地位も、聖女のような献身的恋人も
故郷で出世と幸せを願う母のおもいも捨ててです。
カルメンも半年後とに男を変えるけれど今度は恋!
相思相愛だけれど
カルメンは危険な女
密貿易やらなにやらあやしげの仲間もいる
その仲間にもなこめないドンホセのやきもちはひどく
やきもちを焼くたびに、だんだんカルメンの心もさめていく
今ならそドンホセの女々しさはまるっきりストーカー
浮気な女にささっと見切りをつけなさいよ=って言いたくなるみっちゃんです
カルメンは自由な女誰にも縛られない
縛ることが出来ないと歌う
時の花形闘牛士と恋仲のカルメン
ひどい浮気な多情な女だな
そんな強気に出たら命が危ないよ!
案の定、最後の復縁をきっぱり断るカルメン
ナイフで刺し殺すという有名なストーリーです

詳しくはここから見てね
カルメンあらすじ
http://www.geocities.jp/wakaru_opera/carmen.html
当時(初演1875日本の明治維新の頃)
今より道徳観がキリスト教的でしたから
このストーリーはひどく不評だったそうで失意のうちに作曲者ビゼは急死してしまったそう
しかし作曲者のビゼーはフランス人でスペインへ行ったこともない。
でもスペインの民謡や音楽がすばらしい効果を挙げています
「オペラ蝶々夫人」のプッチーニーが日本にきたことも何もないのにすばらしい日本情緒をも書き立てる音楽を書き上げたのと同じですね
私もストーリーは突っ込みどころいっぱいですが、この歌劇だけはほとんどすべての曲を暗記しています
ですからことし2月に私の大好きな指揮者の山田和樹さんが藤原歌劇団の指揮者で「カルメン」を上演した。
これはかなりの酷評でしたので、今回も期待はしてなかったです。
2時間半の上演ですが休憩時間が1位時間半もあり、終演は夜の10時をかなり回っていた!
帰りの通路も閉鎖されているところもあるので誘導が会った
私は30分ほどで帰ることが出来るのだが11時過ぎていた。
遠くから来られた人はホテル泊まりだそうだ
そのわけは舞台装置であるいつも思うのだが
この塾の舞台装置はメトロポリタン劇場の舞台監督のロビン・ドン
メトロポリタンを髣髴させる大掛かりで迫力アル舞台装置である。
だから舞台展開に時間がかかる
でもそれはそれでこれだけの舞台装置を見られるのは納得であり

満足感があり否が応でも気持ちが高まります
なお衣装のロバート・バージオラも圧倒的なすばらしさを感じる。
ほかのスタッフもやはり世界の小澤の人脈すばらしいと思うスタッフである
久しぶりにフランス語のオペラで嬉しかったです。
でも日本人の出演者もっと語学勉強してほしい
歌い手としてはすばらしいのだが・・
でも全体として熱演よかったです。
最後の愛知芸術劇場でスタンディングオベーション初めて見ました。

そんな思いの春の宵でした。
やっぱり生がいいのはビールだけではないですよ
最初カルメンがホセにあげたバラ怪しい色です

読んでくださってありがとう