
本気と無理の間

今日のタイトル、どういう意味かって? それはね、本当の自分に対する態度であると同時に、子どもに対する態度のこと。 私は小学生の母親と教員に会うことが多...
埼玉県の深谷市で、老夫婦とその娘が、利根川の水に入ったといいます。心中だと言われます。高齢の夫婦はなくなり、50歳近い娘さんは、低体温症で見つかったらしい。娘は、殺人と自殺ほう助で逮捕だとか。今朝の朝日新聞(11.24, 2015, 12版▲p.28)にも載っています。他紙にもあります(http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG23H5I_T21C15A1CC1000/)。
ここ数日、急に冷え込んできましたよね。利根川の水もどれほど冷たかっただろうか、と想像します。痛かっただろう、しびれただろうと思います。毎日1,000人くらいの人が自殺するニッポン(その内、死ぬ成功率[あるいは、死ぬ失敗率]は1割くらい)ですから、その内の1ケースだ、という見方もできるでしょう。
しかし、私は別の見方をしたい感じでいっぱいです。ここには、幾重にも「平和な」ニッポンと言われるけれども、「戦争状態」である、ニッポンの真実の姿が現われていると感じるからです。
亡くなったおじいちゃん、74才だったそうですね。でも、つい先日まで、新聞配達のバイトをしていたらしい。年金だけでは生活が出来なかったからに違いありません。なぜ、私どもは、掛け金を1円も払わずとも、年金がもらえるデンマークのような年金制度を作らないのでしょうか? 年金を貰っても、生活できない程度のお金しかもらえない制度設計をそのままにしていること自体、日本に暮らす市民の「人間として正しいこと(基本的人権)」が蔑ろにされている、と言えませんか?
また、亡くなったお婆ちゃんは、介護が必要な状態だったといいます。「平和」と言われるニッポンですが、介護が必要になっても、居住タイプの介護施設は、申し込んでも何年間も待たないと入れないし、利用料も取られます。なぜ、デンマークのように、施設にすぐに入れて、しかも、無料な高齢者福祉制度を作らないのでしょうか? 「介護が必要になったら、家族が仕事を辞めてでも介護をしてねっ、それでもだめなら、死んでも構いません、サッサと自殺してねっ」と言わんばかりの介護制度を、しかも、お金を利用者が払って使っているような、貧しい制度は、果たして、「人間として正しい生活(基本的人権を守った生活)」と言えるでしょうか?
また、50才位の娘さんが、仕事を見つけることも困難だったでしょう。たとえ見つけられたとしても、その仕事は、果たして、家族5人が、贅沢はできなくても「人間として正しい」暮らしが、できたでしょうか? ここには、女性の雇用が厳しく、たとえ働けても、「ワーキング・プア」と言われる程度の賃金しか得られない労働政策があります。正規雇用と非正規雇用の分断政策、女性の蔑視、低賃金・長時間労働、働くものの意見表明権の蔑視、職場での話し合いの蔑視、働くものの心と身体の健康を守る労働衛生の軽視など、労働政策の悪質な劣悪化があります。
「女性が輝く社会」の看板を掲げる、アベ・詐欺師ちゃんと悪魔の仲間たち。この心中に2人の女性が含まれていたことを考える時、この「女性が輝く社会」とは、どんな意味があるのでしょうか? もちろん、アベ・詐欺師ちゃんと悪魔の仲間たちは、詐欺師集団、ウソつき集団ですから、この「女性が輝く社会」の看板もウソであることは間違いありません。でも、それだけじゃぁないでしょう。むいろ、ウソ以上に悪質です。つまり、ニッポンの現実は、そりゃぁもう、非人間的な社会にすでになって久しい。改善・改革が必要です。そこでこの「女性が輝く社会」の看板が威力を発揮します。現実には、女性が生きやすくなるような政治は皆無と言っても、間違いないのですが、この「女性が輝く社会」の看板があれば、たとえなにも役立つことはしてなくても、「やる気はある」と言い張ることはできるでしょ。つまりこの「女性が輝く社会」の看板は、真面なことをやらない「口実」「言い訳」にはなるんですね。
私どもは、看板に騙されないで、市民の「人間として正しいこと」を頼りに、その実現を政治日程に乗せる政治を選択していかなくてはならないでしょう。

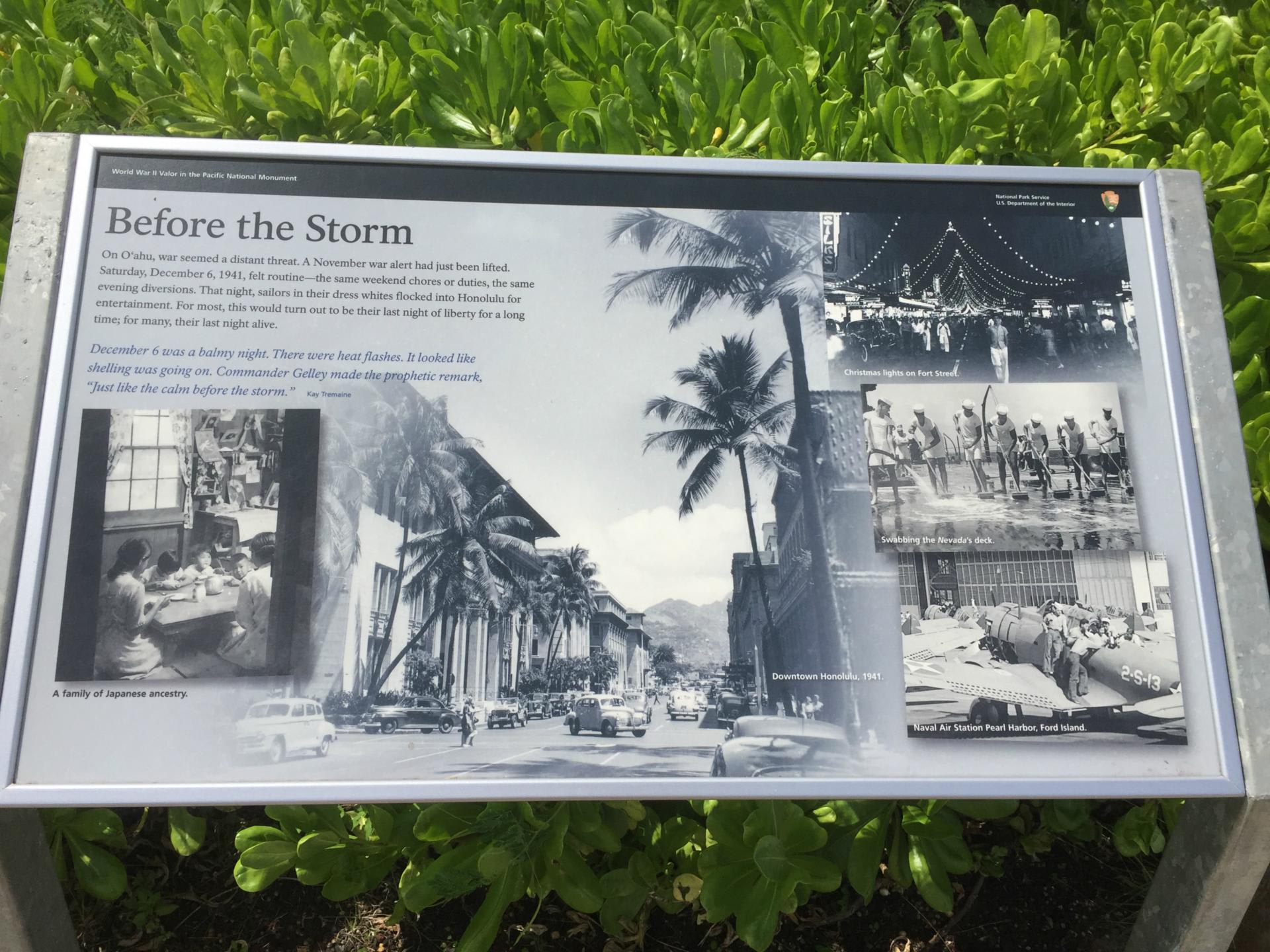











 今日のタイトル、どういう意味かって? それはね、本当の自分に対する態度であると同時に、子どもに対する態度のこと。 私は小学生の母親と教員に会うことが多...
今日のタイトル、どういう意味かって? それはね、本当の自分に対する態度であると同時に、子どもに対する態度のこと。 私は小学生の母親と教員に会うことが多...

 踊りと巻き上げに注意。 p80下から2行目から。 世の中は、バカデッカイ食べ物になっち...
踊りと巻き上げに注意。 p80下から2行目から。 世の中は、バカデッカイ食べ物になっち...





 早熟の道徳性、早熟の良心は、禁物です。「正しい」ことよりも、「ホッとできる温もり」が何よりも大事だからですね。 p224第3パラグラフ。 ...
早熟の道徳性、早熟の良心は、禁物です。「正しい」ことよりも、「ホッとできる温もり」が何よりも大事だからですね。 p224第3パラグラフ。 ...





