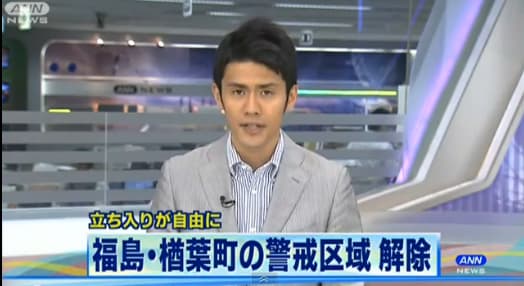
国立市から 改訂版

国立市。東京の小さな町。私の出身地。 国立市在住で最も有名な人はだれか? 山口百恵さんを挙げる人が多いでしょうね。 でも、私は生まれも育ちも国立市谷保...
昨日の晩に、福島県楢葉町の住民の帰還が、なかなか進まない現状を伝える、NHKスペシャル「東日本大震災・原発事故5年 ゼロからの町再建 楢葉町の苦悩」と言う番組を見ました。9月5日2015年に、「避難指示」が解除されました。しかし、避難前の楢葉町の住民7,400人の内、実際に町に戻ったのは、高齢者を中心に400人ほど、人口の6%に留まっていると、この番組は伝えています。
ですから、上下水道、電気・ガスなどが使えるようになり、コンビニも楢葉町にはあるそうですが、大型スーパーや病院などは、まだないそうです。経営できるだけのお客さんがいないからだそうです。でも、なんで住民が戻らないのか? について、この番組では、本当のことは報道しませんでしたね。
日本には、一般の日本市民が被ばくしても仕方がない、とする被爆のレベル(線量被ばく)は、一年間に、1ミリシーベルト(mSv)以下にしなくてはなりません。これは、放射線障害防止法「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号)」という法律で決められていることです。この法律には、放射線技師など、放射線を活用した仕事をする専門家には、年間20mSvという別の基準があります。(https://www.jrias.or.jp/disaster/pdf/20120213-134623.pdf、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html)
しかし、放射線には「安全」の閾値はありません。放射線の専門家の山本義隆さんや、小出裕章さんの言葉です(http://www.dailymotion.com/video/x34x391)。
ところが、小出裕章さんによれば、今の日本はまだ原発事故後の「緊急事態宣言」が出ている状況だそうです(http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4220.html)。一般市民の被ばく限度が、年間1mSvから、専門家にしか許されない年間20mSViに、上げられたままになってしまっています。楢葉町の住民の被ばく限度は、年間1mSvではなくて、専門家にしか認められないはずの20mSvが適応されているのですね。これって、果たして、日本市民の命を守っていることになるのでしょうか?
いまにフクシマ原発から、東電社長の広瀬さんは、「最大で1日あたり最大200億ベクレルのセシウムが放出されているとみている」と言っているくらいです。
小出裕章さんは、日本外国特派員協会での講演で、
「この4号機の半分壊れた原子炉建屋の中に、使用済み燃料プールが宙づりになっているのですが、そのプールの底には広島原爆に換算すると、約1万4000万発分のセシウム137が含まれていました。それがプールの底で発熱を続けているわけで、プールの水が干上がってしまって、燃料が溶けるようなことになれば、「東京すら放棄するしかない」と当時の原子力委員会の近藤駿介委員長が報告書を出しました。」
とおっしゃっています(https://www.youtube.com/watch?v=nCbXX3DURd0)。
フクシマ原発事故は、アンダー・コントロール、作業が進んでいるのではなくて、アウト・オブ・コントロール コントロールできず、いまも、放射能が撒き散らされている状況が暴走している訳です。
フクシマ原発は、漏れた放射能汚染水で、「放射能汚染水の沼」になっていると言います。
いまも、フクシマ原発は、放射能の泥沼にあり、フクシマ原発から、放射能が撒き散らされているのが、日本の偽らざる真実の姿なのですね。
そんなところに、一般市民である楢葉町の住民を戻していいのでしょうか?
そんなところで、オリンピックなんぞをしていていいのでしょうか?
私は、楢葉町に一般市民を戻すことは、全人類に対する犯罪 だと確信します。
今のニッポンは、オリンピックなんぞをしている場合ではない と確信します。













 国立市。東京の小さな町。私の出身地。 国立市在住で最も有名な人はだれか? 山口百恵さんを挙げる人が多いでしょうね。 でも、私は生まれも育ちも国立市谷保...
国立市。東京の小さな町。私の出身地。 国立市在住で最も有名な人はだれか? 山口百恵さんを挙げる人が多いでしょうね。 でも、私は生まれも育ちも国立市谷保...

 昨日で『人を大事にする術』の翻訳が完了。 今日は、レイチェル・カーソンのThe Sense of Wonder 不思議を感じる感じ から p52。&n...
昨日で『人を大事にする術』の翻訳が完了。 今日は、レイチェル・カーソンのThe Sense of Wonder 不思議を感じる感じ から p52。&n...
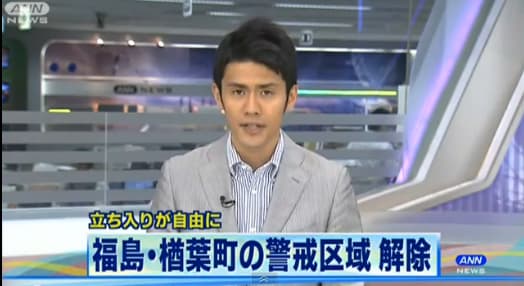


 自分を確かにする感じ、時代さえ変えてしまう力があります。 p177第2パラグラフ。 &n...
自分を確かにする感じ、時代さえ変えてしまう力があります。 p177第2パラグラフ。 &n...





