この世界に無駄なものなど一切ない......と、思います。
皆、全てが、必要があって存在している、と。
存在しているということそれ自体が、
何かや誰かに必要とされていることの証明であると。
ただ、音楽や芸能というのは、
時にそんな世界の真実を浮き立たせるための、
思い出させるための、
色がより鮮やかに見えてくるようにするための、
その為のカウンター的役割を担っているような時や
コトいうのがある様にも思います。
僕は以前、そんなコンセプトを裏に隠し持ったライブを
敢行していたことがありました。
カウンター故に、
全くもってマス......メジャー、大衆的......
なコンセプトではないので、
当時メジャーレーベルで働いていた僕としては、
そのコンセプトと水が合う
「インディーズ」という形態とチームを新たに作り、
取り掛かっていました。
結果としてそのライブは毎回とても実験的で、
挑戦的なスタイルとなって世に問う形となっていきました。
そんなライブのメインアクトは当時14歳の少女詩人。
螢。
活動の基幹となっていたCDパッケージ周りに関しては、
音楽は勿論、デザインやウェブも彼女の世界観に合うように、
皆エッジの立ったクリエーター陣で組んではいましたが、
彼女のやりたい事や伝えたい事がフィルター・レスで表現できて、
ファンにもよく伝わるライブの方は、パッケージとはまた違う、
彼女が何かと話をしやすいスタッフィングで臨んでもいました。
そんな彼女なりの世の中へのカウンターを詰め込んだステージは、
勿論、苦労も多かったのですが、毎回とても印象的で面白く。
様々な部分を一緒に創っていた僕でも、
見ていていつも鳥肌が立っていたことを覚えています。
会場となる場所に関しては
「あくまで彼女は詩人であって、音楽人ではないのです......」
という精神性を示す為、演劇系の劇場を選びました。
プロデューサーの僕としては、
彼女に劇場以外の会場はイメージできなかったですし、
ライブハウスなどの場合、ミュージシャンでもない彼女は必ず、
いろんな意味でステージで苦しくなっていくであろうと。
そんな考えもあり、チームみんなで話し合いながら、
初期の彼女のホームグラウンドはそんな劇場に決めていました。
東京、銀座小劇場。
一人芝居とポエトリー・リーディングと音楽と。
そういうものをミクスチュアした、
創っている僕自身もよく分かっていないまま敢行していたステージ。
忘れ得ぬ彼女のステージ。
なぜ?
今まで何本、何十本!?と見て、
作っても来た音楽やエンタメのステージの中で、なぜ?
彼女のライブが僕の中で今だ忘れられないモノであり続けているのか?
しかも、100人も入ればパンパン......となる様な、
古い民家の屋根裏の様な、うらぶれた小劇場のステージなのに......
それは......
僕が創って来たステージの中で、
観客から「一つの拍手も起こらなかった」ものは
彼女のステージしかないからです。
観客から「一度も声が聞こえなかった」ステージも
彼女のものしかないからです。
「歓声も拍手も望まなかった」ステージも
彼女のものしかなかったからです。
初のインディーズアルバムを発売した直後。
チケットも即完売したセカンドライブに至っては、彼女は......
その時集まった100人以上の観客達に向かってマイクを握り、
ステージの最後、
演出的にも一番注目が集まるところでこう言い放ちました......
「みんな死ねばいい」
彼女はそのままマイクを放り投げて、
ステージサイドに歩き去って行きました。
客席は水を打ったようにシーンとして、
誰一人、身動きをしませんでした。
舞台で詠まれた詩の延長上にある言葉の様でもあるし、
そうでないかも知れない。
14歳の少女が放ったこの言葉をいったい、
どう受け止めればいいのか?
誰もが、
そんなことを考えていた様に思います。
真っ暗闇となっていた会場で「死ねばいい」と言われ、
終演後も呆然と座り込む観客。
僕らは客電を必要以上に明るく点け、然りげ無く、
会場を出る様に......と促しました。
「......ご、誤解だヨォォォーーーっ!?(@。@)
螢わイイ子なんだよぉぉーーっ!」
と、僕は心で叫びつつも、
PA卓辺りから見たその会場の様子は
未だに忘れられない光景となって心に残っています。
デビューライブからずっと追いかけてくれていた親愛なるライターさんが、
そんな彼女のライブの様子をある雑誌でこんなふうに書いていました。
==========================
「14歳の少女詩人・螢」は今や業界的にも
最注目の新人なんて呼ばれている。
だがその日、
暗幕を垂らしただけのごく質素でダークなイメージには
「いよいよこれから何かが始まる!」
なんて月並みな高揚感はかけらも無かった。
むしろ、何かを葬り去ろうという黒い意志。
それをよりどころに慎重152センチの小さなカラダは
闇の中に立っている様に見えた。
拍手なんか誰もしない。身動きもできない。
硬い椅子に座り、
じっと耐えるような気持ちでコトバに耳を澄ます。
全編80分の倒錯した夢みたいなライブ。
出口にはNHKのニュース番組のカメラが待っていた。
監禁から解かれた客たちの顔に笑顔は無かった。
==========================
こんなライブは後にも先にも、僕にとっては螢だけ。
大抵はいつも観客の拍手を望み、
笑顔を望み、
満足や幸福や希望を望み。
それがエンターテイメントの仕事。そんなものです。
そしてソレ故に、
彼女のステージは今も僕には特別なのです。
良い悪いを越えたところにあるものなのです。

このライターさんの記事や螢のことが特集で組まれた雑誌
「QuickJapan(クイックジャパン)」
ネットワーク社会以前、鈍い輝きを放っていた「サブカルチャー」
シーンにおける代表的雑誌の一つ。
思えば、螢が表紙を飾った最初の雑誌でした。
今も自宅の書棚にストックされています。
この号の特集にはまた違う回のライブのことが書かれていて、
それは予想外の!?
CDの「メジャーリリース」が決定した直後のステージのこと。
インディーズ時代とはうって変わって、
必然的に様々な関係者や大人達が大勢押し寄せたライブともなったステージで、
また彼女は最後に皆を黙らせる一言を言い放ったのでした。
それが雑誌の表紙にもなってしまったコトバ。
「ムダな人数」
この後、僕はかなりのバッシングを直接的にも間接的にも受けたり、
人伝のモノ言いで耳にしたりもしましたが、
やはり、僕からすれば、
とても彼女らしい「愛すべき」立ち回り。
スタートからのコンセプトにも沿った!?名セリフ。
「俺達だけはなんとしても彼女を護らねば、、」
と。そんな悪戦苦闘をしていたことも覚えています。
良い悪いを越えたところで捉えて欲しいコトバ。
「......ご、誤解だヨォォォーーーっ!?(@。@)
螢わヤサスィー子なんだよぉぉーーっ!」
こんな感じの、
小さな少女の挑発的な言動を受けざるをえない
大人のインタビューアーさん達は、
人によっては受けて立ったり、戦ってみたり。
流してみたり。
見透かしてみたり。
子供扱いしてみたり。
すぐ近くで見ていた僕にとってはそれはそれで、この世の
「普段見えなくなっている何か」
を浮き上がらせてもくれる時間であったりもしました。
写真にあるこの本のインタビューの中でも、
彼女はこんな受け答えをしています。
===============================
学校は本当にきらい。ぜんぶ。
教科とかじゃなくてぜんぶ。
場所として嫌い。
なんにも言えなかったから、コトバに出来なかったから、
だからその気持ちを紙に書いた。
—————あの日は平日だったっけ?
うん。学校休んだ。
—————なんて言って?
ライブだからって。
—————先生はなんて?
あ、そうって。
—————この間、関係者の人が
「螢は学校では表現できなかったものを表現できる場を見つけた」
って言ってたんだけど当たってる?
うん。
......だって学校でどうやって表現なんかしろっていうの?
—————学校じゃ何も表現できない?
うん。
—————最近ちゃんと「おつかれさま」とか言うようになったよね?
言ってないよ。
—————言ってるじゃないですか。
べつに言いたい人には言うけど、言いたくない人には言わない。
良い仕事をした時だけ言うようにしてる。
—————自分の中で大体どれくらい先まで考えてる?
そんなの知らないよ。
===============================
ソーシャル・ネットワークの時代。
誰かと繋がりたいと思えば、いつでも繋がれて。
様々な表現が出来て。
とても幸せな時代だと思います。
しかし、それ故に生まれた闇も、
悩みみたいなものもあるのではないでしょうか。
特に、不器用な人にとっては本当に切実な話なども。きっと。
そんな人達の顔が今回の螢の話を記していて思い浮かんできました。
今は亡き、
敬愛する哲学者の池田晶子さんがこんなことを記し残しています。
「空虚な孤独が空虚な言葉で繋がって、
果たして繋がったことになるのかと疑う。
他人を求めるよりは、
自分を求めることのほうが、順序としては先のはずだ」
「この人の世では、人は人に好かれたいと必ず思い、
人に嫌われたくない、と必ず思っている。
好かれたくて嫌われたくないのが人の世の原理なのである。
やはりこれは凄いことではなかろうか。
他人にどう思われるかが、自分の行為の基準なのである。
実に多くの人がそうやって人生を生きていくのである。
端的に、これが社会というものである。
本当に驚くべきことだと私は思う」
池田さんのこんな言葉を省みても、
螢という少女と過ごした時間を思い出してみても、
世の中へのカウンターとしての音楽は大切にしなければ、と。
そんなことを思います。
カウンターとしての価値や意義はまだまだ、
しばらく失ってはならないと。
カウンターはいつも美しく、魅惑的なものであれ、と。
改めて、そんなことを思う次第なのです。
.......1年毎と約束していた螢の記事を待っていていくれた皆さん。
今年は遅れてしまい申し訳ありませんでした。
お詫びいたします。
「螢」の記事はサイト左にあるカテゴリー・メニュー
「初めに、タイトルの話」に全て纏めてあります。
良き夏をお過ごしください!(^^)
皆、全てが、必要があって存在している、と。
存在しているということそれ自体が、
何かや誰かに必要とされていることの証明であると。
ただ、音楽や芸能というのは、
時にそんな世界の真実を浮き立たせるための、
思い出させるための、
色がより鮮やかに見えてくるようにするための、
その為のカウンター的役割を担っているような時や
コトいうのがある様にも思います。
僕は以前、そんなコンセプトを裏に隠し持ったライブを
敢行していたことがありました。
カウンター故に、
全くもってマス......メジャー、大衆的......
なコンセプトではないので、
当時メジャーレーベルで働いていた僕としては、
そのコンセプトと水が合う
「インディーズ」という形態とチームを新たに作り、
取り掛かっていました。
結果としてそのライブは毎回とても実験的で、
挑戦的なスタイルとなって世に問う形となっていきました。
そんなライブのメインアクトは当時14歳の少女詩人。
螢。
活動の基幹となっていたCDパッケージ周りに関しては、
音楽は勿論、デザインやウェブも彼女の世界観に合うように、
皆エッジの立ったクリエーター陣で組んではいましたが、
彼女のやりたい事や伝えたい事がフィルター・レスで表現できて、
ファンにもよく伝わるライブの方は、パッケージとはまた違う、
彼女が何かと話をしやすいスタッフィングで臨んでもいました。
そんな彼女なりの世の中へのカウンターを詰め込んだステージは、
勿論、苦労も多かったのですが、毎回とても印象的で面白く。
様々な部分を一緒に創っていた僕でも、
見ていていつも鳥肌が立っていたことを覚えています。
会場となる場所に関しては
「あくまで彼女は詩人であって、音楽人ではないのです......」
という精神性を示す為、演劇系の劇場を選びました。
プロデューサーの僕としては、
彼女に劇場以外の会場はイメージできなかったですし、
ライブハウスなどの場合、ミュージシャンでもない彼女は必ず、
いろんな意味でステージで苦しくなっていくであろうと。
そんな考えもあり、チームみんなで話し合いながら、
初期の彼女のホームグラウンドはそんな劇場に決めていました。
東京、銀座小劇場。
一人芝居とポエトリー・リーディングと音楽と。
そういうものをミクスチュアした、
創っている僕自身もよく分かっていないまま敢行していたステージ。
忘れ得ぬ彼女のステージ。
なぜ?
今まで何本、何十本!?と見て、
作っても来た音楽やエンタメのステージの中で、なぜ?
彼女のライブが僕の中で今だ忘れられないモノであり続けているのか?
しかも、100人も入ればパンパン......となる様な、
古い民家の屋根裏の様な、うらぶれた小劇場のステージなのに......
それは......
僕が創って来たステージの中で、
観客から「一つの拍手も起こらなかった」ものは
彼女のステージしかないからです。
観客から「一度も声が聞こえなかった」ステージも
彼女のものしかないからです。
「歓声も拍手も望まなかった」ステージも
彼女のものしかなかったからです。
初のインディーズアルバムを発売した直後。
チケットも即完売したセカンドライブに至っては、彼女は......
その時集まった100人以上の観客達に向かってマイクを握り、
ステージの最後、
演出的にも一番注目が集まるところでこう言い放ちました......
「みんな死ねばいい」
彼女はそのままマイクを放り投げて、
ステージサイドに歩き去って行きました。
客席は水を打ったようにシーンとして、
誰一人、身動きをしませんでした。
舞台で詠まれた詩の延長上にある言葉の様でもあるし、
そうでないかも知れない。
14歳の少女が放ったこの言葉をいったい、
どう受け止めればいいのか?
誰もが、
そんなことを考えていた様に思います。
真っ暗闇となっていた会場で「死ねばいい」と言われ、
終演後も呆然と座り込む観客。
僕らは客電を必要以上に明るく点け、然りげ無く、
会場を出る様に......と促しました。
「......ご、誤解だヨォォォーーーっ!?(@。@)
螢わイイ子なんだよぉぉーーっ!」
と、僕は心で叫びつつも、
PA卓辺りから見たその会場の様子は
未だに忘れられない光景となって心に残っています。
デビューライブからずっと追いかけてくれていた親愛なるライターさんが、
そんな彼女のライブの様子をある雑誌でこんなふうに書いていました。
==========================
「14歳の少女詩人・螢」は今や業界的にも
最注目の新人なんて呼ばれている。
だがその日、
暗幕を垂らしただけのごく質素でダークなイメージには
「いよいよこれから何かが始まる!」
なんて月並みな高揚感はかけらも無かった。
むしろ、何かを葬り去ろうという黒い意志。
それをよりどころに慎重152センチの小さなカラダは
闇の中に立っている様に見えた。
拍手なんか誰もしない。身動きもできない。
硬い椅子に座り、
じっと耐えるような気持ちでコトバに耳を澄ます。
全編80分の倒錯した夢みたいなライブ。
出口にはNHKのニュース番組のカメラが待っていた。
監禁から解かれた客たちの顔に笑顔は無かった。
==========================
こんなライブは後にも先にも、僕にとっては螢だけ。
大抵はいつも観客の拍手を望み、
笑顔を望み、
満足や幸福や希望を望み。
それがエンターテイメントの仕事。そんなものです。
そしてソレ故に、
彼女のステージは今も僕には特別なのです。
良い悪いを越えたところにあるものなのです。

このライターさんの記事や螢のことが特集で組まれた雑誌
「QuickJapan(クイックジャパン)」
ネットワーク社会以前、鈍い輝きを放っていた「サブカルチャー」
シーンにおける代表的雑誌の一つ。
思えば、螢が表紙を飾った最初の雑誌でした。
今も自宅の書棚にストックされています。
この号の特集にはまた違う回のライブのことが書かれていて、
それは予想外の!?
CDの「メジャーリリース」が決定した直後のステージのこと。
インディーズ時代とはうって変わって、
必然的に様々な関係者や大人達が大勢押し寄せたライブともなったステージで、
また彼女は最後に皆を黙らせる一言を言い放ったのでした。
それが雑誌の表紙にもなってしまったコトバ。
「ムダな人数」
この後、僕はかなりのバッシングを直接的にも間接的にも受けたり、
人伝のモノ言いで耳にしたりもしましたが、
やはり、僕からすれば、
とても彼女らしい「愛すべき」立ち回り。
スタートからのコンセプトにも沿った!?名セリフ。
「俺達だけはなんとしても彼女を護らねば、、」
と。そんな悪戦苦闘をしていたことも覚えています。
良い悪いを越えたところで捉えて欲しいコトバ。
「......ご、誤解だヨォォォーーーっ!?(@。@)
螢わヤサスィー子なんだよぉぉーーっ!」
こんな感じの、
小さな少女の挑発的な言動を受けざるをえない
大人のインタビューアーさん達は、
人によっては受けて立ったり、戦ってみたり。
流してみたり。
見透かしてみたり。
子供扱いしてみたり。
すぐ近くで見ていた僕にとってはそれはそれで、この世の
「普段見えなくなっている何か」
を浮き上がらせてもくれる時間であったりもしました。
写真にあるこの本のインタビューの中でも、
彼女はこんな受け答えをしています。
===============================
学校は本当にきらい。ぜんぶ。
教科とかじゃなくてぜんぶ。
場所として嫌い。
なんにも言えなかったから、コトバに出来なかったから、
だからその気持ちを紙に書いた。
—————あの日は平日だったっけ?
うん。学校休んだ。
—————なんて言って?
ライブだからって。
—————先生はなんて?
あ、そうって。
—————この間、関係者の人が
「螢は学校では表現できなかったものを表現できる場を見つけた」
って言ってたんだけど当たってる?
うん。
......だって学校でどうやって表現なんかしろっていうの?
—————学校じゃ何も表現できない?
うん。
—————最近ちゃんと「おつかれさま」とか言うようになったよね?
言ってないよ。
—————言ってるじゃないですか。
べつに言いたい人には言うけど、言いたくない人には言わない。
良い仕事をした時だけ言うようにしてる。
—————自分の中で大体どれくらい先まで考えてる?
そんなの知らないよ。
===============================
ソーシャル・ネットワークの時代。
誰かと繋がりたいと思えば、いつでも繋がれて。
様々な表現が出来て。
とても幸せな時代だと思います。
しかし、それ故に生まれた闇も、
悩みみたいなものもあるのではないでしょうか。
特に、不器用な人にとっては本当に切実な話なども。きっと。
そんな人達の顔が今回の螢の話を記していて思い浮かんできました。
今は亡き、
敬愛する哲学者の池田晶子さんがこんなことを記し残しています。
「空虚な孤独が空虚な言葉で繋がって、
果たして繋がったことになるのかと疑う。
他人を求めるよりは、
自分を求めることのほうが、順序としては先のはずだ」
「この人の世では、人は人に好かれたいと必ず思い、
人に嫌われたくない、と必ず思っている。
好かれたくて嫌われたくないのが人の世の原理なのである。
やはりこれは凄いことではなかろうか。
他人にどう思われるかが、自分の行為の基準なのである。
実に多くの人がそうやって人生を生きていくのである。
端的に、これが社会というものである。
本当に驚くべきことだと私は思う」
池田さんのこんな言葉を省みても、
螢という少女と過ごした時間を思い出してみても、
世の中へのカウンターとしての音楽は大切にしなければ、と。
そんなことを思います。
カウンターとしての価値や意義はまだまだ、
しばらく失ってはならないと。
カウンターはいつも美しく、魅惑的なものであれ、と。
改めて、そんなことを思う次第なのです。
.......1年毎と約束していた螢の記事を待っていていくれた皆さん。
今年は遅れてしまい申し訳ありませんでした。
お詫びいたします。
「螢」の記事はサイト左にあるカテゴリー・メニュー
「初めに、タイトルの話」に全て纏めてあります。
良き夏をお過ごしください!(^^)










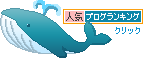












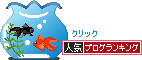







今もあの衝撃を覚えています。
無神経で想像力のない社会への
アンチテーゼのようです。
uzmetさんの生き方と
かぶるのではないでしょうか。
ありがとうございます(^^)
とても読みやすく仕上がってましたね♪
ありがとうございます。
今年は遅れてしまい申し訳ありませんでした。