「赤」は「紅」「朱=しゅ」とも表されます。
色の遷移を円形チャートで表す「色相環表」では
「緑」に対して180度正対する位置......
いわゆる互いの色を引き立てあい、
補い合う色である「補色=ほしょく」の位置に置かれています。
野山に拡がる「緑」の中で、自らの種子を作り、
蒔き広げようと咲き誇る花さん達に赤系の色が多い理由もココにあります。
そこには、自らの命や種の大元である「タネ」を運んでくれる
動物や昆虫さん達に分かり易いようにと、
補色の関係を利用し、
目立たせようとした植物たちの確信に満ちた進化!?
神の叡智!?
をも感じられます。
そして、僕らの生命を運ぶ血液の色も「赤」です。
そんなところから古来「赤」は生命力の象徴となってきました。
古代の人々は猛獣と相対する狩猟に出かけたり、
避けられぬ戦などに出かけなければいけない時には、
武運や無事を祈り、顔に赤い顔料を塗ったりもしました。
その顔料に「赤」や「紅=べに」が多かったのも、
この赤い色が持つ「生命力」が何よりもの「魔除け」
になると信じられていたからです。
塗料を「顔料」と書くのもここに起因します。
女性の口紅、化粧、メイクの起源もここにあります。
「七五三」で母親が幼き娘さんに
そっと紅を差してあげるのにもこんな理由があります。
本来メイクは、紅は、魔を避けるものです。
最近は男を惹きつけますが.......!?_φ( ̄ー ̄ )
神社の敷地結界を示す鳥居が赤いのもここに理由があります。
魔の侵入を防ぐには、
強力な生命力を持つ「赤」で封じるのが最強......とされたのです。
それで......
少し前に友人と訪れた地に立っていたこの樹。
この木々......



真っ赤です。
真っ赤に聳える大きな木。
大木の持つ生命力と赤の持つ生命力とが重なり、
異様な力と雰囲気を醸し出しています......
ちょっと不思議な感じ。
一般的に「赤い幹の木」として知られるのは
「ヒメシャラ」辺りだと思いますが、
ここまでの大木になると、
屋久島あたりまで行かないことにはそうそうお目にかかれません。
ヒメシャラは幹もツルツルですし、
この木は明らかに違いますし。
ということは......
すぐわかった方もいるかとは思いますが......
実はこの木、誰もが知っているであろうとてもメジャーな木......
「杉」なのです。
「スギ」。
スギちゃん。
ちなみに此方が普通のスギちゃん。

群馬県、榛名神社の千本杉。

茨城県、鹿島神宮参道の杉並木と、下は神奈川県、大山阿夫利神社登山道の杉林。

どれもマッタク同じ杉の木。
しかし、あまりに違う色をしています。
同じ杉同士並んでみてもその違いは一目瞭然。


「スギ」は「水の木」でもあって「すいのき」。
以前「進化論の絵図」と言う記事の中で触れた
「戸隠神社の杉並木」の部分でも書きましたが、
杉は地中から大量の水を体内に汲み上げるような木です。
だから杉の大木は水が潤沢にある場所に多く育ちます。
その杉の木がこんな色をしているなんて.......
だから、こんな杉の木を見た時には僕はこう考えるのです。
「きっと......この地には、多くの “朱” が眠っているに違いない......」
デジタル化される前の体温計で使われていた銀色に輝く液体......
「水銀」というのは、古代においてとても珍重されていた物質で。
何故かというと、
先ずは「常温で液体化する金属」という不思議な性質が見せる、
金属なのにウネウネとした蛇のような!?不可思議な動き......と、
何より、その原料となる鉱物「辰砂=しんしゃ」と呼ばれる岩石が
「真っ赤」な色をしていたというところ。
それは記したように自然界ではとても目立つ色でもあり、
生命力の象徴でもあることから、
古代中国や日本ではこれを飲むと不老不死の仙人になれる......
という思想も生まれました。
時の権力者が大金を出してでも欲しい薬「仙丹=せんたん」
今考えると、毒を飲むのに等しいこの行為。
時代とは恐ろしいものです(; ̄ェ ̄)
さらに水銀は、貴金属業界や鉄工関係に従事している人であればよく知っているように、
古代においてモノに「メッキ」をする際に不可欠な物質です。
仏像を金ピカにしたい時、
建物や鳥居を「長持ちする赤」で塗りたい時、
指輪を銀色にしたい時、
色々な金属に装飾をしたい時、
水銀が必要になります。
水銀は神社仏閣、宗教関係者からも垂涎の物質であり。
時の権力者からも宗教関係者からも、様々な工芸職人さん達からも、
とても必要とされる貴重なる宝が「水銀」だったのです。
水銀は、言わば、古代における「金のなる木」です。
コレを上手く扱える人は洋の東西を問わず、時にこう呼ばれたのです......
「錬金術士=れんきんじゅつし」
と。
地下から大量の水を吸って育つ杉の木が真っ赤に染まっている......
しかも、それが、一定範囲に広く、何本も何本も聳え立ち......
ということは、この地の水には赤い色が混じっていて、
それが杉の表皮に出ている......
こんな山奥で、地中で赤や朱色を出すものといえば.......
辰砂......しんしゃ.......赤い石......
この地には沢山の辰砂が含まれているに違いない。
掘れば沢山出てくるだろう......
して、
それは、
水銀の原料......
だから僕はこんな珍しい「真っ赤」な杉を目にした時にこう考えるのです......
「......もうかりまんな( ̄+ー ̄)キラーン」
つづく......
色の遷移を円形チャートで表す「色相環表」では
「緑」に対して180度正対する位置......
いわゆる互いの色を引き立てあい、
補い合う色である「補色=ほしょく」の位置に置かれています。
野山に拡がる「緑」の中で、自らの種子を作り、
蒔き広げようと咲き誇る花さん達に赤系の色が多い理由もココにあります。
そこには、自らの命や種の大元である「タネ」を運んでくれる
動物や昆虫さん達に分かり易いようにと、
補色の関係を利用し、
目立たせようとした植物たちの確信に満ちた進化!?
神の叡智!?
をも感じられます。
そして、僕らの生命を運ぶ血液の色も「赤」です。
そんなところから古来「赤」は生命力の象徴となってきました。
古代の人々は猛獣と相対する狩猟に出かけたり、
避けられぬ戦などに出かけなければいけない時には、
武運や無事を祈り、顔に赤い顔料を塗ったりもしました。
その顔料に「赤」や「紅=べに」が多かったのも、
この赤い色が持つ「生命力」が何よりもの「魔除け」
になると信じられていたからです。
塗料を「顔料」と書くのもここに起因します。
女性の口紅、化粧、メイクの起源もここにあります。
「七五三」で母親が幼き娘さんに
そっと紅を差してあげるのにもこんな理由があります。
本来メイクは、紅は、魔を避けるものです。
最近は男を惹きつけますが.......!?_φ( ̄ー ̄ )
神社の敷地結界を示す鳥居が赤いのもここに理由があります。
魔の侵入を防ぐには、
強力な生命力を持つ「赤」で封じるのが最強......とされたのです。
それで......
少し前に友人と訪れた地に立っていたこの樹。
この木々......



真っ赤です。
真っ赤に聳える大きな木。
大木の持つ生命力と赤の持つ生命力とが重なり、
異様な力と雰囲気を醸し出しています......
ちょっと不思議な感じ。
一般的に「赤い幹の木」として知られるのは
「ヒメシャラ」辺りだと思いますが、
ここまでの大木になると、
屋久島あたりまで行かないことにはそうそうお目にかかれません。
ヒメシャラは幹もツルツルですし、
この木は明らかに違いますし。
ということは......
すぐわかった方もいるかとは思いますが......
実はこの木、誰もが知っているであろうとてもメジャーな木......
「杉」なのです。
「スギ」。
スギちゃん。
ちなみに此方が普通のスギちゃん。

群馬県、榛名神社の千本杉。

茨城県、鹿島神宮参道の杉並木と、下は神奈川県、大山阿夫利神社登山道の杉林。

どれもマッタク同じ杉の木。
しかし、あまりに違う色をしています。
同じ杉同士並んでみてもその違いは一目瞭然。


「スギ」は「水の木」でもあって「すいのき」。
以前「進化論の絵図」と言う記事の中で触れた
「戸隠神社の杉並木」の部分でも書きましたが、
杉は地中から大量の水を体内に汲み上げるような木です。
だから杉の大木は水が潤沢にある場所に多く育ちます。
その杉の木がこんな色をしているなんて.......
だから、こんな杉の木を見た時には僕はこう考えるのです。
「きっと......この地には、多くの “朱” が眠っているに違いない......」
デジタル化される前の体温計で使われていた銀色に輝く液体......
「水銀」というのは、古代においてとても珍重されていた物質で。
何故かというと、
先ずは「常温で液体化する金属」という不思議な性質が見せる、
金属なのにウネウネとした蛇のような!?不可思議な動き......と、
何より、その原料となる鉱物「辰砂=しんしゃ」と呼ばれる岩石が
「真っ赤」な色をしていたというところ。
それは記したように自然界ではとても目立つ色でもあり、
生命力の象徴でもあることから、
古代中国や日本ではこれを飲むと不老不死の仙人になれる......
という思想も生まれました。
時の権力者が大金を出してでも欲しい薬「仙丹=せんたん」
今考えると、毒を飲むのに等しいこの行為。
時代とは恐ろしいものです(; ̄ェ ̄)
さらに水銀は、貴金属業界や鉄工関係に従事している人であればよく知っているように、
古代においてモノに「メッキ」をする際に不可欠な物質です。
仏像を金ピカにしたい時、
建物や鳥居を「長持ちする赤」で塗りたい時、
指輪を銀色にしたい時、
色々な金属に装飾をしたい時、
水銀が必要になります。
水銀は神社仏閣、宗教関係者からも垂涎の物質であり。
時の権力者からも宗教関係者からも、様々な工芸職人さん達からも、
とても必要とされる貴重なる宝が「水銀」だったのです。
水銀は、言わば、古代における「金のなる木」です。
コレを上手く扱える人は洋の東西を問わず、時にこう呼ばれたのです......
「錬金術士=れんきんじゅつし」
と。
地下から大量の水を吸って育つ杉の木が真っ赤に染まっている......
しかも、それが、一定範囲に広く、何本も何本も聳え立ち......
ということは、この地の水には赤い色が混じっていて、
それが杉の表皮に出ている......
こんな山奥で、地中で赤や朱色を出すものといえば.......
辰砂......しんしゃ.......赤い石......
この地には沢山の辰砂が含まれているに違いない。
掘れば沢山出てくるだろう......
して、
それは、
水銀の原料......
だから僕はこんな珍しい「真っ赤」な杉を目にした時にこう考えるのです......
「......もうかりまんな( ̄+ー ̄)キラーン」
つづく......










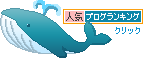




















真っ赤な杉、一度見て見たいです。
見ちゃってくだされぇぇぇーーーっ!(○´∀`○)ノえんりょなくぅぅぅーー!
金属イオンが蓄積するクマツヅラという植物を目印に鉱脈を探していたそうです。
空海の死因、
奈良から京都への遷都も
(大仏建立による)
水銀の鉱毒によるもの
ともいわれているそうです。