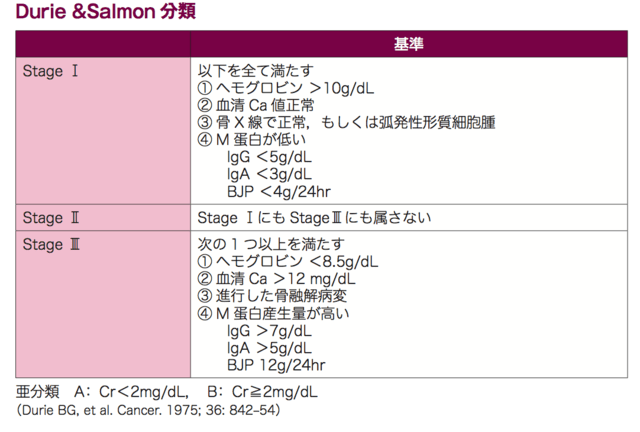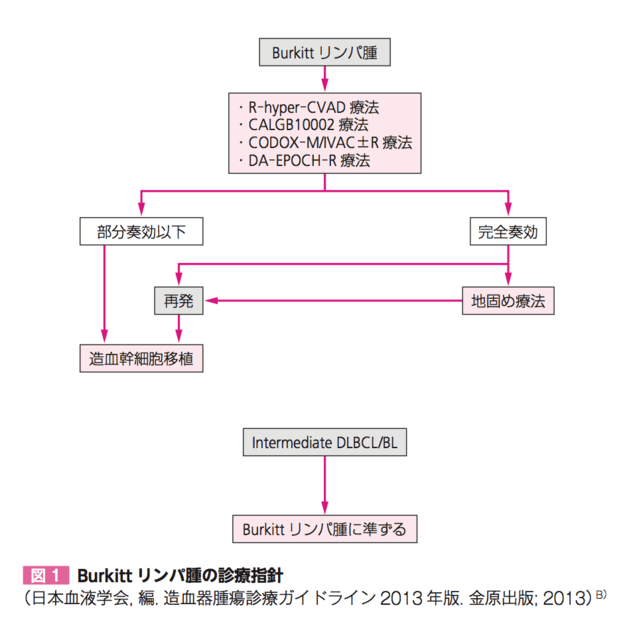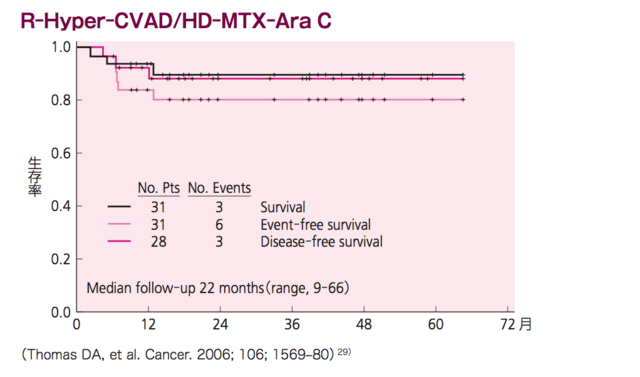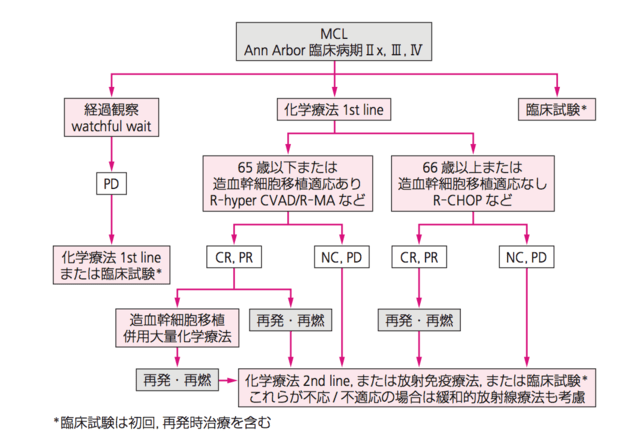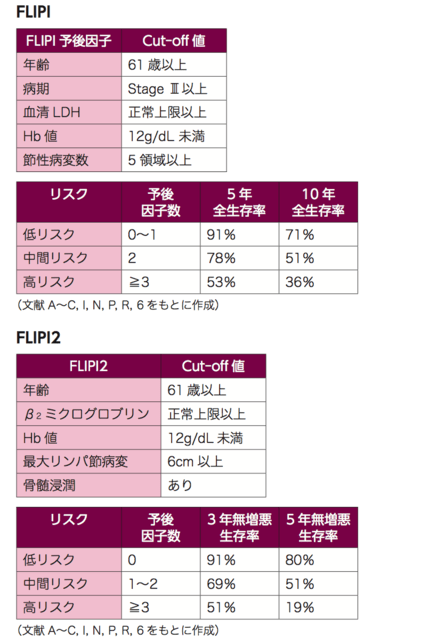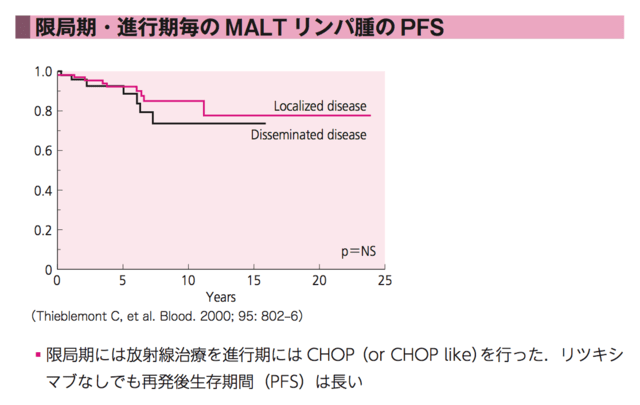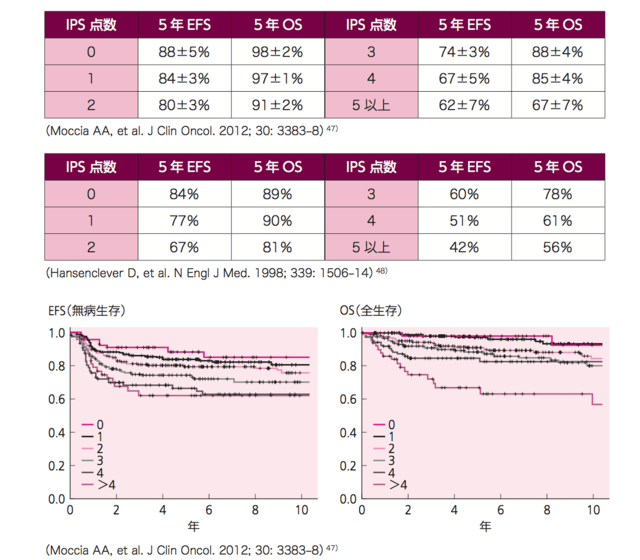特発性(免疫性)血小板減少性紫斑病(ITP)は血小板に対する自己抗体のため、脾臓で血小板が処理されて、血小板が低下する疾患です。この自己抗体がちぎれる前の血小板(巨核球からちぎれた断片が血小板なので、巨核球にもペタペタ張り付きます)にも影響するとも言われています。
基本的に血小板産生は正常から亢進しているので、自己抗体の産生を抑えれば血小板は増えてきます。しかし、それでもダメな時は血小板を食べる脾臓を摘出したり、巨核球に刺激を与えて血小板産生を増やしたりします(巨核球にひっついている自己抗体が血小板産生を邪魔しているとも言われてます)。
自己抗体が関連するものは治療に基本的にステロイド剤を使用します。難治になるとリツキシマブなども使用されたりします。
血小板数は10万/µl以上あれば正常で、5万/µl以上あれば出血が起きやすい手術でない限りは安全に実施できるといいます(整形外科の骨切り術とかは警戒しますが)。3万/µl以上あれば(研究によっては2万/µlでも大丈夫)出血死のリスクは健常人と変わらないと言われます。
そのため、副作用の多いステロイド剤による治療は「出血傾向がない」状況であれば2万/µl未満、もしくは3万/µl未満になるまで様子をみます。
それまでに唯一できる治療がヘリコバクター・ピロリ菌の除菌です。イタリアと日本からの報告ですが、ピロリ菌陽性のITPの場合、除菌が成功すると40%の患者さんで血小板数が上昇します。そのため、ステロイド治療の前に行うことができる唯一の治療法になります。
・・・この疾患も、過去に説明記事を書いていないのか・・・。意外だ〜。
この疾患は特定疾患ですので、国の補助が受けられます。
では、簡単に書いていきます。
Wさんは先日健康診断で、血小板という数値が5万/µlと減少していたため、当院に紹介となりました。
血液検査では白血球 6000/µl、ヘモグロビン 15g/dlと正常範囲ですが、血小板数のみ5万/µlと減少していました。
末梢血液像では通常血液中にいない細胞、例えば白血病細胞や不良品の血液(異形成)などはなく、割合も正常でした。
凝固系も正常で(PTやAPTT、FDP)した。これは播種性血管内凝固(DIC)という病気やAPTTが延長して血小板が下がる病気(抗リン脂質抗体症候群)ではないことを示しています。
抗核抗体など膠原病の因子も異常はなさそうです。PAIgGという血小板にひっついている抗体の数を示すものですが、120と少し上昇していました。しかし、これは血小板数が下がれば普通上昇するので、参考程度と考えています。
Wさん:先日行った骨髄の方はいかがでしたか?
骨髄の検査ですが、血液細胞の数は正常で(正形成骨髄)、巨核球という血小板を作る細胞の数も正常でした。白血病細胞などはなく、異形成(骨髄異形成症候群を示唆する)もありません。巨核球は少し表面がつるんとした感じの印象を受けますが、異形成はありません。
Wさん:病気の原因がはっきりしないということですか?
いえ、今までの検査の結果からITPと診断しました。この病気は他の病気の所見がないことを示す必要があります(除外診断)。
血小板を造る能力が落ちる病気(急性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血など)ではなく、他に血小板の消費が亢進する病気(DICなど)でもない。肝不全などで血小板が低下しているわけでもないなど、いくつかの病気を除外して診断します。
ITPは血小板を壊す抗体を作ってしまい、それがひっついた血小板は脾臓で壊されてしまいます。そういう病気です。
治療の基本は、この自己抗体を作らせなくすることにあります。その治療薬はステロイド剤というものを使います。この薬は色々な副作用がある薬です。そのため使用開始は副作用を超えるメリットがあるときに初めて使うことになります。
Wさんの血小板の数は5万/µlと低下していますが、実は血小板数は2万/µlくらいまで低下しないと出血などによる悪影響(大出血、出血に伴う死亡など)は増えないとされています。そのため、出血傾向がなければ2万/µl未満、出血症状が出ている患者さんでは3万/µl未満まで様子をみます(明らかに出血しているのであれば、3万/µl以上でも治療すると思いますが、普通はないです)。
Wさん:そうすると、しばらくは採血しながら様子見ですか?
その前に一つやっておくべき検査があります。実はこの病気はピロリ菌が原因で起きることがあります。ピロリ菌が陽性の患者さんで除菌を行うと、4割くらいの患者さんの血小板数が回復するといいます。まずはピロリ菌の検査と除菌を行いましょう。
Wさん:宜しく御願い致します。
こんな感じでしょうか。患者さんによっては即日入院してステロイドを入れることもあります(出血傾向があり、血小板数0.1万/µlとか)し、外来で導入することもあります(血小板数1万台くらい)。
ITPはピロリ菌の除菌、ステロイドで治療が終了しなかった場合は、脾臓摘出術やTPO-R(トロンボポエチン受容体)作動薬などを使用します。
いつも読んでいただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
http://blog.with2.net/link.php?602868
人気ブログランキングへ←応援よろしくお願いします
それでは、また。
 血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社
血液内科 ただいま診断中!クリエーター情報なし中外医学社