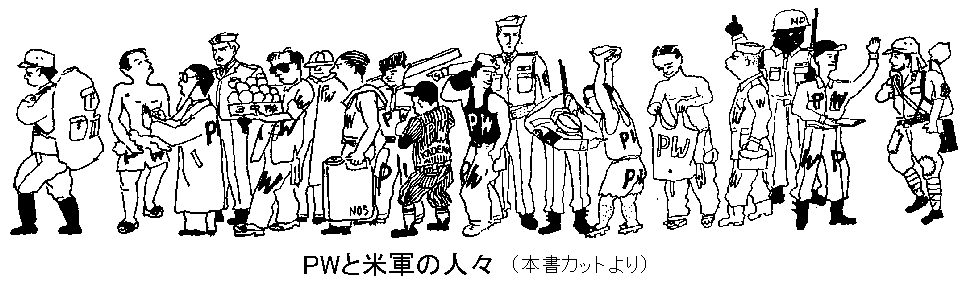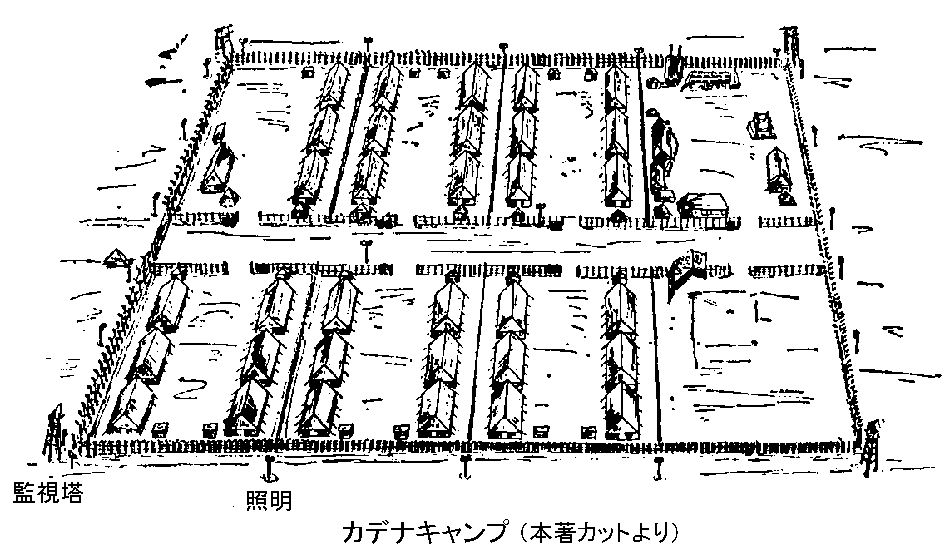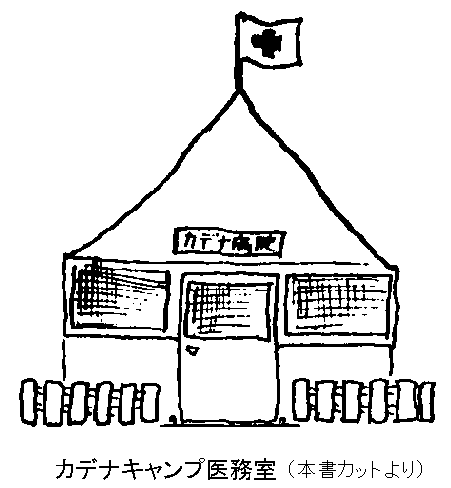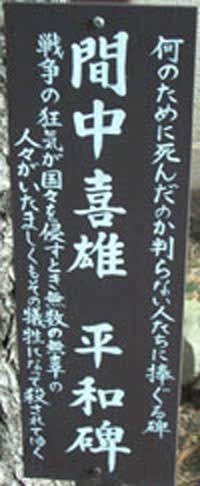坂井豊作(1815〜1878年)は、江戸時代徳川末期の針医。坂井が48歳の時、小森頼愛(よりなる)典薬頭の門に入る。小森家に伝わる横刺術を研究し、1865年「鍼術秘要」を著わした。同世代の者で最も有名な者に石坂宗哲(『鍼灸説約』1812年)がいる。
※典薬頭:「典薬」は宮中や江戸幕府に仕えた医師のことで、「頭」は、その長官。
坂井の鍼術の特徴は、経穴に刺すというより経絡に従って横刺するもので、経穴位置にこだわらず、丹念に指先で反応を捉えるのを特徴としていた。代田文誌は「針灸臨床ノート(下)」で、本書を、筋の反応点を指頭の触覚によってとらえ、これを克明に刺していったようで、それで著効をあげることができたのであろうと記した。代田文彦は、坂井豊作の横刺のことを「縫うように刺す」と表現していた。いわゆる鍼灸古典文献とは異なり、自分の考え方をしっかりと表明している点や、型にはまっていない記述スタイルが好印象である。
現代では、坂井流横刺は筋膜刺激として説明できそうだが、各症状に対する実際のテクニックはどのようなものだろうか。<鍼術秘要>は漢文で書かれているが、幸いなことに自然堂HPに、読み下し文が公開(漢方薬の説明部分は省略)されている。自然堂に感謝するとともに、これを底本として現代文への翻訳を試みた。本書は三部構成になっている。とりあえず「上」の部から着手してみた。ただし興味のわかない部分は省略した。
<鍼術秘要>には挿絵が多数載っている。なるべく鮮明な図をネットで発見して載せることにした。
本来、翻訳は私の得意な方ではなく、少なからず間違えもあると思う。間違えを発見された方は、ご指摘をお願います。
.

1.はじめに
大昔からの治療の一つに針法があり、種々の病に施術した。しかし後世においてはついにその術を失った。その上、国中のヤブ医者が針術をするようになると、その方法がかえって道理のある術ということになってしまい、古人のやり方の針術を論じる者がいなくなった。
現在の針医と称する者は、口先では十四経の経穴を唱えてはいるが、その針治療する姿を見るに、腹痛む者には、その痛む処の筋を刺し、シコリのある者には、そのシコリ辺りを刺し、痙攣する者には、その痙攣部の筋を刺す、このような状態では、病んでいる経に針が命中することはない。もしも病経に命中した場合であっても、刺し方が正しくないが故に、針先がかすかに経絡にふれるに過ぎず、病を治すことは非常に稀である。私は古人の針の妙術を会得したわけではないが、現在の針の医術がつたないのを苦痛に感じ、ここに数十年間に経験してきたことを収録し、同志の者に示す。広く病人を救う手助けとなることを願うのみである。
2.針を腹部に刺す際の経絡の関係を論ずる
①針術が効果ある種々の疾患は、すべて肝の臓に関係することを知らねばならない。肝は筋を主どるからである。経絡は肉にあり、肉絡の集まるところは筋である。もし肝の臓が鬱滞し、あるいは心腎肝脾の四臓と調和しないときは、これらが主どる筋絡もまた鬱滞するから、肝はますます鬱滞して諸病を発症する。
②肝を池に例えると、筋絡は水路に例えられる。
雨が降って水があふれるような時、その池の水門が塞がっていたり、水路がつまっていたならば、池の土手は崩れ、また水路は壊れ、田園にまで被害がおよぶ。池の水はあふれ、水田が損害をうけるような頃に、池底をさらったり水門を開いたりしても事態は解決できない。
③肝の臓が鬱滞して、諸病が発症する時に際しては、腹部に針を刺すことに何の利点があろうか。ゆえに私の針術は、肝をはじめ他臓の部位に刺針せず、もっぱら経絡を刺すことにしている。水門を開き、水路に水を通せるようにしておけば、たとえ大雨が降って池が満水になっても、被害が及ぶことはないのである。
心腎肺脾の不和であれば肝が鬱滞し、種々の病が発症するといえども、その経絡に針を刺すならば、よく病苦を除く。これが私が数十年前から心がけていることである。
初学の針(略):刺針の練習台として、ぬか枕を用意するという内容。本書では刺針に際して管針を使わず、捻挫針で刺入練習をしている。
3.針術の要点
①私の針術は、直刺を好まず横刺をしている。なぜなら直刺は、針の根本まで肉中に入る場合でも、病経を通過するのは一~二分に過ぎない。これをもって効を得ることは少ない。横刺する時は、針先から針の根本まで、ことごとく病経に当たる。ゆえに直刺と比べれば、その効果は十倍となるからである。
※柳谷素霊は、その刺針のやり方は、押手の母指頭・示指頭で皮膚を撮み圧して、 針尖を指頭間に置き刺入する方法であり、この刺法は「霊枢官鍼篇」にあると記している。
②針を刺す時、深く肉中に入れたり、骨にあたる手応えを手に感じる時は、素早く抜き、改めて刺針し直すとよい。骨にあたれば針先は曲がり、あるいは折れることもある。
深く刺入する時は、禁針穴を貫いたり、心・肺・大動静脈に刺さることがあるからである。
首・肩・背中の第2~第5胸椎あたりでは、特に用心して直刺してはならない。誤って直刺したりすれば、その害は計り知れない。
また喉の下、胸骨の上際の陥凹しているところは、左右二寸ばかり間隙があり、慎重に針先が骨に触れないようにすべきである。この図も後に示す。
③下腹の丹田(=気海)を押按する際、はなはだ柔かく、押按すると溝のようになったり凹んだりする者には、針を施術してはならない。たとえ針しても治効を得ることはできない。
下腹を押按する際、皮膚表面が緊張してつっぱっていて、少し力を入れて按圧する時、腹底に力のない患者の多くは、心窩部や背部二行線がことごとくつっぱり、あるいは下痢している者である。このような者に針しても、治効は得難い。
④書物に掲げられた病のみ針術を行い、それ以外の病症には針してはならない、ということではない。この中のいくつかの病気に対しては針術は効果を得やすく、初学の者であっても患者を導きやすいからである。
針を刺して後、発熱・頭痛・上衝・目眩・嘔吐・食欲不振などの症状が出て、その病が一段と重く見えるみえることがある。これは針術の効果がある予兆であるから決して驚いてはならない。
⑤針術を施すには、まず布団を敷き、患者を側臥させ、足腰あたりに布団をかけ、風邪をひかせぬように注意すること。針術を終えた後といっても、たいてい半時(現在の約一時間)ばかりは静かに横臥させておくこと。
⑥すべて諸病の初発は軽症であるから、一日~二日または七~八日針して治す、とはいえ重症だったり半年や一二年の長い病期を経過した者は、たいてい五~六十日あるいは半年ばかりは治療すべきである。
慢性病や重病の者は、数十日あるいは数ヶ月間針すべき病状の場合、初回治療ではたいてい二十~三十ヶ所に刺針し、次の日から次第に多く刺し、百刺あるいは百四~五十ヶ所刺すこともある。
⑦すべての針術を施す際には、軽症重症に拘らず、遠くに出かけることや力仕事を禁ずる。
もしも遠くへ出歩いたり力仕事をしたりすれば、その病は元の状態に戻ってしまう。また足腰など下部の病では、下駄を履くのを禁ずること。
⑧針術を施すにおいて、患者は針の痛みに耐えかねることがある。これは呼吸閉塞の者または表熱のためにそうなっている者である。表熱のある者に針を刺す際、ところどころ刺痛を感ずる穴がある、これはその部に肺気が巡行していないので、皮膚が閉塞しているのが理由である、このような者は、指でこの辺りを揉んだりつかんだりして、運動させた後に刺すとよい。あるいはその痛む穴より5分ばかり傍に刺すとよい。
⑨表熱に対しては麻黄加柴胡あるいは小柴胡加麻黄葛根あるいは桂枝加葛根湯のような方剤を一~二日服用させて後に針をする。また常に呼吸閉塞の者は、この頃かかる症状や脉状を診察し、虚実を判定し、害がないようであれば麻黄湯・大青竜湯・葛根湯などを使って、後に針術を施すのがよい。
⑩十四経には数百数千の穴名があるり、それらの穴ごとに針の浅深・禁針などを説明している。それは直刺する場合の注意である。私の方法は横刺であるから、その見方とは別である。ただ十四経絡に従って針するのみである。
⑪刺した針が抜けにくい時は、その針の傍に別の針を一本刺せば、ただちに抜けやすくなるいものである。世にこれを迎え針という。
⑫針が筋中に折れ残った場合には、酸棗仁を一回煎服すれば抜け出ることもある。また筋肉中に消えてなくなることもある。またこの薬を服用しないで放置していたとしても、害となる者はいない。数日の後には小便となって出る者がいる。
医者になって間もなく、銀パイプの管を使って、尿閉を治療したことがある。誤って膀胱の出口あたりでカテーテルの先を切断してしまった。どうにもならず、クジラの長いペニスを膀胱内に送り進めると、その後に小便の出が良くなり、少しも害は起こらなかった。数年後であっても、患者はカテーテルの先端部は膀胱内に残留していることを気づかないと言った。その膀胱で消えてなくなるものだろうか? こうした経験から、銀パイプが膀胱内にあっても、害にはならないことを知るべきである。
⑬針術に補瀉の二つの方法がある。瀉針というのは針痕から病の気を漏らすようにする針のことをいう。補法というのは、血脈に穴を開けて、金気をつけて(?)体内に送り込むことである。ゆえに瀉針は、針を抜いた後に、その針痕を柔らかく揉み、あるいはさするのがよい。補の針は、針を抜いて直ちに指頭でその針痕に当て、気を漏らさないように、揉みつつ少し力を入れて押し込む。
ただし実際には補針の症状は非常に少なく、瀉針の症状ははるかに多い。補針を必要とする症状は、さまざまな病気のうち、温補剤を投与してから施術するのもよい。
⑭針を研ぐには、柔らかい砥石で針先を研ぎ、その後に厚い炭で針先を研ぐやり方がよい。
五臓六腑を略図し、肝経を示す:横刺の治療対象は主に筋であり、五行で筋は肝に属するから、肝の治療が重要だと記した。
古方、今方の漢方薬を説明し、対処法を示す(略)
4.腹痛の針
訳者註:示された診療法は、「肩こり」治療として記したものでないことに注意。横隔神経を介しての反射を利用したものだろう。座位で肩甲上部の僧帽筋をつまむよう引っ張り上げると、必ずゲップが出る患者がいたことを思い出した。
①触診法
心下臍上が痛む者では、布団に側臥させ、腰から下にも布団をかぶせ、医師はその後ろに坐る。右手または左手の母指・示指・中指・環指の四指で首の根もとから肩先まで指でつまむと、下図のように肩の前後で、筋(肩甲上部僧帽筋)の境目を感ずる。それを指頭でつまんで、ゴリゴリとする。この時、患者も痛みを覚える。
凝った筋は大きく太く痛みが強い。肩の経絡の触診だけそうするのではなく、十四経絡みな同じく、この要領にする。

②刺針法
この肩甲上部にある経は、手の太陽小腸経である。首の付け根近くで後の処から、グリグリと凝った筋にかけて、肩の前方へ突き通すくらいに針を刺す。僧帽筋の前縁に向けて、後方から4~5分ずつ間を隔てて横刺する。およそ四~五本ほど針するとよい。
さらに肩井穴あたりの外方から、耳前の方に向け、斜めに一本刺すようにする。この刺針効果は、前記の針の二~三針と同様の効果をもつ妙術である。

その後、患者を腹臥位に寝かせ、片方の肩の小腸経と背中の膀胱経の二経にも刺すようにするほか、他部位にも同じように刺す。背部膀胱経の2行線(督脈の外方3寸)上では、第3胸椎の高さに並ぶように取穴する。上から下に斜刺し、椎骨に向かって少し斜めに刺す。(訳者註:皮下組織と筋をつまみ上げた状態で、横刺するのであれば、捻針で刺入したのだろう。杉山和一創案の管針法は、この150年前に誕生しているのだが)
第九胸椎の高さまで、少なくとも六~七本の針を刺すのが普通である。さらにその経絡上で殿部筋上際まで三~四針ほど刺すとよい。次に腹臥位のまま、もう片方の肩および背中の二行の走行に刺す。この背中の二行は足の太陽膀胱経になる。
5.足の太陽膀胱経の反応と刺針
①背部二行三行の反応の診かた
足の太陽膀胱経で背部二行と三行に針をするには、まず患者を側臥位にせしめ、医師はその後に座る。下図のように五指で脊椎の両傍にある溝をつくる筋を、両肩の下から臀部の上際まで、つまみ上げて診察する。ゴリゴリとして指に感ずる大絡(経脈から出た支流)は、健常者でも同様の所見をみるも、病者の肉絡は太く大きく、痛みを感ずることは健常者よりも甚だしい。この所見があるものを病んでいる絡とし、病絡でないものとの違いを分別する。

※訳者註:四指でつまみあげた組織は、最長筋とみなすのではなく、皮下組織だろう。それが太く大きく感ずるのは、浅層ファッシアが癒着していることを示すものだろう

①背部二行のへの横刺
背部の二行線に針する際、臍から上が痛む病症には、第二第三胸椎の両傍から、それぞれ1寸五~六分ばかりのところから、下図のように上から下に向け、少し椎体の方に斜めに向け、そのゴリゴリとする肉絡に刺すのだが、あまり深刺しないようにして、第九胸椎の両傍あたりまで二行の線に沿って、通常は左右それぞれ五~六針する。
ただし病の軽重によって、左右それぞれ二三針から七八針まですることもある。
第二腰椎より下は、針の数を少なくし、病症によっては針をしなくてもよい。

背中の左右の二行線三行線上で第二腰椎あたりの針は、側臥位で針を少し斜めに深く刺す。
ゴリゴリとする凝った絡と病症の状態によっては、脊椎の際(=背部一行線)から下方へ向け、少しくぼんだ方へ斜めに刺すこともある。ただし、このような針をする病症はかなり稀である。
※訳者註:胸椎から第一腰椎にかけて、背部二行線(棘突起外方1.5寸)から多数針を横刺するのに対し、第二腰椎以下の背部二行線にあまり針をしないのは、反応が出にくいからだろう。すなわち脊髄神経後枝の撮痛反応点が現れにくい領域だからだろう。


6.上腹の痛み
(中略)、臍上・心下・あるいは胸中が痛む者に針を施す場合、任脈に沿う痛みだけを問題にせず、両肩や背中の背部二行線上の、第二第三胸椎あたりから、第九胸椎あたりまで刺す。また前述したように首の両傍、両耳の後ろの筋、あるいは頸項、あるいは上腕あるいは腋窩の前後の経絡などに凝絡ある時は、すべてこれを刺すべきである。
針は第十胸椎より下に刺し、臀部の上部まで刺すこともある。
○ 心の痛みと胃部痛に対する針と方剤
心痛、胃部痛の針術とは、腹痛の針のやり方に従い、第2腰椎の上を刺すべきである。
◯咽喉が腫れて痛む時の針と方剤
咽喉が痛む歳の針もまた心痛の針術と同様である。
7.下腹の痛み
臍下の下腹部が痛む者は、これも任脈だけを問題にせず、背中の背部二行、第二第三胸椎あたりから殿部上際まで刺すのがよい。
通常、腹痛の針は臍から上が痛む症状ならば、第二腰椎より上を多く刺し、臍から下が痛む症状なら、第二腰椎より下に繰り返し刺すのが普通である。それより三行線の章門から腰椎の上際まで刺すとよい。
8.腹の症状や腹のシコリに対する針
腹部の痙攣や硬結に対する針は、腹痛の針と同様である。
しかし臍のあたりで、石のように硬く可動性のないシコリでは、その腹の皮膚や表面の皮下脂肪はむしろ柔らかい。石のように固く塊の中には拍動があって(=腹部大動脈瘤?)、患者も非常に苦しむ。このような状況に対しては、背部の第二腰椎あたりで、その椎骨の際から、左右ともに脇腹の方に向け、針を少し斜めに向けて深く刺す。または左右の二行線においても、やはり針を深く刺すべきである。
そうとはいえ、この針は塊の状況により、斜刺あるいは直刺と適宜行う。また病症によっては三行から刺すこともある。私が針を深く刺すことは、この症にのみ限定して行っている。そしてこの針数は、病症に従い、適宜斟酌すべきである。その他の経絡に針することは、上記の通りである。
回虫による痛みと食中毒による痛みは、服薬で効果あるもので、針術の主治ではない。
針術秘要 中の巻 現代文訳
https://blog.goo.ne.jp/ango-shinkyu/e/3c8fcd917865f6c0e1957f83c629908b