◆7月10日
この引用ツイート【「教会の存続を“本気で”考えるなら、若者伝道や次世代への信仰継承ではなく、教会ごとの平均年齢以上(多くの場合、高齢者)の層を厚くすることに力を注ぐ方が良いですよ。60〜80代の人たちが中心に支えている共同体として維持していくべきです。今の状況をそのまま次世代の人たちに担わせるのは酷です。」というツイート】、ほんとそれよね、と思う。今の所属教会でゲンナリするのは、若い人が来たら、①小間使い②長老③伝道④教会学校など、全部その人に押っ付けようという魂胆が見え見えなこと。勿論、歳を取ると大変なんだな……というのは私も段々解ってきたが、それにしても大勢の年配教会員が寄ってたかって壮年層を褒めちぎりさえすればいいと思ってるようにしか見えないのにはウンザリ。5年ほど前、都心から引越してきた夫婦が新来会された時、確か「分区聖日」の講壇交換で隣の市の教会の牧師がお越しになっていて、礼拝後にその先生がご主人の方に「ウチの教会の(何かの)建築工事を手伝って下さい」みたいなことを頼んでて、傍で見ていた私は(新来会者にいきなりそんなこと頼む?労働力が不足してるのは分かるけど)と唖然。某年配教会員も私のところにやって来て、何とかそのご夫婦と関係作りをして、ウチの教会に居続けてもらえるよう便宜図ってくれ、みたいに懇願してきた。私は人付き合いが苦手だし、結婚したいと思う方の心中は察しかねるような変人なので、正直閉口した。結局そのご夫妻は少し離れた所の若い人・趣味の合う人がいる教会の所属になったようだ。何か教会員を見てると「伝道」の名目のためなら(あるいは自教会の存続のためなら)何をしてもいい(来会者の人権を蹂躙してもいい)とでも思ってるようにしか見えない。コリントの信徒への手紙 一 13章5節に「(愛は)…自分の利益を求めず、…」ってあるのにねぇ。
↓ ↓ ↓
<新改訳第三版 ガラテヤ人への手紙6章2節>
互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
* * *
<新改訳第三版 ガラテヤ人への手紙6章5節>
人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。
…という御言葉もあるのに。少しは若い人の困りごとも聞いてあげたの?って思っちゃう。
◆7月29日
<新共同訳 ルカによる福音書7章2〜10節>
ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が、病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。「あの方は、そうしていただくのにふさわしい人です。わたしたちユダヤ人を愛して、自ら会堂を建ててくれたのです。」そこで、イエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬ所まで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。「主よ、御足労には及びません。わたしはあなたを自分の屋根の下にお迎えできるような者ではありません。ですから、わたしの方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。ひと言おっしゃってください。そして、わたしの僕をいやしてください。わたしも権威の下に置かれている者ですが、わたしの下には兵隊がおり、一人に『行け』と言えば行きますし、他の一人に『来い』と言えば来ます。また部下に『これをしろ』と言えば、そのとおりにします。」イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。「言っておくが、イスラエルの中でさえ、わたしはこれほどの信仰を見たことがない。」使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。
↓ ↓ ↓
秒で人を癒せる主なら、最初から百人隊長の家まで出かけようとせず、〈遠隔癒し〉をすることもできたのだろう(実際、後でしている)。でも、イエスは身体をもって生きられたし、そのことを大事にしてもいたのだろう。イエスがバシバシ奇跡をしてたら、私達はただ物乞いのようにイエスに縋るだけで、自分で何もする術がなく、自堕落に過ごすしかできなかった。病人が助けを必要としているという知らせを受け、出かけていく。物理的に時間も労力もかかる。効率的ではない。でも、イエスは肉体をもって生きる私達の手本となるために、超人としての生き方を通されなかったのだと思う。この時間的・空間的制約の中で、どう行動するかを考えて動くこと。
* * *
ヨハネによる福音書11章のラザロが復活させられる話で、ラザロの病気の報を受けたイエスは即座にラザロのもとに駆けつけることができなかった(6節)。理由は明示されていないが、複数の事由があったのではと思う。ラザロの姉マリアも、すぐにおいでにならなかったイエスを詰る口調だった(32節)。「イエスは、彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して」(33節)、「イエスは涙を流された」(35節)。それを見て、イエスの心根の深さに動かされる者もいれば(36節)、「盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか」(37節)とあげつらう者も。高みの見物でなく、人間として世の中の一隅に身を置き、動揺して憤りを覚え、涙を流されるイエス。イエスが人々の感情の渦に呑み込まれつつ、人を癒すわざを行なって下さったからこそ、私達にも人間として生きながらも御心を尋ねて生きる道がひらかれているのだと思う。
この引用ツイート【「教会の存続を“本気で”考えるなら、若者伝道や次世代への信仰継承ではなく、教会ごとの平均年齢以上(多くの場合、高齢者)の層を厚くすることに力を注ぐ方が良いですよ。60〜80代の人たちが中心に支えている共同体として維持していくべきです。今の状況をそのまま次世代の人たちに担わせるのは酷です。」というツイート】、ほんとそれよね、と思う。今の所属教会でゲンナリするのは、若い人が来たら、①小間使い②長老③伝道④教会学校など、全部その人に押っ付けようという魂胆が見え見えなこと。勿論、歳を取ると大変なんだな……というのは私も段々解ってきたが、それにしても大勢の年配教会員が寄ってたかって壮年層を褒めちぎりさえすればいいと思ってるようにしか見えないのにはウンザリ。5年ほど前、都心から引越してきた夫婦が新来会された時、確か「分区聖日」の講壇交換で隣の市の教会の牧師がお越しになっていて、礼拝後にその先生がご主人の方に「ウチの教会の(何かの)建築工事を手伝って下さい」みたいなことを頼んでて、傍で見ていた私は(新来会者にいきなりそんなこと頼む?労働力が不足してるのは分かるけど)と唖然。某年配教会員も私のところにやって来て、何とかそのご夫婦と関係作りをして、ウチの教会に居続けてもらえるよう便宜図ってくれ、みたいに懇願してきた。私は人付き合いが苦手だし、結婚したいと思う方の心中は察しかねるような変人なので、正直閉口した。結局そのご夫妻は少し離れた所の若い人・趣味の合う人がいる教会の所属になったようだ。何か教会員を見てると「伝道」の名目のためなら(あるいは自教会の存続のためなら)何をしてもいい(来会者の人権を蹂躙してもいい)とでも思ってるようにしか見えない。コリントの信徒への手紙 一 13章5節に「(愛は)…自分の利益を求めず、…」ってあるのにねぇ。
↓ ↓ ↓
<新改訳第三版 ガラテヤ人への手紙6章2節>
互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
* * *
<新改訳第三版 ガラテヤ人への手紙6章5節>
人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。
…という御言葉もあるのに。少しは若い人の困りごとも聞いてあげたの?って思っちゃう。
◆7月29日
<新共同訳 ルカによる福音書7章2〜10節>
ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が、病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。「あの方は、そうしていただくのにふさわしい人です。わたしたちユダヤ人を愛して、自ら会堂を建ててくれたのです。」そこで、イエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬ所まで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。「主よ、御足労には及びません。わたしはあなたを自分の屋根の下にお迎えできるような者ではありません。ですから、わたしの方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。ひと言おっしゃってください。そして、わたしの僕をいやしてください。わたしも権威の下に置かれている者ですが、わたしの下には兵隊がおり、一人に『行け』と言えば行きますし、他の一人に『来い』と言えば来ます。また部下に『これをしろ』と言えば、そのとおりにします。」イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。「言っておくが、イスラエルの中でさえ、わたしはこれほどの信仰を見たことがない。」使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。
↓ ↓ ↓
秒で人を癒せる主なら、最初から百人隊長の家まで出かけようとせず、〈遠隔癒し〉をすることもできたのだろう(実際、後でしている)。でも、イエスは身体をもって生きられたし、そのことを大事にしてもいたのだろう。イエスがバシバシ奇跡をしてたら、私達はただ物乞いのようにイエスに縋るだけで、自分で何もする術がなく、自堕落に過ごすしかできなかった。病人が助けを必要としているという知らせを受け、出かけていく。物理的に時間も労力もかかる。効率的ではない。でも、イエスは肉体をもって生きる私達の手本となるために、超人としての生き方を通されなかったのだと思う。この時間的・空間的制約の中で、どう行動するかを考えて動くこと。
* * *
ヨハネによる福音書11章のラザロが復活させられる話で、ラザロの病気の報を受けたイエスは即座にラザロのもとに駆けつけることができなかった(6節)。理由は明示されていないが、複数の事由があったのではと思う。ラザロの姉マリアも、すぐにおいでにならなかったイエスを詰る口調だった(32節)。「イエスは、彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して」(33節)、「イエスは涙を流された」(35節)。それを見て、イエスの心根の深さに動かされる者もいれば(36節)、「盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか」(37節)とあげつらう者も。高みの見物でなく、人間として世の中の一隅に身を置き、動揺して憤りを覚え、涙を流されるイエス。イエスが人々の感情の渦に呑み込まれつつ、人を癒すわざを行なって下さったからこそ、私達にも人間として生きながらも御心を尋ねて生きる道がひらかれているのだと思う。











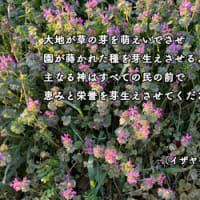















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます