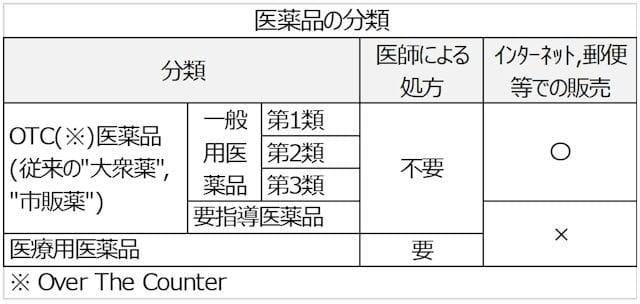紙の健康保険証の新たな発行は2024年12月1日を以って終了となり、2024年12月2日からはマイナンバーカードに健康保険証を利用登録した形の「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行するということです。
マイナ保険証は、その利用の本格運用が2021年10月に始まっていますが、2024年12月2日時点で手許に「マイナ保険証」が用意できていない場合、以下のような導入移行措置が考慮されており、それにより診療を受けることが可能となっています。
・手許にある健康保険証は、2024年12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間(~2025年12月1日)利用できる。
・2024年12月2日以降、マイナンバーカードが手許にない人には「資格確認書※」なるものが交付され、それの提示で診療は受けられる。
※ ここには、本人の被保険者資格等の情報が記載されている。
マイナ保険証の利用案内のサイト(厚労省)は以下です。ここでは、利用上のメリット、マイナカードへの保険証の利用登録方法、電子処方箋などが案内されています。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/#:~:text=マイナンバーカードをなくしたり,受けることができます。
12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等に関するセミナーの動画サイト(厚労省)は、https://www.youtube.com/watch?v=CZLZBks1v8Eです。