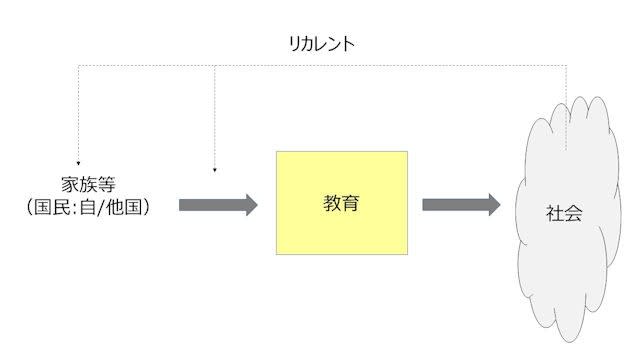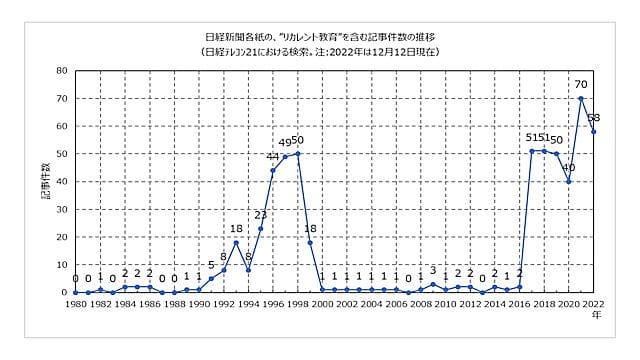紙の教科書の内容全体が、例えばPDFファイルのように、そのままデジタル化(電子化)されたものを指しています。正式には、"学習者用デジタル教科書"と呼ばれます。ノートPCやタブレット等の学習者用端末に表示して見ることができます。
動画や音声、アニメーションなどのコンテンツは、デジタル教科書には含まれず、それと組み合わせて利用することで学習の充実が図れる「補助教材」とされています。
デジタル教科書を導入した時の、紙の教科書にない利点としては、基本的に以下の2点が考えられています。
(1)拡大縮小、ハイライト、音声読み上げ、検索などのデジタル特有の機能が活用でき、教育活動の充実が図れること、および
(2)動画や音声、アニメーションなどのデジタル補助教材と組み合わせることが可能なこと
その他、視覚聴覚障害を持った児童生徒や発達障害のある児童生徒に対する特別支援としての活用も期待されています。
文科省は、これまで、デジタル教科書を「紙の教科書」の代替教材と位置付けていたようですが、学校現場に浸透していない現状に鑑み、デジタル教科書を「正式な教科書」と位置付けた上で、2024年9月には、その使用拡大に向けた議論を開始したようです。
そして、2025年1月21日には、中央教育審議会のデジタル教科書推進ワーキンググループ(作業部会)において、デジタル教科書を「正式な教科書」として位置づけることを盛り込んだ以下のような論点案が文科省より提示されたようです。即ち、
・デジタル教科書の位置づけを代替教材から「正式な教材」へ変更すること
・紙の教科書かデジタル教科書かを各教育委員会で選択すること
・紙とデジタルを合わせた「ハイブリッド」な形態の教科書を認めること
・教科書と教材の線引きを明確にすること
これを受け、今後は、2030年度予定の新しい教科書の使用開始に向け、以下のようなスケジュールで取り組みを進めていくようです。
2025年2月:上記作業部会で中間とりまとめを行う。
2025~26年度:文科省で教科書制度を改正する。
2029年度:各教育委員会で教科書を選択
2030年度:新しい教科書の使用開始
論点案の資料(2025.1.21付け、文科省)は、https://www.mext.go.jp/content/20250121-mxt_kyokasyo01-000039635_1.pdf です。
参考サイト:3.学習者用デジタル教科書について(文部科学省)、https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/04060901/1349317.htm