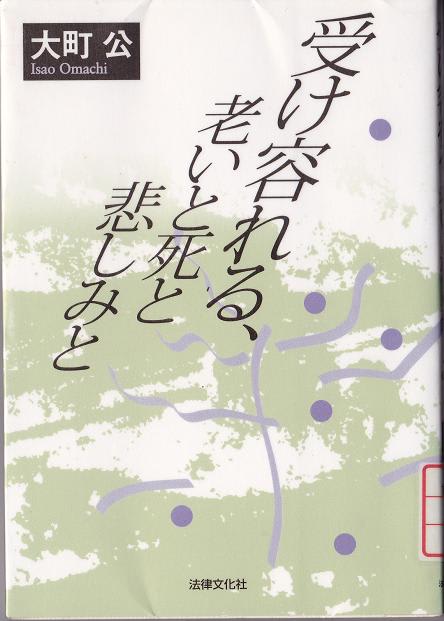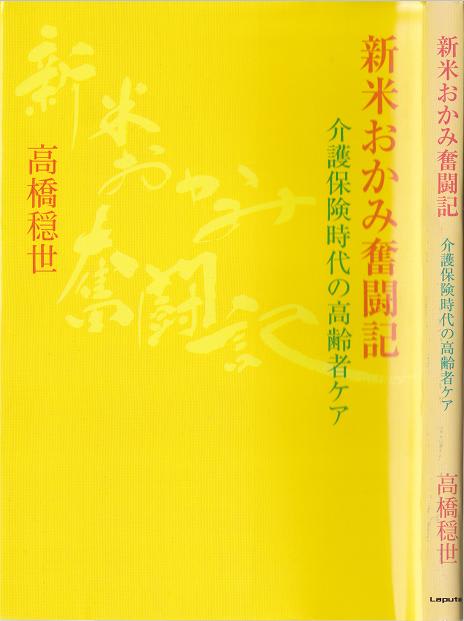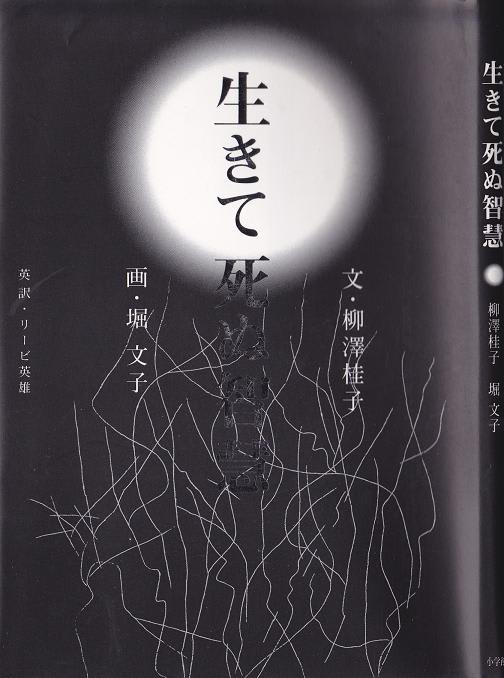まず驚くのがp.54の家族介護の「神話」というところ。
>これまで「介護は女がするもの、介護は家族の仕事、昔は日本では
>家族がお年寄りを手厚くお世話したものだ」と思われてきた。
そう書かれていた。それは「<かいご>の<ごかい>」であるとバッサリ斬り捨てている。何故なら、高度経済成長前の昭和30年代、高齢者は重い病気になっても、都市部でさえ、入院することはほとんどなかったからだ。
>「多くの高齢者は数日から数週間自宅で床についてなくなった。」としている。
そう、平均寿命が大幅に延びてしまったがために、寝たきりの問題が発生し、長期にわたる介護が必要となった。これには驚いたというより、驚愕である。
次に驚いたのが、p.80からの「断食死」について。平安時代末期から中世期にかけて編集された修行僧の電気、「往生集」や「高僧伝」を見ると、いよいよ最後の命終の時期が近づくと、彼らの多くが断食に入っていくそうだ。五穀を断ち、十穀を断ち、やがて、木の実や葉も断って、枯れ木のようになっていくそうだ。
この本では、西行も、願い通りの時期に死を迎えているので、自発的に断食死であったろうとしている。
以前から、古典を紐解くと、高僧が予言した通りの時期に死を迎えていることに疑問を持っていたが、なるほど、自発的に絶食して絶命しているのなら、納得が行く。
最後に、この「断食死」を『お迎えのとき-日本人の死生観-』の第1章で書かれたのが山折哲雄先生である。また、p.186にはシスター鈴木(秀子)先生の名前もあがっている。徐々に、知らなければならない先生方の名前が繋がってきた。このタイミングが一番、学習が面白い時期なのかもしれない。