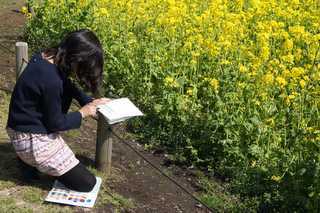駅からの散歩
No.342 東船橋~船橋 6月17日
船橋は人口60万人で県で千葉市に次ぐ大都市である。しかし船橋と聞いてもどんな街なのかイメージが湧かない。それは東京湾に面しての漁業があり、東京に近いことから首都圏のベットタウンであり、北部は梨やニンジンの農家と、さまざまな業態が入り混じっているからだろうか。今日はそんな船橋の南部の海岸沿いを歩いてみた。船橋の歴史は古く、日本武尊が東国平定の成就を祈願して創建したと言われる船橋大神宮が1900年前の創建と書かれてあった。古くからの町だからのだろう、神社仏閣が多く、中心部は細く曲がりくねった道が入り組み、新旧の家が混在していて、雑然としてまとまりのない街のように感じてしまう。

JR総武線 東船橋駅

道祖神
道祖神社の祠を覆う大イチョウは昔からの道標になっていたようだ。

了源寺

了源寺

西福寺
四国四十八箇所霊場より御霊験石を拝領して鉄柱の上に置いてある。この石をさわり
「南無大師遍照金剛」と唱えて回れば四国八十八箇所を回ったのと同じ功徳があるらしい。

船橋大神宮

船橋大神宮
景行天皇40年(110年)に日本武尊が東国を平定の成就を祈願して創建したと云う古社

境内は苔むしていて歴史を感じる


浜町橋



鵜

海老川水門

海老川水門




船橋沿岸はゼロメートル地帯が広がり、わずかな高潮でも浸水被害が
出てしまうため、船橋港付近はぐるりと堤防に囲まれている。

旧運河沿いの道 廃屋が多く立ち並んでいる

廃屋の後方には真新しい高層マンションが立つ

古い町並みの本町


西向き地蔵

いくつもの寺が建つ寺町

行法寺

新しい感覚のお寺

ときわ湯 昨年9月に閉店


海老川

海老川橋
橋から突き出た廻船のモニュメント、ここは船橋という地名の発祥の地
川に小舟を並べて橋の代わりをしたという逸話から、船橋の地名の由来になった。

御蔵稲荷神社

東照宮(左)と御殿稲荷神社(右)
ここは家康が秀忠と佐倉方面に狩に出かけたときに宿泊した船橋御殿があった場所
各地に東照宮はあるが、ここの社殿は小さく質素である。

このあたりは車も入れないくらい道は細く入り組んでいる。

御殿通り

船橋駅
No.342 東船橋~船橋 6月17日
船橋は人口60万人で県で千葉市に次ぐ大都市である。しかし船橋と聞いてもどんな街なのかイメージが湧かない。それは東京湾に面しての漁業があり、東京に近いことから首都圏のベットタウンであり、北部は梨やニンジンの農家と、さまざまな業態が入り混じっているからだろうか。今日はそんな船橋の南部の海岸沿いを歩いてみた。船橋の歴史は古く、日本武尊が東国平定の成就を祈願して創建したと言われる船橋大神宮が1900年前の創建と書かれてあった。古くからの町だからのだろう、神社仏閣が多く、中心部は細く曲がりくねった道が入り組み、新旧の家が混在していて、雑然としてまとまりのない街のように感じてしまう。

JR総武線 東船橋駅

道祖神
道祖神社の祠を覆う大イチョウは昔からの道標になっていたようだ。

了源寺

了源寺

西福寺
四国四十八箇所霊場より御霊験石を拝領して鉄柱の上に置いてある。この石をさわり
「南無大師遍照金剛」と唱えて回れば四国八十八箇所を回ったのと同じ功徳があるらしい。

船橋大神宮

船橋大神宮
景行天皇40年(110年)に日本武尊が東国を平定の成就を祈願して創建したと云う古社

境内は苔むしていて歴史を感じる


浜町橋



鵜

海老川水門

海老川水門




船橋沿岸はゼロメートル地帯が広がり、わずかな高潮でも浸水被害が
出てしまうため、船橋港付近はぐるりと堤防に囲まれている。

旧運河沿いの道 廃屋が多く立ち並んでいる

廃屋の後方には真新しい高層マンションが立つ

古い町並みの本町


西向き地蔵

いくつもの寺が建つ寺町

行法寺

新しい感覚のお寺

ときわ湯 昨年9月に閉店


海老川

海老川橋
橋から突き出た廻船のモニュメント、ここは船橋という地名の発祥の地
川に小舟を並べて橋の代わりをしたという逸話から、船橋の地名の由来になった。

御蔵稲荷神社

東照宮(左)と御殿稲荷神社(右)
ここは家康が秀忠と佐倉方面に狩に出かけたときに宿泊した船橋御殿があった場所
各地に東照宮はあるが、ここの社殿は小さく質素である。

このあたりは車も入れないくらい道は細く入り組んでいる。

御殿通り

船橋駅