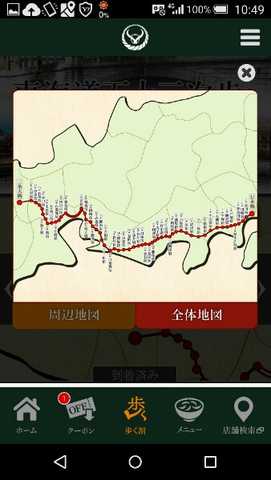通勤途中、いつも本を一冊持っていないと手持ち無沙汰である。だから一冊読み終えれば、直ぐに本屋へ行くことになる。最近は小説をあまり読まないから、どちらかといえば生活に密着した新書が多くなる。今回は薬に関してのもの。《その一錠が脳をダメにする》著者宇田川久美子、タイトルはセンセーショナルであるが、めくり読みすると共感できることもある。早速読んでみることにした。
著者は薬剤師である。その著者が自分の経験からこんなことを書いている。
若かりし日の私も、頭痛薬を手放せませんでした。薬の量も1錠から2錠、3錠と増え薬学部の友人から心配されたほどです。それでも私は飲み続けました。痛みを抑えなければ勉強することもリラックスした時間を楽しむことも出来なかったからです。そして薬剤師になると、様々な薬に囲まれて働くようになります。そんな薬に恵まれた環境は、薬への依存をいっそう高めさせました。
薬の知識があるだけに、痛みを消すにはどんな薬がよいのか分かります。つらい痛みを薬で抑え込み、それがうまくいかなければ薬の量を増やしたり、より作用の強い薬を飲んだりする。そんな薬漬けの生活が30年近くも続きました。頭痛薬、ビタミン剤、胃腸薬、筋弛緩剤・・・・7種もの薬を毎日17錠も飲んでいたことがあります。しかしどれほど薬を飲んでも、痛みから解放されることはない。痛み止めに含まれる鎮痛成分には、痛みを軽くする作用があるだけで、痛みのもとを除く働きはありません。それだけではなく、常用していると、頭痛の起こる頻度は増え、痛みは強くなっていく。頭痛を取るために薬を飲み、一時的に痛みを抑えたところで、再び強い痛みがやってくるのだとしたら、何のための薬かわかりません。悪循環にはまり込むだけです。薬を大量に飲み続けてきた私は、薬と決別する覚悟を決めました。
著者は医療のあり方を視点を変えて見ることで、今の薬の扱われ方を警告し、健全な薬のあり方について書いている。以下ポイントになる所だけを抜粋してみた。
・・・・・・・・・・・・
実は、薬とは「病気を治す」ものではありません。ほとんどの薬は、心身に生じる症状を抑えるためのものです。本当の意味での健康な心身を築くには、まずは薬に対する認識を改め、できる限り薬に頼らずにすむ身体づくりを始める事です。
薬剤師は薬学部に入学した時から薬の勉強を続けることになりますが、真っ先に教わるのは「薬は身体にとって異物であり、毒である」と言うことです。異物が身体に起こす反応の力を借りて、不快な症状を感じにくくしたり、症状を抑え込んだり、病原菌の力を削いだりするのが薬です。つまり薬とは、病気の力を抑えて、自然治癒力が働きやすくなるようサポートするのが本来の目的。そのために薬は存在するのです。つまり、病気を治す主体はあくまでも身体に備わった自然治癒力。薬はそれを支えるもの。ところが多くの人は、「薬が病気を治す」と勘違いしています。
「くしゃみ3回○○3錠」「効いたよね、早めの○○○○」などといったキャッチフレーズは、症状の出始めに薬を飲んでおけば、翌朝にはスッキリ爽快、風邪を吹き飛ばせることを視聴者に連想させます。しかしCMはイメージを植えつけるためのの映像で、どこにも「風邪が治る」とは言っていません。薬に風邪を治す力がないことを知っている人達が、ウソを語らずに薬の力を信じさせるためにつくった巧妙なしかけです。
風邪薬の多くは、回復に向けて欠かせない免疫反応を抑え込んでしまうものです。これによって、つらく不快な症状が一時的に軽減されます。本人は「風邪がよくなった」と思うかも知れません。しかしウイルスは体内でくすぶり続けます。風邪薬に頼っている人ほど、症状がすっきりとれにくいのはこうした理由があるからです。
しかし、抗生物質だけは少し話が異なります。抗生物質は20世紀最大の発見と呼ばれた名薬です。「神の薬」「救世主」とたたえられたほど、世界中で多くの命を救ってきました。世界最初の抗生物質はペニシリン、その後、数々の抗生物質が製造され、細菌による感染症の治癒に絶大な力を発揮しました。ところが人類は、残念なことにこの大切な薬の使い方を誤りました。効力の高さゆえ、乱用するようになったのです。抗生物質は、細菌による感染症を抑えるうえですばらしい威力を発揮します。ただし効くのは細菌感染においてのみです。風邪も感染症の一種ですが、原因のほとんどがウイルス。ウイルス感染において抗生物質は無力です。ところが、先進諸国では、抗生物質の威力を過信し、風邪にも抗生物質を処方する時代を長く続けてしまったのです。その結果抗生物質の効かない耐性菌の出現です。
欧米では、一度の受診で処方されるのは1剤のみの「1剤処方」が基本です。ひるがえって日本では、5剤以上の処方も珍しくありません。名著「ドクターズルール425 医者の心得集」には、「4剤以上飲まされている患者は、医者の知識が及ばない危険な状態にある」「薬の数が増えれば増えるほど、副作用のリスクは加速度的に増す」という提言が記載されています。薬の乱用は、人の健康を脅かし、国全体を不幸な状態に導く大問題であると、先ずは知って欲しいと願います。
効き目のよい薬や即効性の高い薬ほど、身体のどこかで副作用が生じています。なぜなら飲み下された薬は腸から吸収されると、血流にのって体中をまんべんなくめぐっていくからです。当然のことながら、薬には意思はありません。薬を必要としている個所にピンポイントで届くわけではなく、随所で作用を及ぼします。例えば咳止めを飲めば、のど粘膜の炎症を柔らげるだけではなく、脳や胃腸などの内臓諸器官から手足などの末端にいたる粘膜に、作用が働くことになるのです。
薬の作用には、必ずプラス(効果)とマイナス(毒性)があります。患部に働きかけるプラスの作用を主作用といい、意図した作用以外のマイナスの作用を副作用といいます。副作用には眠くなる、蕁麻疹がでるなど自覚できるものもあれば、自覚はないけれど体内でなんらかの作用をもたらしていることもあります。プラスとマイナスはワンセットであり、薬の効果を感じれば、身体のどこかで副作用も起こっています。軽い気持ちで飲んだ一錠が、思わぬ結果をまねくこともあります。
「薬は命と健康を守ってくれるもの」と思い込んできた方には衝撃かもしれませんが、医師がつくる多くの学会は、製薬会社と表裏一体の関係にあるのです。メディアが報道する情報も、資金の豊富な製薬会社や影響力の大きな広告代理店が背景に絡んでいれば、鵜呑みにできないものとなります。近年の健康ブームにのり、テレビでは毎日のように健康情報が流されます。名医と呼ばれる医師たちが登場し、視聴者の不安をあおる形で病気を説明します。テレビ局は製薬会社をスポンサーとし、名医と呼ばれる医者は「早期発見、早期治療」を呼びかけて大勢の人を病院に集め、製薬会社は医師達に薬を売ってもらう、・・・・。テレビの健康番組には、こうした連携が見え隠れしています。
たとえば高血圧の降圧剤治療、「130超えたら血圧高め」とイメージ宣伝が効いているのか、医者は過剰に降圧剤治療を進めます。現在、降圧剤ビジネスの市場は1兆円規模になっています。日本では約4000万人が高血圧症と推定されており、3000万人以上が降圧剤を毎日服用しています。具体的には、50歳以上の約4割近くが降圧剤の常用者です。これは異常な状況です。降圧剤は血管を拡張して血圧を抑える作用はありますが、血管壁をピチピチに若返らせる働きはありません。血管を拡張するので一度飲み始めると「一生のおつきあい」というのが医者の常套句になります。大勢の患者さんが降圧剤を飲んでくれていれば、医療も製薬会社も安泰です。
ではどうすればよいか。そのために重要なのは、「身体の声を聞く」ことです。痛みやだるさ、疲れなどの不快感は、身体から送られてくるSOSのサインです。サインを受け取ったら、薬で症状を抑える前に、身体のためにできることを実践してあげて下さい。たとえばひたすら眠る。食欲がないときは食事をする必要はありません。発熱時、味がしない、何を食べても苦く感じるというのは、身体が「食べないで」とサインを送っている証です。私たちの身体は2~3日は食べなくても大丈夫です。脱水症状を起こさないよう、こまめに水分補給をし、身体の声に従って休んでいれば、風邪は治っていきます。風邪をひいたら薬に頼らず、自らの免疫力だけで治すという体験を積んで見ましょう。成功体験が、薬を遠ざける第一歩となるはずです。
・・・・・・・・・・・
糖尿病にしても高血圧症にしても高脂血症や脳卒中、心臓病、はたまたガンまで生活習慣病といわれている。本来なら生活習慣を改めれば病気になりにくいし、改善できるはずである。しかし、多忙な生活に追われていると、どうしても薬に頼りがちになる。しかしこれでは根本的な解決にはならないばかりか、身体を痛めることになる。著者が言うようにまずは身体の声を聞く、そしてそれが風邪など、今までの経験の範囲であれば自己免疫で自力で治す。症状が重いものだったり今まで経験したことのない異変であれば、医者に行って検査を受ける。それでもだだ医者の処方を鵜のみにするのではなく、自分でも調べ対応を考えてみる。自分の身体だから、医者任せにせず自分が把握し管理する。そんなスタンスが必要なように思うのである。