金融法務事情No.1909の「特集:会社法制の見直しとコーポレート・ガバナンス」にある神田先生の「上場会社に関する会社法制の将来」という記事(講演録のまとめ)は今までの議論の経過をわかりやすく整理していて参考になります。
参考になるだけでなく、「コーポレート・ガバナンス」論議に関する私の持っている違和感の原因もおぼろげながらわかってきた感じがしました。
神田先生の記事では、まず
要するに、コーポレート・ガバナンスとは、上場会社等において、経営を牽制するような仕組みを会社がどのように作り上げるかという問いです。
と定義しています。
当たり前のようでけっこうこれが大事で、「内部統制」などとごっちゃになると議論のポイントがずれることが(特に素人同士や、素人を安易に折伏してしまおうという専門家においては)しばしばあるので要注意です。
話を元に戻すと、
このコーポレート・ガバナンスの概念は、従来は「不祥事の再発防止」だけを議論していたものが、1999年のOECDの「コーポレート・ガバナンスに関する諸原則」制定などを契機に、不祥事防止とともに、企業が業績を上げるためにどのような意思決定の仕組みを設けたらいいか、という「車の両輪論」がグローバルな「標準的な議論」となってきた。日本でも会社法制においては委員会(等)設置会社制度が導入された。
一方で昨年来のコーポレート・ガバナンスをめぐる「現在の議論」はそれとは別のグローバルな状況との「格差」に対応することを主眼としている。
これはプレゼンスを増してきた外国人投資家などからの指摘を受けたもので、この文脈で不透明な第三者割当増資の是正や独立役員制度が議論されることになってきた。
そこで、東証の規則で設置が求められるようになった独立役員をさらに会社法制で制度化しようとして、各所でレポートが出されたり、法制審議会などで社外取締役、社外監査役その他もろもろの制度が議論になっている。
というのが今の状況だと説明されています。
法制審議会の議論についてはbizlaw_styleさんが軽妙な解説とともに紹介しているのでもっぱらそれを参考にさせていただいくと、上の「車の両輪」特に前向きな効果の方についての議論はほとんどなく、経営者に対する監視機能や、欧米(欧と米でも違うようですが)との違いをどう埋めるか、そこついて現行法と整合性をどうとるかの議論が中心になっています。
なるほど、いままでのコーポレート・ガバナンス論議への違和感の根源は、神田先生曰くの「標準的な議論」と「現在の議論」のギャップにあったということが腑に落ちました。
平たく言えば、その改正の方向が会社の健全な成長に結びつくのか、そもそも何で今その議論をする必要があるのか(外国人投資家が投資判断をしにくい、という理由が法制度を変える理由になるのか)という疑問ですね。
そもそも企業不祥事についても、既存の会社法に加え、粉飾決算とか怪しい増資についていえば、J-Soxを含む金融商品取引法で対応しているわけです。
このうえに独立役員を増やせば不祥事がさらに減るとか、企業業績が向上するというものでもないように思います。
また、そもそもコーポレート・ガバナンスの改革云々の前に、既に日本企業は、外国人をはじめとする投資家、株主重視に舵をきっているように思います。
2002年から2007年のいわゆるいざなみ景気は好調な輸出に牽引され企業業績も過去最高益を記録する企業が続出した一方で、従業員の給料や正規雇用はいざなみ景気の間ほとんど増えませんでした。
とこどがリーマンショックが起きるや否や企業は即座に従業員のリストラに走り、その結果、早速今期の業績見込みを上方修正する企業も出てくるという状態です。
法制審議会で経団連の八丁地委員は繰り返し「立法事実がない」と言っているようですが、「企業は今のままで十分ちゃんとやってるじゃないかよ」とういうことなんだと思います。
またぶっちゃけて言えば、企業自身にプラスになると思われないような形で独立役員制度を無理やり導入しても、結局企業は新しい「お客様」の処遇の仕方を考え出すだけで実効性は伴わないと思います。
たとえば社内役員に対する監視機能だけについていっても、結局社内作成の「ご進講」とか社内から選ばれた「社外役員室」要員を使うだけでは完全に独立したチェックはできないわけです。
だからといって自らが独立の従業員を指揮して監視活動にあたらせるかというとその費用対効果はどうなのか、逆に日常業務を停滞させるのではないかという問題が出ます。
今の民主党の「政治主導」と官僚との関係のようなものですね。
また、よしんば監視を強化したとしても、エンロンのように巨額の利益をあげて急成長している途上の会社に対してストップをかける度胸(万が一それが間違った指摘だったらそれこそ会社の成長を大きく阻害してしまうわけです)があるか、また、社外役員がそこまでの「大役」になったときに引受ける人がいるかどうかは疑問だと思います。
アメリカではエンロン、ワールドコム事件を受けてSox法が制定されましたが、それが本当に機能しているかどうかは証明不能で、新たな不祥事が起きた場合に「機能していない」ことが明らかになるだけですから。
少なくともアメリカにおけるサブプライム・ローン問題を見る限り、粉飾決算などの不正には至らないが過大なリスクを負うような企業活動については欧米流のコーポレート・ガバナンスは機能しなかったわけです。
また、業績が低迷しても経営者が居座ったままでいたときに取締役を解任する機能を社外役員に求めるという議論もありましたが、しかし今日びオーナー企業でもない限り「居座る」というのは例外に近いんじゃないかと思います(富士通も一応社内の取締役が機能したようですし)。
むしろ本来会社として重要なのは、業績が悪化して新しいことをはじめる資金的余裕が乏しくなる前に、新しい経営陣に引き継ぐことだと思うのですが、これは社外役員がいればできるというものではありません。
(それがなされずに政治の世界で苦労しているのが、二箇所で戦争してるわ財政は大赤字だわで政権を引き継いで取りうる選択肢が限られているオバマ大統領ですね)
ひょっとすると、統計を取ったりすれば経営者が交代すると業績が上がるとかいうデータも出るかもしれませんが、これもたとえば会社が業績回復をかけて新社長を送り込むときは、直前に損を出し切ってジャンプ台を用意しておくということもあるので(たとえば日産自動車のゴーン社長の就任時とか)あまり参考にならないと思います。
それから、民主党の公開会社法案の中に従業員からの監査役選任というのもありますが、給料があがらないからといって従業員監査役が機能するとは思えません。
そのかわり、『日本の安心はなぜ、消えたのか』でも紹介されているように、日本の従業員は別に昔から組織や上司に忠誠を誓っていたわけではないので、上で言ったように社外役員が会社のために役に立たないと思えば体よく棚上げする一方で、経営者がだめだと思えば、「だめ」の態様に応じて、内部で上を突き上げたり、逆に手を抜いたり、場合によっては海上保安官のようにちょっと内情を外に漏らしてみたりということをするわけで(*)、そういうメカニズムが働けば、何も「コーポレート・ガバナンス」なんてご大層な後ろ盾がなくてもいいんじゃないかと思います。
(*) SESCの大森次長のこれなんかもそのひとつですね。
なので、会社法制の改正に関しては、総論としては
改正を所与の前提として拙速な取り纏めをすることなく、各検討事項につき、改正の必要性、方向性、改正の具体的内容および改正した場合の影響の内容や程度を慎重に検討する。
ことが必要だと思います。
ちなみに上のフレーズは、日弁連の(2010.6.17理事会)「民法(債権法)改正問題に取り組む基本姿勢」(参照)から拝借しました :-)
また、各論として何か現状を改善し、上の「標準的な議論」を進め、また「現在の議論」にも一定程度対応するとすれば、
取締役の報酬について、現状の一定金額以上の開示でなく報酬決定のルール自体を開示して、インセンティブの歪みがないかをステークホルダーが確認できるようにする 。
これだけでいいんじゃないかと思います。
これをやれば経営者も粉飾まがいの益出しや「一発逆転」のような過剰なリスクテイクの事業判断をするにも「悪意」を推定されないように説明責任を尽くすようになると思うので、一番手っ取り早くて実効性があると思うのですが、どうでしょうか。
(でも経団連とかはものすごく反対しそうですけど)。










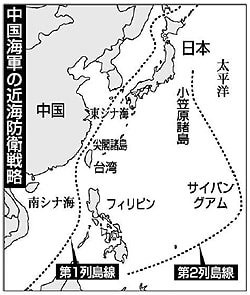
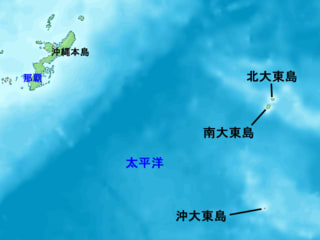
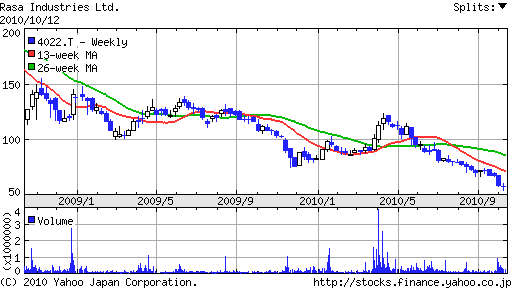
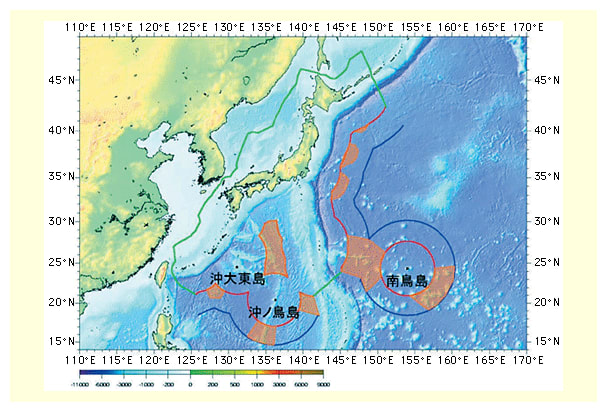 とすると
とすると 




