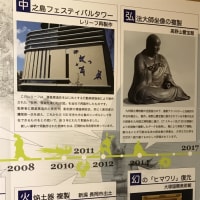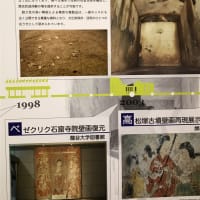(その2を書いていたらおさまりが悪くなったので、その1も加筆修正してます)
今回の高裁決定は決定文としては法律な論点をつめる以上にかなり「浪花節」の入ったものになっています。 特にスティールパートナーズを「濫用的買収者」と決め付ける認定する部分などは、
スティールを、高値で買い取らせることを目的に株を買い占める「グリーンメーラー的」などと大臣を筆頭に批判してきた経済産業省も「有事に導入された買収防衛策でも、入念な手続きをすれば認められるという画期的な判決だ」(幹部)と決定に大喜び。
(2007年06月29日 朝日新聞)
とはしゃいでいた経済産業省の幹部などさらに狂喜乱舞してしまうかもしれません。
また、裁判官の価値基準というものがよくうかがえるフレーズが随所にあります(下線は筆者)。
本件は、前記認定のとおりの属性を有し濫用的買収者と認められる抗告人が、日本国内で創業以来100年余の歴史を有し、堅調にソースの製造販売事業を行っている相手方を本件公開買付けによって買収しようとするものである。相手方は、このような買収行為によって、場合によって解体にまで追い込まれなければならない理由はないのであって、・・・
妙な外人は堅気の日本企業に手ぇ出しちゃいけねぇよ、というところでしょうか。
ブルドックソースのシェアは27.4%と国内トップですが、独禁法違反で勧告を受けた直後だったりしたらどうだったんでしょう。
また、
我が国において、本件のような敵対的買収行為の対応が成熟し、しかもそれが相手方ないしそれ以下の内容、規模の企業にまで浸透するには、なお時間と経験を要するであろうことは諸々の現実に照らしやむを得ないものであり、各企業の今後の重い課題である。
とも言っています。
要するに上場企業にも「おみそ」がいる、ということですね。証券取引所はいやな顔をしそうです。
また、マザーズとかヘラクレスの企業は本業そっちのけでM&Aばかりやっている企業が多いことを考えると、この裁判官は「古き良き日本企業は保護されてしかるべきだ」という価値観に立っているようにも読めます。
この判決について、「これで日本の株式市場に外人(投資ファンド)の金が流れなくなるのでは」等という論調も一部にあるようですが、アウトサイダーを排除しよう、という動きはどこの国でも起こる話です。たとえば
インサイダー取引:ダウ社外取締役を提訴へ 米証券取引委
米ダウ・ジョーンズへの買収提案をめぐるインサイダー取引疑惑で、米証券取引委員会(SEC)が、ダウ社の社外取締役を務める李国宝・東亜銀行会長を提訴する方針を固めたことが18日明らかになった。
(2007年7月19日 10時06分 毎日新聞)
金余りの状況が変わらない以上、儲けられそうだと思わせる(上品に言うと「魅力ある市場にする」ということでしょうか)ことさえできれば、お金は入ってくると思います。
アウトサイダー排除といえば村上世彰氏の実刑判決もその一環ともとれますね。
ただ、この事実認定を最近とみに摘発・監督処分モードになっている証券取引等監視委員会(や親元の金融庁)が適用するとかなり幅広い取引まで網が掛けられる可能性があるんじゃないかというのがちょいと心配ではあります。