JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。
10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。
古紙蒐集雑記帖
富士急行 都留市駅発行 東京山手線内ゆき 片道連絡乗車券
1977(昭和52)年4月に富士急行大月線の都留市駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道連絡乗車券です。

青色PJRてつだう地紋のA型一般式大人・小児用券になります。
前回御紹介致しました金額式券同様、硬券末期の最終様式となっており、従前の様式では大人運賃しか記載されておりませんでしたが、この頃から小児用運賃が併記されるようになっています。これは、富士急行の小児運賃が大人運賃の半額で、10円未満の端数を切り上げる方法を採っているのに対し、国鉄では小児運賃が大人運賃の半額であることには変わり在りませんが、10円未満の端数を切り捨てる方法が採られておりますので、小児用として発売する際の営業事故を防止する意味があったようです。
連絡乗車券に小児運賃を併記する方法は当時国鉄においてもこの頃から採用されており、それに倣ったものと思われます。
富士急行 大月駅発行 1110円区間ゆき片道乗車券
1993(平成5)年6月に富士急行大月線の大月駅で発行された、1110円区間ゆきの片道乗車券です。

青色PJRてつだう地紋のB型金額式大人・小児用券になります。
1110円区間は当時の同社最遠区間用で、河口湖ゆきの券になります。
これは同社の硬券末期に使用されていた様式で、どことなく国鉄東京印刷場で調製されていた金額式券に文字の並びが似ています。
ただし、印刷場は岳南鉄道を含む富士急行グループで独自の印刷場で調製していたようで、お世辞にもスッキリとした綺麗な印刷とは言えない活版印刷感が大変感じられる券が多く見受けられました。

同社の金額式券は大人・小児用として設備され、大人専用券は未見でしたが、小児用券も設備されており、自社用の金額式券で小児断片を切断して発売することは殆ど無かったようです。
富士山麓電気鉄道 河口湖から東京電環ゆき 学割用片道連絡乗車券
今から約66年前の、1955(昭和30)年5月8日に富士山麓電気鉄道(現・富士急行)河口湖駅で発行された、東京電環(現・東京山手線内)ゆきの学割用片道連絡乗車券です。

桃色PJRてつだう地紋のA型学割専用券となっています。
社名の「富士山麓電気鉄道」の「気」の字が「氣」という旧字体になっています。
学割と言っても同線には「社学」の制度は無かったと記憶していますので、社線区間については通常の大人運賃で、国鉄区間について学割適用運賃となっており、発売額は双方の合算になります。
現在でも大月駅から東京山手線内までの大人運賃は1,490円であり、学割は大人運賃の2割引ですので、1,490円の2割は298円となり、割引後の運賃の10円未満のは数は切り捨てとなることから割引額は300円であり、そのために学校によっては年間の発行枚数に制限のある「学生・生徒旅客運賃割引証」を年度が始まったばかりの5月に使用するのは、些かもったないような気がしてしまいます。
京浜電気鉄道 品川から北品川・立会川間ゆき片道乗車券
1934(昭和9)年4月に京浜電気鉄道(京浜電鉄・京浜急行電鉄の前身)品川駅で発行された、北品川駅・立會(会)川駅間ゆきの片道乗車券です。

地紋がハッキリしないのでどのようなものであったかが判別できませんが、桃色券紙のA型一般式大人・小児用券になります。

裏面です。券番の他、「(京濱電鐵)=京浜電気鉄道」の社名と「(品川驛發行)=品川駅発行」の表記があります。
京浜電気鉄道は京浜急行電鉄の前身の会社で現在の横浜駅以北の区間が該当し、1941(昭和16)年11月に横浜以北の区間に該当する湘南電気鉄道と合併して現在に近い路線網が出来上がります。
しかし、翌1942(昭和17)年5月に戦時の事業統制に基づき、東京急行電鉄に編入されてしまい、戦後の1948(昭和23)年6月に京浜急行電鉄として東京急行電鉄から分離し、現在に至っています。
富士山麓電気鉄道 河口湖から吉祥寺ゆき 片道連絡乗車券
1960(昭和35)年4月に富士山麓電気鉄道(現・富士急行)河口湖駅で発行された、国鉄(現・JR東日本)中央線吉祥寺駅ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色PJRてつだう地紋のA型一般式大人・小児用券になります。乗車経路は河口湖~(河口湖線)~富士吉田(現・富士山)~(大月線)~大月~(中央東線)~吉祥寺となる経路で、社線営業キロ26.6km、国鉄線営業キロ65.3km、合計91.9kmとなります。
同社は中央線の大月駅から分岐しているという路線であり、1934年(昭和9年)と古くから国鉄線との直通運転列車を走らせていた関係から、国鉄線との連絡乗車券は多岐に亘っており、現在でも赤坂駅・十日市場駅・寿駅・葭池温泉前駅を除く社線各駅からJR東日本の中央東線・篠ノ井線(広丘駅~松本駅間)を始めとして、東海道本線(東京駅~平塚駅間、西大井駅~新川崎駅間)・山手線・赤羽線・南武線・鶴見線・武蔵野線(北府中駅~西浦和駅間)・横浜線・東北本線(東京駅~大宮駅間、尾久、北赤羽駅~北与野駅間)・常磐線(日暮里駅~金町駅間)・総武本線(東京駅~小岩駅間、錦糸町駅~御茶ノ水駅間)・京葉線(東京駅~葛西臨海公園駅間)と、広範囲に亘っての連絡運輸が継続して行われています。
なお、この券が発売された約1か月後、同社は富士急行株式会社に社名が改称され、同線も富士急行線と呼ばれるようになります。
〇自 様似駅発行 自動車線70円区間ゆき片道乗車券
1986(昭和61)年9月に「〇自」様似駅で発行された、様似から70円区間ゆきの自動車線用片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式券で、札幌印刷場で調製されたものです。
国鉄日高本線の様似駅は、国鉄自動車線である日勝線の駅でもあり、発行駅名の頭にあります「〇自」の符号は自動車線駅であることを示しています。自動車線の様似駅は鉄道と同じ駅舎を使用しており、乗車券の発券窓口も鉄道と同じ窓口でした。
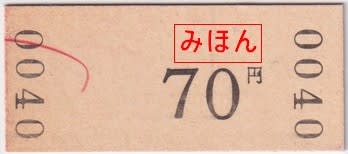
裏面です。当時すべての便がワンマン化されており、運賃収受機に乗車券を投入した際、箱の中で裏返しに着地しても金額の確認ができるよう、裏面にも70円の表記があります。
国鉄バス日勝線の歴史は古く、1943(昭和18)年に「苫小牧~浦河~様似~襟裳~広尾~帯広」という鉄道路線の建設計画があり、「鉄道の先行路線」という、鉄道が開通するまでの暫定的路線の位置づけで様似~襟裳間の路線として開業したのが始まりのようです。しかしながら、帯広~広尾間の広尾線がJR民営化直前の1987(昭和62)年2月に全線廃止され、日高本線についても2021(令和3)年3月に鵡川~様似間が廃止されてしまいましたので、日勝線はその殆どがバスだけが生き残る形となって現在に至っています。
富士山麓電気鉄道 河口湖から大月ゆき 片道乗車券
富士山麓電気鉄道(現・富士急行)河口湖駅で発行された、大月駅ゆきの片道乗車券です。

桃色PJRてつだう地紋のB型一般式大人・小児用券となっています。
富士山麓電気鉄道は現在の富士急行の前身で、今から約60年前の1960(昭和35)年5月に富士急行株式会社に改称されています。
同社は鉄道事業および自動車(バス)事業などの運輸事業を母体とする企業ですが、売り上げに占める鉄道事業の割合は5%程度しかなく、新宿バスターミナル(バスタ新宿)と富士五湖エリアなどを結ぶ中央高速バスを始めとした自動車事業や、沿線にある直営の遊園地である富士急ハイランド、ゴルフ場等の観光事業が主な収入になっているようです。
鉄道事業については「富士急行線」というJR中央線の大月駅から河口湖駅までの営業キロ26.6kmの路線がありますが、正確には大月駅から富士山(旧・富士吉田)駅までの営業キロ23.6kmの大月線と、スイッチバック方式になっている富士山駅から河口湖駅までの営業キロ3.0kmの河口湖線の2路線から成っています。全区間の標高差が約500mあり、河口湖駅方面ゆきの電車は延々と坂を登ることから、「富士山に一番近い鉄道」というキャッチフレーズで観光案内が行われています。
2021年4月28日、同社は2022年4月を目途として鉄道事業を分社化させ、「富士山麓電気鉄道株式会社」を設立するという発表をいたしました。新しい会社名は同社としては旧社名と同じであり、「先祖返り」するような感じになります。
JR北海道 新千歳空港から940円区間ゆき片道乗車券
1993(平成5)年9月にJR北海道千歳線(空港支線)の新千歳空港駅で発行された、940円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JR北地紋のB型金額式大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。
同駅は新千歳空港の千歳空港ターミナルビル供用終了および新千歳空港ターミナルビル供用開始にともなって1992(平成4)年7月に開業した新しい駅で、千歳線南千歳(旧千歳空港)駅から分岐する支線(空港支線)の終点に位置しています。同駅の開業に伴い、千歳空港駅は空港連絡駅としての使命が終了し、南千歳駅に改称されています。
同駅はJR北海道では珍しい地下駅で、開業が比較的最近であることから近代的な駅に見えますが、窓口には硬券が設備されており、券売機はあるものの、近距離用の硬券も発売されていました。
同社では通常使用される乗車券については平成初期に廃止されており、また、同駅には1998(平成10)年には自動改札機が導入されておりますので、同駅で硬券乗車券が発売されていた期間はさほど長くはなかったと思われます。
| 次ページ » |





