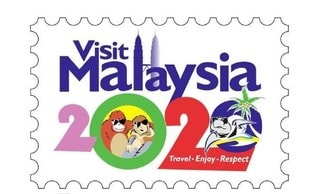北海道新聞08/15 05:00

【阿寒湖温泉】釧路市阿寒町阿寒湖温泉の木彫作家藤戸竹喜さん(83)が、道内の経済や文化発展に貢献した個人・団体を表彰する本年度の道功労賞に選ばれた。毛並みや表情までダイナミックに再現した木彫り熊や、アイヌ民族の先人を表現した等身大の人物像などで道内の文化振興に貢献したことが高く評価された。地元関係者から「阿寒の誇り」と喜びの声が上がっている。
藤戸さんは旭川市出身のアイヌ民族。熊彫り職人だった父のもとで幼少期から木彫りを始め、1964年に阿寒湖温泉で民芸店を開業。71年にモスクワのレーニン博物館に「レーニン胸像」を納めたほか、94年には、米国スミソニアン国立自然史博物館に作品が展示されるなど海外でも活躍し、14年にJR札幌駅にエカシ(長老)像が展示された。
昨年10~12月に札幌芸術の森美術館で開かれた個展「木彫家 藤戸竹喜の世界」には1万2千人が来場。同展は今年1~3月に国立民族学博物館(大阪府吹田市)でも開催され、2万5千人が訪れた。
阿寒観光協会まちづくり推進機構の大西雅之理事長は藤戸さんの功労賞受賞を「木彫り一筋に生きてきたアイヌ芸術家をたたえる最高の栄誉。受賞は郷土阿寒の宝であり、アイヌ民族全体の誇りとも言えるはず」と喜ぶ。
藤戸さんは現在入院中で、妻の茂子さん(69)は「藤戸は、受賞を『闘病の励みになる』と喜んでいる。支えてくれた多くの方のおかげ」と感謝を示した。
阿寒湖温泉からの同賞受賞は、1983年の前田一歩園財団初代理事長・故前田光子さん以来2人目。(佐竹直子)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/218507

【阿寒湖温泉】釧路市阿寒町阿寒湖温泉の木彫作家藤戸竹喜さん(83)が、道内の経済や文化発展に貢献した個人・団体を表彰する本年度の道功労賞に選ばれた。毛並みや表情までダイナミックに再現した木彫り熊や、アイヌ民族の先人を表現した等身大の人物像などで道内の文化振興に貢献したことが高く評価された。地元関係者から「阿寒の誇り」と喜びの声が上がっている。
藤戸さんは旭川市出身のアイヌ民族。熊彫り職人だった父のもとで幼少期から木彫りを始め、1964年に阿寒湖温泉で民芸店を開業。71年にモスクワのレーニン博物館に「レーニン胸像」を納めたほか、94年には、米国スミソニアン国立自然史博物館に作品が展示されるなど海外でも活躍し、14年にJR札幌駅にエカシ(長老)像が展示された。
昨年10~12月に札幌芸術の森美術館で開かれた個展「木彫家 藤戸竹喜の世界」には1万2千人が来場。同展は今年1~3月に国立民族学博物館(大阪府吹田市)でも開催され、2万5千人が訪れた。
阿寒観光協会まちづくり推進機構の大西雅之理事長は藤戸さんの功労賞受賞を「木彫り一筋に生きてきたアイヌ芸術家をたたえる最高の栄誉。受賞は郷土阿寒の宝であり、アイヌ民族全体の誇りとも言えるはず」と喜ぶ。
藤戸さんは現在入院中で、妻の茂子さん(69)は「藤戸は、受賞を『闘病の励みになる』と喜んでいる。支えてくれた多くの方のおかげ」と感謝を示した。
阿寒湖温泉からの同賞受賞は、1983年の前田一歩園財団初代理事長・故前田光子さん以来2人目。(佐竹直子)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/218507