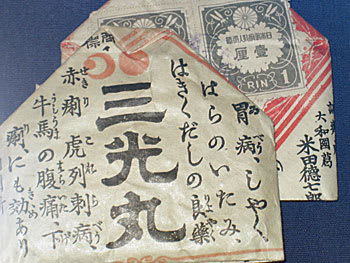ようやく秋らしくなりました。
曇り空の下、矢田丘陵を歩いてきました。


矢田寺駐車場のヒガンバナは、はや終わりに近くなりました。


稜線を歩いて南僧坊池を過ぎた湿地帯では、今年もキセルアザミの花がたくさん咲いています。
この花は終わると首をまっすぐに上に向けます。
露ナシ池で手を叩くと、久しぶりにヒメが艶やかな姿を現しました。釣り糸にも係らず、元気で暑い夏を乗り切ったようで、嬉しく思いながら下りました。
曇り空の下、矢田丘陵を歩いてきました。


矢田寺駐車場のヒガンバナは、はや終わりに近くなりました。


稜線を歩いて南僧坊池を過ぎた湿地帯では、今年もキセルアザミの花がたくさん咲いています。
この花は終わると首をまっすぐに上に向けます。
露ナシ池で手を叩くと、久しぶりにヒメが艶やかな姿を現しました。釣り糸にも係らず、元気で暑い夏を乗り切ったようで、嬉しく思いながら下りました。