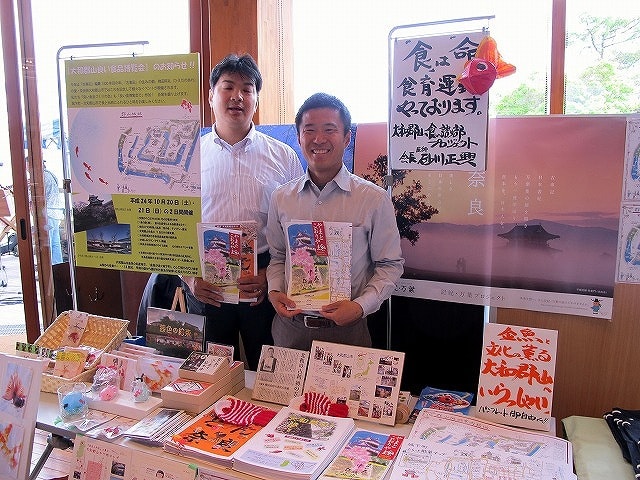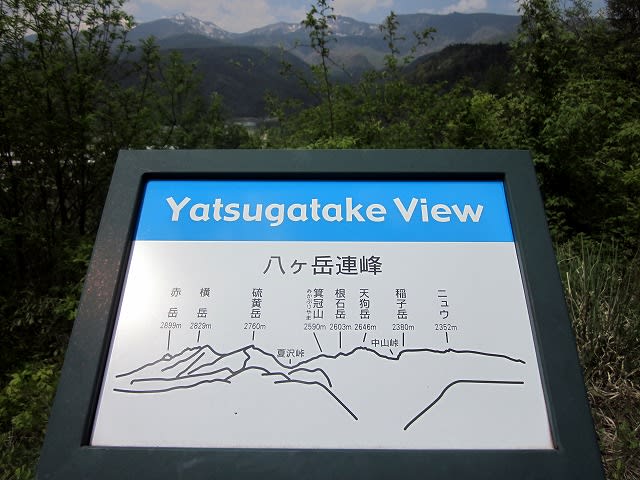山を歩いていて美しい花々に心惹かれるようになったのは、何時頃からでしょうか。若い頃は厳しい山に向き合って、「挑む」という程でもなくても登るだけで精いっぱいで、花を見てもそれほど関心を持てませんでした。ようやく足元に咲く美しい花々に心を動かされ、時には慰められるような余裕も出てきてカメラを向けるようになりました。そんな花たちとの5月の出会いの一部をご覧ください。
(ただいまフイルムスキャン、スキャナーによるプリントからのデジタル化などを行って整理中です。説明も不十分ですし誤りも多いと思いますが、ご指摘ご指導いただければ幸いです)
 青葉山(693m)
青葉山(693m)
若狭湾のすぐ近くに聳えています。秀麗な山容は福井・京都、それぞれの側から若狭富士、丹後富士と呼ばれています。山麓の松尾寺は西国二十九番札所。この山は山陰地方の植物の宝庫で、その数は400種類に及ぶといわれています。
立夏の日、松尾寺から山麓の道を、ヤブツバキ、ウマノアシガタ、キツネノボタン、アザミなどの野の花を見ながら中山登山口に歩きました。尾根末端から植林地に入るとシャガとホウチャクソウの大群落。赤紫や白のイカリソウは東峰を過ぎて西峰まで私たちの目を楽しませてくれました。
他にはアオダモ、キランソウ、スミレ、チゴユリ、エンレイソウなど。東峰山頂付近ではイワカガミの大群落。ここから西峰への尾根にはイワカガミ、ヤマシャクヤク、ヤマルリソウ、フデリンドウ…何度かハシゴ場などを過ぎて西峰へ。最後は10mほどの大岩に登って内浦湾の素晴らしい展望を楽しみました。帰りは松尾寺にお詣り。庭園はあでやかなボタンの花盛りでした。
 イカリソウ・淡紫(2003.05.06 青葉山)
イカリソウ・淡紫(2003.05.06 青葉山)
碇草、錨草。4枚の花弁が距を突出した形が舟のイカリの形に似ているのが名前の由来です。ただし、ここでいう「イカリ」は現在の形ではなく、昔の和船で用いられた四本鉤のイカリのことです。近畿でもあちこちの山で見かけましたが、花の赤紫色にはいろんな濃淡があるようです。
 イカリソウ・白(2003.05.06 青葉山)
イカリソウ・白(2003.05.06 青葉山)
 ヤマシャクヤク(2003.05.06 青葉山)
ヤマシャクヤク(2003.05.06 青葉山)
山芍薬。「立てば芍薬、座れば牡丹」という美人の形容詞となったシャクヤクの山ガール版。この時期あちこちの山で見かける花ですが、準絶滅危惧種として多くの都道府県でレッドリストに入っています。
 シロバナニシキゴロモ(2003.05.06 青葉山)
シロバナニシキゴロモ(2003.05.06 青葉山)
錦衣。 シソ科キランソウ属。普通、赤紫色の花で葉脈が紫色に染まり美しいので、この名がつきました。日本海側の山に多いと聞きました。近畿でよく見かける似た花にツクバキンモンソウがありますが、これは標高の低いところでも見られます。写真は青葉山で初めて見たシロバナのニシキゴロモです。
 七面山(東峰 1624m)
七面山(東峰 1624m)
五條市大塔(元大塔村)にあり大峯山脈から西に張り出した支脈上に東西二つの峰があります。この日はシャクナゲを見るのが目的でした。車は王子製紙林道入口までしか入れず、そこから1時間、標高差330mの登りでようやく登山口です。さっそく杉林の急登が始まる中で、♀ペンがこの花を見つけました。
笹原との境を行く道ではユキザサの群落、ギンリョウソウも落ち葉の中から顔を出していました。七面尾(も下辻山へ向かう長い尾根)から西峰へ向かう道ではまずシロヤシオ、そして次第に痩せてくる尾根道では回り一面が赤い色であふれかえるようなシャクナゲの大群落で、すっかり満足しました。
東峰へ往復した後、西峰から西に続く槍ノ尾を下ると写真のアケボノ平にでます。このように気持ちの良い笹原が拡がっています。正面の円錐形のピークが七面山東峰、その向こうに仏生ヶ岳、孔雀岳と奥駆け道の通る大峰の山々が見えます。槍ノ尾三角点ピークまでにはシャクナゲのトンネルもあり、なかなか楽しい山歩きの一日でした。
 イチヨウラン(2003.05.29 七面山)
イチヨウラン(2003.05.29 七面山)
葉が1枚だけなので一葉蘭。イチョウ〈公孫樹〉とは関係ありません。深山に見られる1属1種の日本特産種です。
 シャクナゲ(2003.05.29 七面山)
シャクナゲ(2003.05.29 七面山)
石楠花、石南花。ツツジ科ツツジ属。ホンシャクナゲの他にアズマシャクナゲ、キバナシャクナゲ、ハクサンシャクナゲなど多くの種類があり、各地の亜高山帯でよく見かける花です。ヒマラヤでも色んな種類のシャクナゲを何度か見かけました。関西では十津川の「21世紀の森」で世界各地のいろんな種類のシャクナゲを見ることができます。関西のお寺でもシャクナゲの名所がいくつもありますが、自生地としては大峰山脈の山々や稲村ヶ岳などが有名です。
 ギンリョウソウ(2003.05.29 七面山)
ギンリョウソウ(2003.05.29 七面山)
銀竜草。代表的な腐生植物(普通の植物のように光合成できず、菌類と共生して栄養素・有機物を得て生活する植物)です。色素が全くなく白いのでユウレイタケという名前もあります。全国の林床でごく普通にみられ、私の家の近く矢田丘陵でも見ることができます。よく似た植物にギンリョウソウモドキがありますが、これは出てくる時期が遅く秋になってからです。
 七七頭ヶ岳(693m)
七七頭ヶ岳(693m)
ななづがたけ。湖北・余呉湖の北に位置します。麓から仰ぐ山容の美しさから地元で「丹生富士」と呼ばれています。写真は上丹生近くの野神橋から見る七七頭ヶ岳です。ここから少し先の矢田部橋が登山口で山頂まで1.9km。地元の人がよく登る山のようで、エンレイソウが数輪咲くそばにたくさん木の杖が置いてありました。雑木林に入るとシュンラン。イカリソウはこの先頂上近くまでたくさん見られます。30分ほどで尾根道にでると、ヤマブキ、ヤブツバキ。あと「1000m」の標識近くはヤブレガサの群落。最後の急登ではヤマツツジ、ショウジョウバカマ、ブナやミズナラの疎林の中で各種のスミレ、シュンランも多かったです。
イワウチワは三角点北側の「るり池」周辺で、いくつも大きな群落を作って咲いていました。
 イワウチワ(2001.05.14 七七頭ヶ岳)
イワウチワ(2001.05.14 七七頭ヶ岳)
花言葉が「春の使者」。名前は葉の形状が団扇(ウチワ)に似ていることから来ています。この花も、鈴鹿の竜王山や油日岳、京都の峰床山、加賀の取立山など色々な山で出会いました。
 シュンラン(2001.05.14 七七頭ヶ岳)
シュンラン(2001.05.14 七七頭ヶ岳)
春に咲くので「春蘭」。分かりやすい名前です。あちこちの山で自生しているのを見かけましたが、東洋ランとして栽培もされていてわが家にも鉢植えのものがあります。
 油日岳(693m)
油日岳(693m)
鈴鹿山脈の南端部、甲賀・伊賀の国境に位置します。甲賀・油日神社のご神体山。山頂には岳明神の祠がありますが、山名は「山頂に降臨した大明神が油の火のような大光明を発した」ことに由来するといわれています。
1994年に北側の油日神社から登り三国岳まで往復したことがありますが、この日は三重県側の南登山口からゾロ峠へ登り、北へ縦走しました。
写真は登山口手前の余野公園から。左端に見えるのが油日岳、右端がゾロ峠です。
イワカガミは鳥不越峠から三国岳へ向かう途中の、何か所か虎ロープの張られた岩混じりの道のところどころで群れ咲いていました。三国岳は近江、伊勢、伊賀の国境です。この辺りにはイワカガミも咲いていました。ここからさらにいくつかのピークを上下して油日岳に登り、北側の尾根から分かり難い踏み跡をツツジが満開の余野公園に下りました。
 イワカガミ (2009.05.01 油日岳)
イワカガミ (2009.05.01 油日岳)
北海道から九州まであちこちの山で見ましたが、開花期が海抜によって違うので亜高山帯では7月頃から咲き始めます。北アルプスの白馬岳では7月末に咲いていました。岩鏡の和名は葉が鏡のように艶々と光っていることから付きました。
 イワウチワ(2009.05.01 油日岳)
イワウチワ(2009.05.01 油日岳)
 但馬妙見山 (1139m)
但馬妙見山 (1139m)
兵庫県八鹿、関宮、村岡の境界にあり矢田川、日置川の分水嶺となっています。江戸時代からの信仰の山であり、ザゼンソウの自生地があることで名高い山です。
大ナル登山口からキャンプ場を抜け山道になると「植物歳時記の道」の表示があり、スミレ、エンレイソウ、ミヤマカタバミなどの花が咲いていました。山頂には大きな方位盤があり、人の少ない静かな山でした。妙見新道を妙見峠に下ったところにエンレイソウの大群落がありました。ザゼンソウの群落は名草神社の社務所手前の山側斜面にありましたが、残念ながら花期は終わり近くで僅かの数の花が咲き残っているばかりでした。
 エンレイソウ(2005.05.08 但馬妙見山)
エンレイソウ(2005.05.08 但馬妙見山)
漢字で書くと延齢草、なかなか縁起の良い名前です。他に延命草、養老草などの名があるのは、中国では根を胃腸薬の原料としたことから来ています。しかし有毒植物で激しい中毒を起こすことがあるそうです。
 ザゼンソウ(2005.05.08 但馬妙見山)
ザゼンソウ(2005.05.08 但馬妙見山)
座禅草。名前の由来はお坊さんが座禅を組む姿に見立てたことから来ています。お坊さんを達磨大師としてダルマソウ(達磨草)とも呼びます。サトイモ科の植物です。