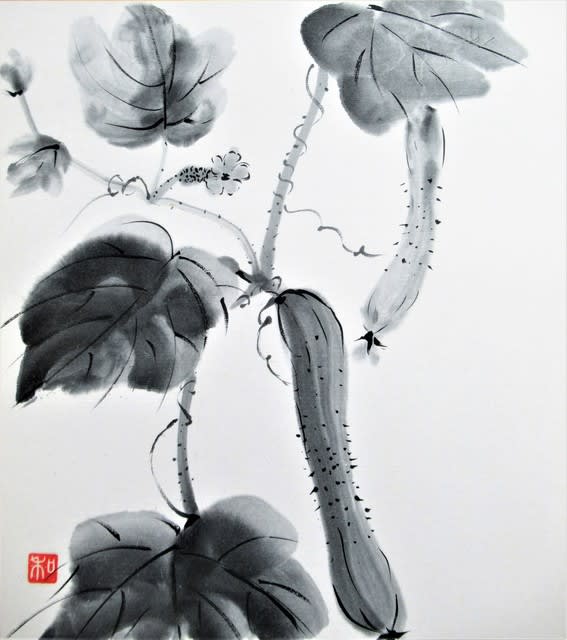今、ネジバナが可憐に咲いています。この辺りではネジリバナと言われることが多いです。

ここは、田んぼの土手ですが、ネジバナが咲いているのは畦の部分です。毎年ここにネジバナが咲きますが、今年も咲いてくれました。

この土手は先週に草刈りをしたのですが、ネジバナを避けながら刈り払うので、どうしても草が残ります。あっという瞬間に刈り倒してしまうので注意しながら草を刈っています。仮に刈り倒してしまっても、他の雑草と同じようにすぐ再生するのでしょうが、愛らしい花を切ってしまうのは忍びないです。

昔は、ほかの場所にもありましたが、今では、私が分っているのはここだけです。
ここは非常に日当たりがよく、周りは天然芝が多い場所なので、条件がいいのかもしれません。ネジバナはランの仲間ですが、他の天然のランは半日陰を好む傾向にあるので珍しい気がします。
ここは非常に日当たりがよく、周りは天然芝が多い場所なので、条件がいいのかもしれません。ネジバナはランの仲間ですが、他の天然のランは半日陰を好む傾向にあるので珍しい気がします。

小さな花がらせん状に綺麗に並んですっと伸びる姿は実にユニークでもあります。右巻きと左巻きと両方あるようですが、よく観察したことはありません。しかし、よく見ると確かに両方ありました。写真で見る方がよく分ります。

ネジバナを掘り上げて庭や鉢に植える方もあるようですが、ここのネジバナをそのようにする気はありません。移してだめにしたということも結構聞きますし、何といっても野に自然に咲いているのがいいです。