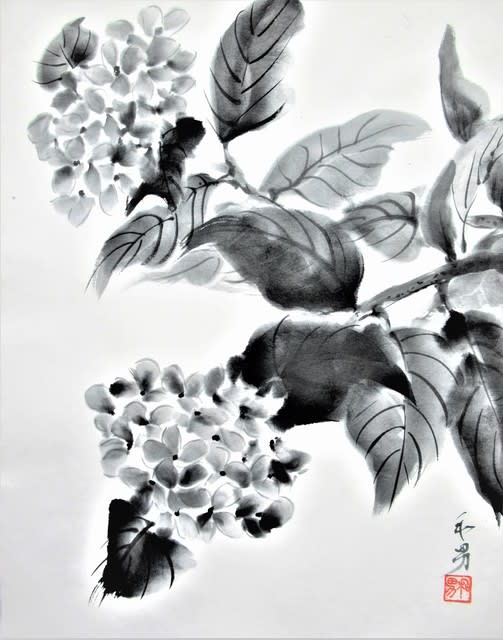ピーマンは6月末から収穫が始まりました。6月の気温が高かったため、小さい苗を植えたことを思えば早まりました。
誘引は、中央の1本の支柱と、畝の両側に廃材を利用したパイプを立て、それに横の直管パイプをフックバンドで止めた簡易な方法で行っています。ナスの誘引とほぼ同じやり方です。
誘引は、中央の1本の支柱と、畝の両側に廃材を利用したパイプを立て、それに横の直管パイプをフックバンドで止めた簡易な方法で行っています。ナスの誘引とほぼ同じやり方です。

枝を止めるのは中央の支柱にだけで直管パイプには縛りません。直管パイプに枝が密着すると枝はあまり動かず、垂れ下がらないようになります。

枝が伸びるのに合せて、この横の直管パイプを上げていきます。フックバンドを完全には止めていないので、下から上に軽く叩くと簡単に上がります。

ピーマンの枝は細いため、実が着くと枝が垂れ下がりやすい。今回一挙に20センチ位上げました。支柱はピーマンの枝が広がるのに合わせ上の方が少し広がっています。

この反対側の横パイプも上げました。
これからもパイプを上げるのでフックバンドを完全には止めません。

これで、枝の垂れ下がりは防げます。時に枝折れしたり、パイプの下をすり抜けるものもありますが、ピーマンは分枝が多いので、それらは切ってしまいます。
整枝は最も簡易な「ふところ枝」の整理を行っています。
ピーマンは花芽が着くごとに2本に分枝し、ねずみ算式に枝が増えていくので放置するとどんどん枝が混んでいきます。
「ふところ枝」とは株の内側の方に向かって伸びている枝の通称です。これを整理し、光線の通りをよくします。風通しが良くなることで病害虫予防にもなり、花芽も整理されて実の太りも良くなります。
旺盛に茂っており、かなり混んできました。
旺盛に茂っており、かなり混んできました。

株を上からのぞき込むようにして、ふところ枝を整理します。
株の中心に向かっている枝を間引きました。

株の中央部が透けて見えるようになりました。

ピーマンの簡易な誘引と整枝が終わりました。

複数の分枝から穫れるようになり、これから収穫の最盛期に入ります。

品種は「京みどり」。縦長で表面に筋が入ったスマートな形をしています。果肉がやや薄く軟らかなピーマンです。