
カゴシマは、もの心ついた時には「鹿兒島」だったような気がします。文字的にいうと、何だか怖い感じの場所でした。真ん中の「兒」も不思議な生き物に見えて、シカがいたり、不思議な生き物もいる変てこな場所のイメージが広がっていました。その頃は、父や母の話でカゴシマをイメージするしかない大阪の子どもでした。カゴシマは父母のふるさとでした。
父は鹿児島に手紙を書いたり、荷物を送ったりするとき、「鹿兒島縣」と書いてたと思います。そんなに古くて遠くて、ムズカシイ場所がカゴシマでした。ですから私は、そうじゃなくて、私の心のふるさとにしようと思って(かな?)、鹿児島を「カゴシマ」でかくことが多いです。「かごしま」と書かないのは、ひらがなで読んでもらって人に媚びるようなことはしたくないからです(ひらがな表記って、相手に対する思いやりという側面もあるけど、何だかバカにされた感じもしてしまう?)。
ひらがな表記が媚びていて、カタカナ表記は自らの心の作業だなんて、つまらないヘ理屈です。でも、カゴシマ表記は続けると思います。漢字で書きたくなったら、ポンと押すだけだから、そうします。今は何かこだわりがあるんですね、よくわからないけれど。住もうと思えば家はあるのだけれど、今まで全く住んだこともないですし、私のふるさとではありませんでした。生まれた土地ではあるのだけれど……。

沖縄は、私には「琉球」ではありません。ずっとオキナワだったような気がします。「縄」という漢字、今なら書こうとしたら、「えっ、糸へんに、カメ(亀)みたいな字の上、何か要らないの?」と頭が迷うかもしれない。
そんな時は、頭は頼りにならないから、手に紙で書かせてみて、正しい文字を呼び出すと思うんだけど、ちゃんと「縄」と書けるかどうか、私の頭は日々ボケてますからね、そのうち書けなくなるかもしれない。手で文字を書くことも忘れてはいけないかもしれない。
それがどれだけの効果があるのか、わかりませんけど、手を動かすのは悪いことではありません。へたくそでひねこびた文字を書いていきたいです。
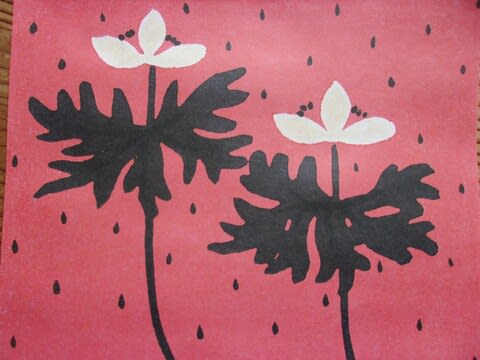
沖縄は、「オキナワ」だったというのは、小さい頃の思い出に重なりますか。小さい頃、近所に沖縄会館というのがあって、琉球舞踊とか、大阪に移り住んだ人々の交流の場がありました。私なんかはとてもそこに出入りできないのですが、でも、ごくたまに、そちらでイベントがあると、めったに入れない沖縄会館に行くチャンスだから、行くこともありました。
1970年前後の頃、中国とようやく国交が開けそうな気配があって、中国物産展なんかも沖縄会館でありました。エンピツとか、中国製のものが売ってたけど、子どもが買えるのはその程度だったけれど、とんでもない品質の悪いものだったと記憶しています。書いててウンザリしましたっけ。それよりはコーリン鉛筆、トンボ鉛筆、みつびし鉛筆などの質の高さ、書きやすさ。比べものにはならなかった。ただ異国情緒を味わうためのイベントだったのか、近くにあるのに何だか遠い国を知る機会でした。
今の中国は、近くにあるし、いろんなものが中国のおかげで手に入れられるんだけど、物質的にはとても近いところにあるのに、というか、私たちの生活すべてが中国抜きでは成り立たなくなっているのに、心理的な距離は遠くなってしまっています。70年代や80年代のころの方が心理的には近しいところにあった気がします。

沖縄会館では、映画も見せてもらいました。普通の映画ではなくて、沖縄返還を訴えるための映画でした。どうしてそういう映画を見に行ったのか、母の趣味だったのか、ただのイベントとしての参加か、とにかくオキナワは、まだ日本ではないらしい。自分のまわりにたくさんいる、オキナワがルーツの子どもたちは、ふるさとを遠く離れて大阪にいて、こうした映画が伝える土地に過去に住んでいたり、親が大阪にやって来て、ここで生まれた二世だったのかもしれません。
自分のまわりのたくさんの大人たちも、チャンスを求めて大阪に来ていた。つてを求めて、私の住んでいる地域の人々は、たいていは沖縄の人か、鹿児島の人か、広島・徳島、どこか遠くの方から来ていた人々でした。親友のノリちゃんちは、奈良県だったから、まだ近い方でした。
よそからやって来た人びとが、寄り添って生きる町に私は住んでいたようでした。どこの町ももそんなものかと思っていたけれど、それはそうではなかったようです。都会には地方から来た人たちもいただろうけど、うちの大阪の実家は特によそから来た人々の吹きだまりみたいなところでした。
かくして、いろんなルーツを持つ人々の一つとして「オキナワ」を意識し、今も漢字で書けるかどうか不安ではあるけど、何度か行かせてもらう機会があったので、「オキナワ」というとんがった感じは私の中でなくなっていきました。
今、私の沖縄は、「おきなわ」になっています。そんなに簡単に行けるわけではないし、遠いところではある。でも、あこがれのオリオンビールは奮発して買いますし、伸びやかさと温かさとたくましさは、感じています。そして、私たちの持っていない何かがそこにあるし、特別なところだし、割と好きなところです。でも、そんなに簡単には行けない。
私の個人的な印象ですけど、沖縄の今を、何とかしなくちゃという気持ちはずっと持っています。有事どうのこうのではなくて、それをなくす努力をしなくてはならない。東シナ海有事があるというのなら、それを徹底的になくせるように、徹底的に平和的な手段で、しなくちゃと思います。



















