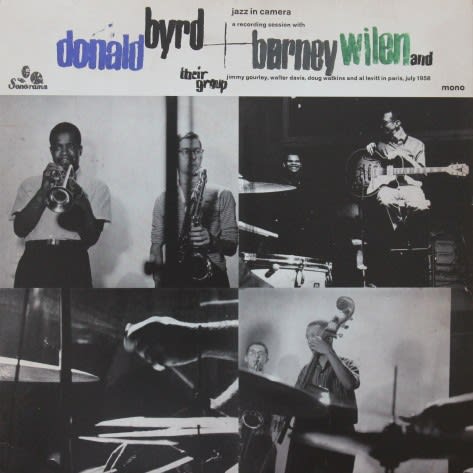Yusef Lateef / Lost In Sound ( 米 Charlie Parker Records PLP-814-S )
チャーリー・パーカーの法定相続人だったドリス・パーカーが散逸した彼の音源資産を守るために興したのがこのレーベルだが、パーカーの演奏
以外にもオリジナルアルバムをいくつか作成していて、これがなかなか聴かせるものが多い。このアルバム裏面のライナーノーツも彼女自身が
書いており、多面的な側面を持ったラティーフの真の実像をここで紹介したい、と率直な想いを書き残している。彼女にはレーベル・オーナー、
レコード・プロデューサーとしての才能があったようでこれには驚かされるが、パーカーと結婚するような人だから元々只者ではなかったのだろう。
彼女が言うように、ユーゼフ・ラティーフはフルートやオーボエなどを操りながら第3世界の音楽要素をミックスした独自の世界観を表現する
アーティストで、我々凡庸なリスナーにはなかなかその実態がよくわからないというのが正直なところだろう。そのエキゾチックな雰囲気から
カルト的アーティストとして一目置かれてはいるが、彼への理解度はその範囲を出ることはない。それは当時も同じだったようで、ドリスは
そういう呪縛を払拭させるために彼にテナーに専念させ、トランペットとリズム・セクションを充ててごく普通のハード・バップを演奏させている。
ラティーフ以外はまったくの無名アーティストたちだが演奏はしっかりとしており、一体どこから連れて来たんだ?とこれにも驚かされる。
ラティーフのテナーの硬質な音色が気持ちいいサウンドで、フレーズも普通のコード進行をベースにしたもので、彼の演奏としてはこういうのは
珍しい。トランペットもケニー・ドーハムやブルー・ミッチェルを思わせるような音色とフレーズで、何だかリヴァーサイドのレコードを聴いている
ような気分にさせられる。バックのピアノトリオ(特にドラムス)の演奏が闊達で、土台がしっかりとしているとこが素晴らしい。
どうも突拍子もないフレーズは吹くなと指示を受けていたような雰囲気があって、ラティーフは極めてお行儀よく演奏しているので、
そういう意味では少し拍子抜けする感があるかもしれない。ここで聴かれる典型的なハード・バップはこのレーベルに残された他のアルバム
全体にも共通する雰囲気で、それがドリス・パーカーの音楽的嗜好だったのだろう。ジャケットやレコードの質感がチープなので典型的な
安レコとしてエサ箱の肥やしになっているが、内容は第1級のハード・バップが聴けるいいレーベルだった。