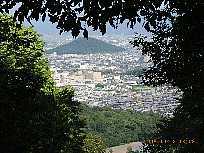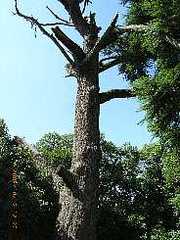いつもは主人と娘夫婦に任せっぱなしの自治会の溝掃除に、久~し
ぶりに(何年振り?)に参加。(主人と娘夫婦に感謝)
できる時には頑張っとこう。
「今年は家族総出ですね」と近所の人に言われた。
午後からは、小雨降る中「鳴く虫の観察会」に堺市大泉緑地へ
雨も降ってるし夜なので、今日は来る人もないだろうと思っていた
が、一人二人と集まり、結局15人になった。熱心な人たち!
案内の「イケメンの講師」が効果大?
今回講師をお願いしたのはK大の2回生の学生さん
ボランティアでやっているとは聞いていたが、説明もなかなかの
もので感心した。頼もしい。
この頃は虫の声とも縁遠くなったが、
一言で虫の声といっても足を翅にすりつけたり、翅のやすり器と
まさつ器をこすり合わせたり発音方法もさまざまらしい。
その音を聞く「耳」は大切で、コオロギは前足の付け根にあると
いうのは聞いたことがあるが、バッタは腹部の前にところにある
とのこと。
大事な「耳」が取れやすい前足についているなんて都合が悪いん
じゃないの?と思ってしまう。
実験をしたことがあるそうで、耳を失ったコオロギは仲間との
コミュニケーションがうまくいかず、いじめられたりすることも
あるそうだ。
発音鏡などで増幅して遠くまで響かせる。外国では15㎞先まで届
くのもあるそうだ。
ボルネオのジャングルで、チェーンソウかと思った音が「シカダ」
と呼ばれるセミだと聞いてびっくりしたのを思い出した。
草むらで虫探し。
最初に見つかったのは昆虫ではなく「セアカゴケグモ」の子供だ
った。初めて本物を見た。


エンマコオロギやハラオカメコオロギ・ツユムシ・ショウリョウ
バッタ・ホシササキリやシブイロカヤキリモドキなどという初め
て名を聞くものもあった。捕まったのはメスが多かった。


ホシササキリ クビキリギス
クビキリギスは噛むとなかなか離さず、強く引っ張ると首が取れ
てしまうそうだ。口元は口紅を塗ったように赤い。
かそけき虫の音は私の耳には聞き取れず残念
降ったりやんだりの中、予定の8時まで観察した。
真っ暗になった池の近くの草むらでは、バッタの仲間が草の葉
にとまっておやすみ中の姿を見れた。
ぶりに(何年振り?)に参加。(主人と娘夫婦に感謝)
できる時には頑張っとこう。
「今年は家族総出ですね」と近所の人に言われた。
午後からは、小雨降る中「鳴く虫の観察会」に堺市大泉緑地へ
雨も降ってるし夜なので、今日は来る人もないだろうと思っていた
が、一人二人と集まり、結局15人になった。熱心な人たち!
案内の「イケメンの講師」が効果大?
今回講師をお願いしたのはK大の2回生の学生さん
ボランティアでやっているとは聞いていたが、説明もなかなかの
もので感心した。頼もしい。
この頃は虫の声とも縁遠くなったが、
一言で虫の声といっても足を翅にすりつけたり、翅のやすり器と
まさつ器をこすり合わせたり発音方法もさまざまらしい。
その音を聞く「耳」は大切で、コオロギは前足の付け根にあると
いうのは聞いたことがあるが、バッタは腹部の前にところにある
とのこと。
大事な「耳」が取れやすい前足についているなんて都合が悪いん
じゃないの?と思ってしまう。
実験をしたことがあるそうで、耳を失ったコオロギは仲間との
コミュニケーションがうまくいかず、いじめられたりすることも
あるそうだ。
発音鏡などで増幅して遠くまで響かせる。外国では15㎞先まで届
くのもあるそうだ。
ボルネオのジャングルで、チェーンソウかと思った音が「シカダ」
と呼ばれるセミだと聞いてびっくりしたのを思い出した。
草むらで虫探し。
最初に見つかったのは昆虫ではなく「セアカゴケグモ」の子供だ
った。初めて本物を見た。


エンマコオロギやハラオカメコオロギ・ツユムシ・ショウリョウ
バッタ・ホシササキリやシブイロカヤキリモドキなどという初め
て名を聞くものもあった。捕まったのはメスが多かった。


ホシササキリ クビキリギス
クビキリギスは噛むとなかなか離さず、強く引っ張ると首が取れ
てしまうそうだ。口元は口紅を塗ったように赤い。
かそけき虫の音は私の耳には聞き取れず残念
降ったりやんだりの中、予定の8時まで観察した。
真っ暗になった池の近くの草むらでは、バッタの仲間が草の葉
にとまっておやすみ中の姿を見れた。