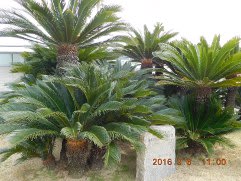京都の洋館などを巡る。
丸太町駅上がってすぐ、美しい煉瓦塀の中の木越しに見える建物は大丸ヴィラ


大丸百貨店店主の下村家の住居 塀が高くて上部しか見えないのが残念。
木を組み合わせることで落ち着いた雰囲気 昭和5年 ヴォーリズ建築事務所の設計とのこと。


聖アグネス教会の大聖堂 1898年(明治31年)平安女学校のチャペルとして建設された。
ここも外観のみ。 続く平安女学院京都キャンパスの場所は旧二条城の跡らしい。
続いて京都府庁へ
旧本館 1904(明治37年)竣工。昭和46年まで京都府庁の本館として使用。現在も会議室などに使われていて、「創建当時の姿をとどめる現役の官公庁建物」としては日本最古のもので、国の重文となっている。


重厚で均整のとれた建物 中庭を取り囲む「ロの字」にとり囲む形。
右)初めてとりいれられたという 玄関の「車寄せ」
旧本館内を見学


2階への階段 周辺のデザインも美しい。 彫刻のある手すりは大理石
旧知事室や正庁(大広間)を見学


大広間 天井の白い漆喰塗りは宮大工の仕事とか。戦前は天皇即位などに使われたというこの大広間。すごいのは今も催し物などに使われ、撮影用やウェディングなどに貸し出しも行っているということ。
右)賓客を迎えるドアには、上部の三角の破風(ペディメント) 格式を表すものだそうだ。


正庁(大広間)から大きく張り出したバルコニー 今までここに出た人は、明治天皇と蜷川知事と?ガガーリンの3人だけとか。この下は車寄せになっている。 右)廊下
内部のデザイン置かれた家具 外壁の各所にも凝った装飾があった。
素晴らしい建物、いつまでも使ってほしいなと思う。

中庭に出た。中央に円山公園の枝垂れ桜の孫の枝垂れ桜
中庭は桜の名所で、もうしばらくすると観桜祭(3月25日~4月4日)も開催される。
上から眺める桜 きれいだろうな。
議場棟(新)は地上3階、地下1階


3階にある(新)議場 傍聴席から見学 議員さんは60名とか。議事録はパソコンかと思ったら、速記も使っているらしい。 右)見たかった旧議場は今修復整備工事中 窓から覗く。
桜のころには完成するらしい。
昭和46年建築の新館2号館は6階建て
エレベーターで6階まで上り、階段を上って屋上「京テラス」へ。

6階 踊り場から下を見る。発掘現場のようだ。
屋上京テラス。 京都議定書に基づく地球温暖化対策


厚手防水シートの上に30センチ厚さの軽量土 その上に一面にコウライシバが貼ってある。
雨水が浸み出す配管もしてある。府民利用のコーナーもある。
右)太陽光発電装置 わずかな分しか賄えないらしいが。

旧本館 玄関前にゆるキャラ「まゆまろ」くんが出ていた。
手触りふわふわ。どこから見ているの?
お昼は新館の地下 生協食堂でお弁当を食べた。
終わって出てきたらちょうど12時。入れ替わりに職員さん達が次々と食堂へ。
京都府庁を出て、
護王神社
平安京の遷都に貢献した和気清麻呂を祀る。
清麻呂が助けられたというイノシシに因み、イノシシ神社とも言われる。


狛犬ならぬ「狛イノシシ」があちこちに。友だちに連れて来てもらったことがあるなあ。
京都御苑へ。
江戸時代には京都御所周辺に200もの公家屋敷が並んでいたという。
明治になって、首都が東京に移り、それに伴って公家も移転。
邸宅は取り壊されて荒れていたのを国民公園として整備された。
現在は、御所は宮内庁が、京都迎賓館は内閣府が、それ以外の公園部は環境省、と3つの官公庁が管理している。


ウメが満開 時代を感じさせるクスノキ大木

オガタマノキ 低い位置に枝がありたくさんの花が咲いていた。
その一隅にある閑院宮跡へ。


閑院宮跡 建物跡もあり、庭園には水が引き込まれいい雰囲気
館内には自然や歴史の展示もあった。

アオバズクの食痕 ムシの残骸の数々 何でも食べるんだなあ。
アオバズクは何回か見に来たことがある。
部屋の周囲を巡る廊下の雨戸


角の部分には工夫がある。上の角 下の角


角まで北雨戸は、下の突起に引っ掛かりくるりと反転 角のこちら側に回り込む。
面白い。すごいアイデア。
京都府庁も説明付きで見ごたえがあったし、他のところもよかった。一日充実。