千曲市森のあんずの里が4月7日土曜日に満開になりました。ほぼ平年並みです。晴れた日曜に来たかったのですが、スギ花粉の飛散がピークというので諦めました。月曜日の午前中は花曇りでしたが、上平の駐車場はほぼ満車。午後から雨というので人の出も早かった様です。花粉は前日でほぼ飛び終わった様ですが、昼過ぎになると風が出てまた飛び始めるので、午前中だけにしました。明朝に大雨になる予報。花散らしの雨になるかも知れません。あんずは桜に比べると花期が短いのです。

毎年撮影する在来種のあんずの木。昨年より色が薄いのは気候のせいでしょうか。

在来種のあんずの花。

花びらに濃い桃色の線が入っています。あんずは種類によって花の色や大きさが異なります。

満開のあんずの里。左端に見える大木は樹齢300年を超えると伝わる古木。森のアンズは、天和年間(1681~1683年)元禄時代、伊予宇和島藩主伊達宗利侯の息女豊姫が、松代藩主真田幸道侯に興し入れの際、故郷の春を忘れじとして国許よりアンズの苗木を取り寄せ、松代東条地区に植え付けたのが始まりとされています。安永年間(1772~1780年)松代藩は、森村・倉科村・生萱村・石川村などへ苗木を配布し、栽培を奨励しました。

あちこちでレンギョウやコブシも咲いています。右奥のあんずはまだ一分咲きです。あんず祭りは12日までですが、それまで持ちそうです。

樹下にはホトケノザやオオイヌノフグリ、水仙、タンポポ、ムシカリ、クリスマスローズなどが咲いています。

あんずの小道を登ってあんず畑の上部へ。

あんず畑の最上部まで満開になりました。あんずの実は6月中旬すぎから販売されます。

遠くに北アルプスの白馬三山が霞んでいます。

あんずのトンネル。他の畑は立入禁止ですが、ここはご自由にお入りくださいと書いてありました。

禅透院の鐘楼と在来種の杏の花。右奥はやはり満開のサンシュユ(山茱萸)。

サンシュユの花。

興正寺へ。山門にある「子持龍」は、諏訪立川流の天才・立川和四郎富昌の作。富昌は八幡の武水別神社の再建中でした。そこで、森出身の弟子・宮尾八百重を案内役に住職、世話人、名主らが建築現場に赴き建築を依頼。引き受けた富昌は三月頃から、父富棟が寛政二年(1789)に建築した善光寺大勧進の表御門形式を参考に絵図面を制作。四月には八百重の家に投宿し近くの薬師山に登って酒宴を催し、満開の杏花を愛でたといわれています。夜は篝火の下で鼓を鳴らし謡曲の「鞍馬天狗」を吟じ、見事な龍を描き上げ、村人や近郷近在の話題をさらい、村では日本一の宮大工が来たと喜んだそうです。

山門越しに見る枝垂れ桜。長野市でもソメイヨシノの開花宣言がされました。

興正寺越しにあんずの里。集落内のあんずの木がずいぶんと減ったなと思います。高校の窓から見えたのですが、その頃は藁葺き屋根もまだ多く、それぞれの屋敷の中に在来種のあんずの木がありました。我が家も大きなあんずの木があったのですが、養蚕のための二階建てのはなれを造る際に切りました。

帰路に立ち寄る岡地。西に山があって日暮れが早いので半日村と呼ばれます。花見客も訪れない穴場です。岡地天満宮には菅原道真作の菅原道真の木像と、法華経妙荘蔵王品一基が所蔵されていますが、菅丞相書『法華経並びに親作木像記』によると、どちらも菅原道真自作・真筆のものと伝えられています。岡地に安置されるようになった経緯は非常に複雑です。もともとの所有者は、江戸城を築城した太田道灌〔「七重八重花は咲けども山吹の実の(蓑)ひとつだになきぞ哀しき」という逸話で有名〕が足利学校で学んだ折りにもらい受けたとされています。ただし、道真公からどういう経緯を辿って足利学校に所蔵されるようになったかは不明です。
昨年は3月28日に満開になりました。下はその記事のリンクです。
●あんずの花は満開。信州千曲市あんずの里は今が見頃です。レンギョウとサンシュユも満開(妻女山里山通信)

8日に長野市のソメイヨシノの開花宣言が出ました。これは10日午後の妻女山。上杉謙信槍尻の泉上のソメイヨシノ。五分咲きぐらいです。森のあんずは豪雨でかなり散りましたが、まだ見られます。

妻女山松代招魂社のソメイヨシノやエドヒガンに枝垂れ桜。三分から五分咲きぐらいです。気温が高いので週末には見頃になるでしょう。貝母も咲き始めるでしょう。
●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。
もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。
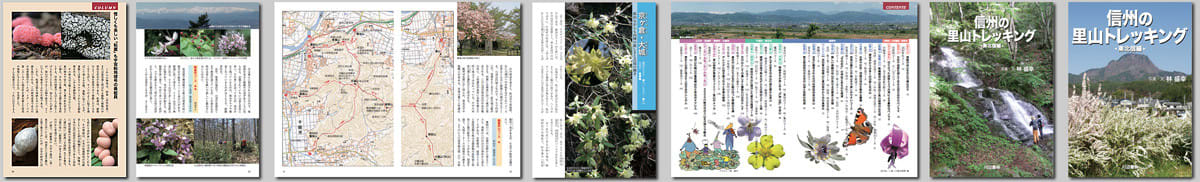
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。掲載の写真は有料でお貸しします。他のカットも豊富にあります。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

毎年撮影する在来種のあんずの木。昨年より色が薄いのは気候のせいでしょうか。

在来種のあんずの花。

花びらに濃い桃色の線が入っています。あんずは種類によって花の色や大きさが異なります。

満開のあんずの里。左端に見える大木は樹齢300年を超えると伝わる古木。森のアンズは、天和年間(1681~1683年)元禄時代、伊予宇和島藩主伊達宗利侯の息女豊姫が、松代藩主真田幸道侯に興し入れの際、故郷の春を忘れじとして国許よりアンズの苗木を取り寄せ、松代東条地区に植え付けたのが始まりとされています。安永年間(1772~1780年)松代藩は、森村・倉科村・生萱村・石川村などへ苗木を配布し、栽培を奨励しました。

あちこちでレンギョウやコブシも咲いています。右奥のあんずはまだ一分咲きです。あんず祭りは12日までですが、それまで持ちそうです。

樹下にはホトケノザやオオイヌノフグリ、水仙、タンポポ、ムシカリ、クリスマスローズなどが咲いています。

あんずの小道を登ってあんず畑の上部へ。

あんず畑の最上部まで満開になりました。あんずの実は6月中旬すぎから販売されます。

遠くに北アルプスの白馬三山が霞んでいます。

あんずのトンネル。他の畑は立入禁止ですが、ここはご自由にお入りくださいと書いてありました。

禅透院の鐘楼と在来種の杏の花。右奥はやはり満開のサンシュユ(山茱萸)。

サンシュユの花。

興正寺へ。山門にある「子持龍」は、諏訪立川流の天才・立川和四郎富昌の作。富昌は八幡の武水別神社の再建中でした。そこで、森出身の弟子・宮尾八百重を案内役に住職、世話人、名主らが建築現場に赴き建築を依頼。引き受けた富昌は三月頃から、父富棟が寛政二年(1789)に建築した善光寺大勧進の表御門形式を参考に絵図面を制作。四月には八百重の家に投宿し近くの薬師山に登って酒宴を催し、満開の杏花を愛でたといわれています。夜は篝火の下で鼓を鳴らし謡曲の「鞍馬天狗」を吟じ、見事な龍を描き上げ、村人や近郷近在の話題をさらい、村では日本一の宮大工が来たと喜んだそうです。

山門越しに見る枝垂れ桜。長野市でもソメイヨシノの開花宣言がされました。

興正寺越しにあんずの里。集落内のあんずの木がずいぶんと減ったなと思います。高校の窓から見えたのですが、その頃は藁葺き屋根もまだ多く、それぞれの屋敷の中に在来種のあんずの木がありました。我が家も大きなあんずの木があったのですが、養蚕のための二階建てのはなれを造る際に切りました。

帰路に立ち寄る岡地。西に山があって日暮れが早いので半日村と呼ばれます。花見客も訪れない穴場です。岡地天満宮には菅原道真作の菅原道真の木像と、法華経妙荘蔵王品一基が所蔵されていますが、菅丞相書『法華経並びに親作木像記』によると、どちらも菅原道真自作・真筆のものと伝えられています。岡地に安置されるようになった経緯は非常に複雑です。もともとの所有者は、江戸城を築城した太田道灌〔「七重八重花は咲けども山吹の実の(蓑)ひとつだになきぞ哀しき」という逸話で有名〕が足利学校で学んだ折りにもらい受けたとされています。ただし、道真公からどういう経緯を辿って足利学校に所蔵されるようになったかは不明です。
昨年は3月28日に満開になりました。下はその記事のリンクです。
●あんずの花は満開。信州千曲市あんずの里は今が見頃です。レンギョウとサンシュユも満開(妻女山里山通信)

8日に長野市のソメイヨシノの開花宣言が出ました。これは10日午後の妻女山。上杉謙信槍尻の泉上のソメイヨシノ。五分咲きぐらいです。森のあんずは豪雨でかなり散りましたが、まだ見られます。

妻女山松代招魂社のソメイヨシノやエドヒガンに枝垂れ桜。三分から五分咲きぐらいです。気温が高いので週末には見頃になるでしょう。貝母も咲き始めるでしょう。
●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。
もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。
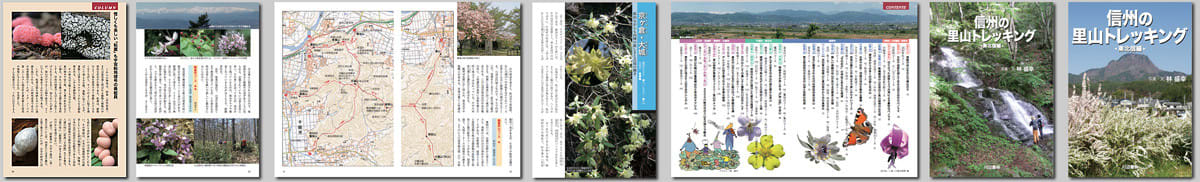
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。掲載の写真は有料でお貸しします。他のカットも豊富にあります。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

























