
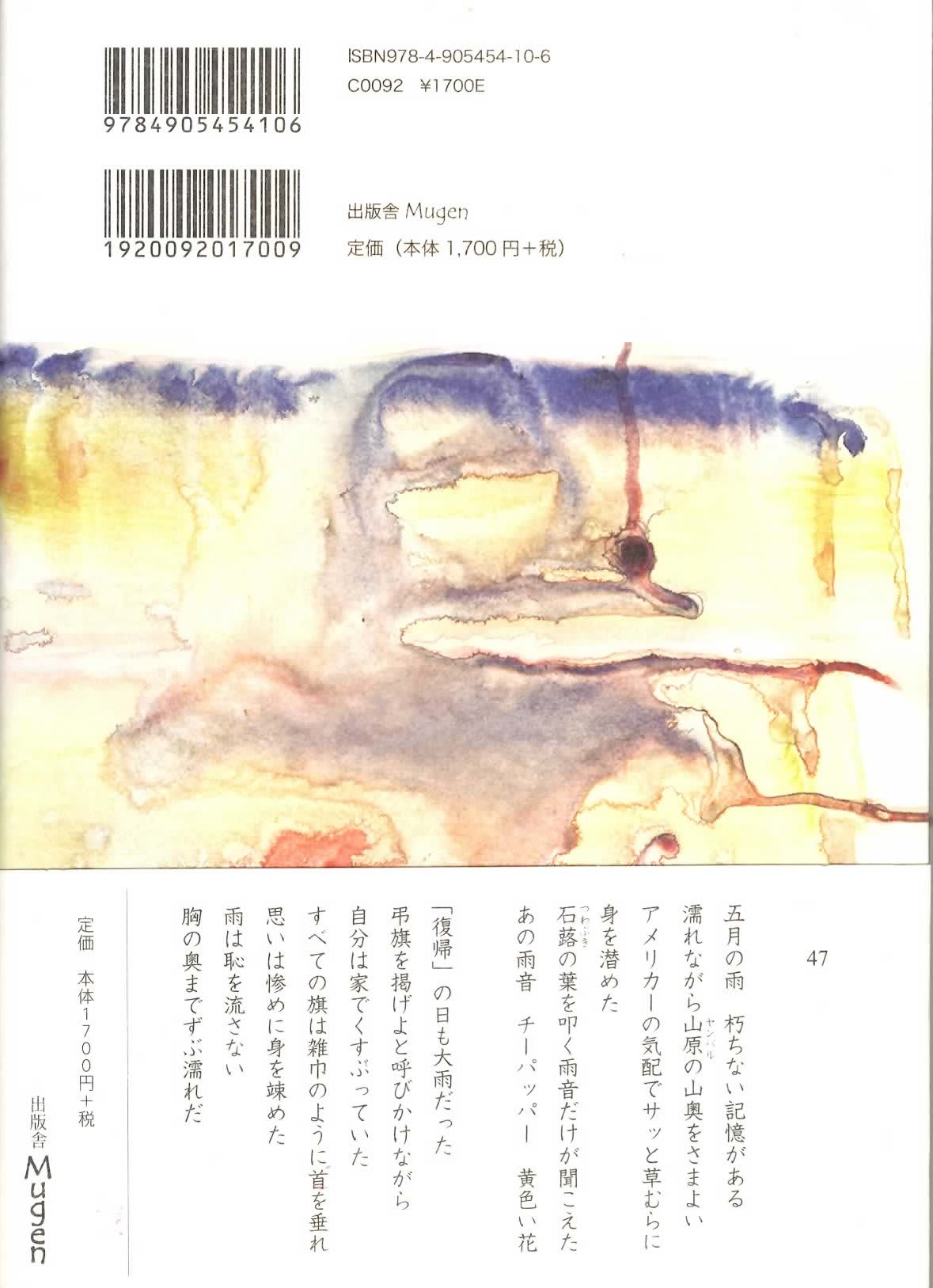

どちらかというと、短い「迷い鳥という貼り紙」のような小編が、ドキンと、迫ってきた。ウチナーグチのリズムの軽やかさがある、この「キッチャキ」の詩は、9・11を扱っていて、すんなり読ませるし、そうだね、と思う。しかし、それが表面的な憤慨なり思いだということを、私達は知ってしまった。9・11が自作・自演で、自国民(アメリカ人以外の人間も含め)を犠牲にしても、戦争をしかけたいパワー中枢の謀だったと、ネットでは「9・11の真実」が拡散している。それゆえに、もっともっと恐ろしい魔の力があり、仕組まれる世界の構図があることを、見通す目線が問われている。軽やかなリズムによる戦後沖縄の素顔が、素朴な「恨」や「復讐」「ざまーみろー」で終わっては、前に進まない。自国民を犠牲にして(殺して)はばからない刃は同じように他国の民にも向かうのである。
同じような似た構図がこの島にもあるのだ。島人を犠牲にしても自らの懐を温めたい人々が島の権力中枢に陣取っていないと、否定できない構図が張り巡らされている。ピラミッドの頂点の階層、わずか1%が99%を支配する。メディアやあらゆる表象の中で、牛耳っていく構図が成り立っている。直接民主主義の麗しいギリシャでも奴隷に支えられていた民主主義だった。今、選挙という民主主義もまた大勢の人間を洗脳し、特定な思潮へと誘導する仕組みが大手メディアでなされ続ける。その中で真実の在り処はますます、己の感性・知性に基づかざるを得ない。多様なアンテナが絶えず要求されている中で根にある文化をどうを耕し、継承していくか、たゆみない想像(創造)が問われ続ける。人は表現したい生き者だから、絶えず新しい創造がなされて行く。無常・無限の世界に歩み続ける。←詩と関係ない話になった。この『キッチャキ』はすんなり、風のように読ませる。中里さんの感性がナウイと感じさせる。戦後やがて70年、変わらない沖縄の戦後にグサッと刺される。ことばの力を思う。写真と散文詩をまとめたいと思っているが、推敲して実現したいと思っている。しかし、ことばの力の不思議に驚いている。軽やかな刃のようなイメージ。ウチナーグチの軽さのすごさがそこにあるように思えた。わたしもウチナーグチで、は厳しいかもしれない。「キッチャキ」のテーマで47編、編んだこの詩集は沖縄の批評書や評論を蹴ってしまう魅力である。
「演劇の手法、自分の考えを他人に言わせて自分に引きつけて書いているね。演劇様式の要素が身体にあるので、演劇畑の人間の感性が詩に応用されているね。トロイのニブイなど、目くらましが入っているよ。トロイ=鈍い、トロイの木馬、とかー」なるほど。
風のようにさっと読ませる詩集だ。すでに既知となった現実の共感は大きいゆえか、新しい表現・表出が常に模索されている。わたしのことばのありかーー。んんん。




















