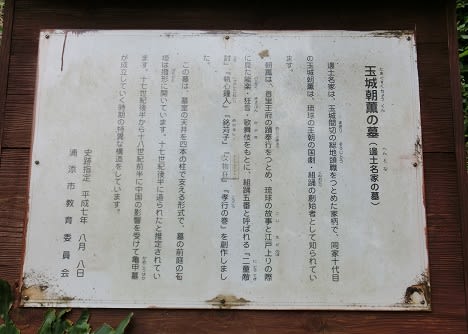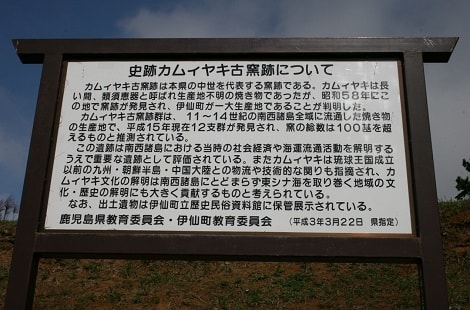首里城のハガキとセットになった切手シート

左より、今帰仁 丈 ・ 中城 条 ・ 首里 澄 ・ 勝連 穣 ・ 座喜味 常

5人の顔とグスクが載った切手シート


琉球王国の要のグスクだった首里城

三山時代、北山を統一していた今帰仁城

第一尚氏に仕えていた城作りの名人、護佐丸が築いた座喜味城

勝連英雄の八代目城主 阿麻和利の勝連城

座喜味城のあと護佐丸が治めていた中城城
ブログ 【 がじゅまるの樹の下で 】 の情報を見て、
ネットで注文していた切手シートが昨日の夕方届いた。
このシートは、グスク好きにとってはたまらない逸品である。
世界遺産になったそれぞれのグスクにちなんだイケメンアニメが、
首里城は、 首里 澄 ・ シュリジョー
今帰仁城は、 今帰仁 丈 ・ ナキジンジョー
座喜味城は、 座喜味 常 ・ ザキミジョー
勝連城は、 勝連 穣 ・ カツレンジョー
中城城は、 中城 条 ・ ナカグスクジョー
の名で、 【 沖縄世界遺産物語 】 に登場している。
『 琉球王国のグスク及び関連遺産群 』 に指定されている5つのグスク。
その中に、グスクめぐりをするきっかけとなった座喜味グスクがある。
一番最初に沖縄へ行った時に、観光の定番である首里城に行ったが、
特別な感動はなかったし、興味もなかった。
そのころ、 島唄と泡盛にハマっていて、
二度目に沖縄に行った時は、りんけんバンドの 「 カラハーイ 」 や、
ネーネーズの吉田康子さんの 「 名護ぬ前 」 などに行った時に、
読谷村にある知花昌一さんの黙認地の楚辺通信所 ( 通称・象のオリ ) を見て、
時間があったので、たまたま立ち寄った座喜味グスクに衝撃を受けた。
その当時、 「 馬の詩 」 というホームページを持っていて、
それに掲載するのにグスクめぐりを始め、
琉球の歴史を知れば知るほど、どんどんのめり込んで行った。
それは、沖縄本島だけにとどまらず、
最南端の波照間島から北限の奄美大島や喜界島にまで及んだ。
個人的には座喜味や安慶名、知念などの城門連郭式のグスクが好きで、
どのグスクも感動したが、特に感動したのは、 「 これでもか! 」 っていうくらい
急勾配の山道を登らなければならない場所に城門があり、
累々と積まれた長い城壁と井戸がある伊平屋島の田名 ( ダナ ) グスクである。