“邪馬台国の会”(安本美典氏を中心とする古代史研究会)に参加して、安本氏の「邪馬台国=福岡県朝倉」と題した講演を拝聴した。
邪馬台国は現在の福岡県朝倉に存在したという安本氏の説の根拠は次のようである。
(1) 福岡県に存在する地名と同じ地名の場所が奈良県に多数存在する
下に掲げた奈良県と福岡県の地図を見ると、同じ地名の場所が両県に数多く存在することが確認できる。その地名を次に羅列する。
上山田、山田、田原、笠置山、春日、三笠山(御笠山)、額田(野方)、住吉神社、平群池田、三井、織田(小田)、三輪、雲悌(雲堤)、大和高田(筑前高田)、朝倉、久米(久留米)、水間(三潴)、天の香山(香山)、高取山(鷹取山)、天ヶ瀬、国樔(玖珠)


福岡県朝倉市周辺略図
(上の2件の地図は、安本氏の講演において配布された資料から拝借したもの)
これらの場所は中心の朝倉から見てみな同じような位置に存在するが、これは偶然ではありえない。大きな集団が北九州から大和に移住した事実を示すと考えるべきである。米国のNew York は英国のYorkから移住した人々が作った都市であるのと同じことである。
(2) 福岡県朝倉市の平塚川沿いに大規模集落の址が発見された(1992年)
この遺跡は有名な佐賀県の吉野ケ里遺跡と同規模で、弥生時代後期(1世紀~3世紀)のものと推定されている。
(3) 九州で箱式石棺がもっとも多く発見されているのは福岡県朝倉市
2世紀後半から3世紀すなわち弥生後期になると、支石墓や甕棺はなくなり、箱式石棺が普遍的になる。その箱式石棺がもっとも多く発見されているのが朝倉市である。
(4) 鉄製武器が多く出土しているのは福岡県朝倉市
魏志倭人伝に記載されている鉄製武器(鏃、刀、矛)が、福岡県朝倉市で33個出土しているが、その次に多いのが10個出土している岡山県倉敷市で、奈良県桜井市(纏向遺跡)では全く出土していない。
(5) 卑弥呼とは天照大神のこと
実在が確認されている第31代用明天皇から後の5~8世紀の天皇の在位年数は平均10.88年。ちなみに、中国の同時代の王の平均在位年数は10.18年。この平均在位年数を昔に遡ると、神武天皇は280-290年に活躍したことになる。そこからさらに3代遡ると天照大神の時代になり、卑弥呼が活躍した時代に一致する。したがって、卑弥呼(248~249年没)と天照大神は同一人物であると考えられる。
邪馬台国の場所については数多くの説があり、みなそれなりに説得力があるが、私(頑固爺)は安本氏の“福岡県朝倉説”に軍配を上げる。理由は、他の説に比べて、根拠がより具体的であることである。










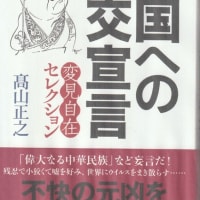








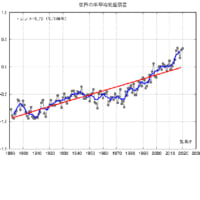
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます