(3) 米国のコメの種類別内訳
過去5年間における米国のコメ生産量は下記のようである(出所:World Markets and Trade)。
2007/8 6,288 千トン
2008/9 6,546
2009/10 7,133
2010/11 7,554
2011/12 6,001
平均 6,704 千トン
一方、Rice Yearbook (Table 6) によると、種類別内訳の過去5年の平均はインディカ米(長粒種)が71.3%、ジャポニカ米の中粒種が27.1%、ジャポニカ米の短粒種が1.6%であった。この二つを組み合わせて、過去5年間の種類別内訳は次のようになる。
インディカ米―長粒種: 4,780 千トン (71.3%)
ジャポニカ米―中粒種: 1,817 千トン (27.1%)
短粒種: 107 千トン (1.6%) 合計6,704千トン
中粒種には前述のように、カルローズ米とそれを日本人の好みに合うように品種改良した特選米があるが、その内訳を示す統計資料は存在しない。私は以前業界に関与していた頃、特選米は中粒米の2割から3割と聞いていたので、36万トン乃至55万トンと推定する。
これを別の角度から検証してみる。特選米はカルローズ米よりも価格が高いので、そのほとんどが日系市場で消費される。その日系市場はジャパニーズ(日系人および在留邦人)の家庭用、日本食レストラン業界向けの業務用、および輸出(おもに欧州・中南米の日本食レストラン業界向け)から成り立っている。
米国におけるジャパニーズの人口は現在約80万人程度だから、日本における人口と消費量の比率から考えて家庭用は5万トン程度だろう。そして、日本食レストラン業界(客はほとんどが非ジャパニーズである)の規模はその5倍として25万トン。これに輸出が10万トンとして合計40万トン。この数字は上述の推定36万トン~55万トンの中に収まるので、本稿では中粒米の1,817千トンのうちの400千トンを特選米とし、残りの1,417千トンをカルローズ米と仮定して論を進める。
もう一度、全生産量を種類別に整理すると次のようになる。
インディカ米―長粒種: 4,780 千トン (71%)
ジャポニカ米―カルローズ米: 1,417千トン (21%)
特選米: 400千トン (6%)
超特選米: 107千トン (2%)
全体像を次の円グラフで把握していただきたい。

では、関税ゼロで自由化された場合、日本が輸入できるのはどのくらいか。
生産者は売れる見込みがある数量しか作らないから、予想外の豊作でもないかぎり、生産物が余ることはない。7月(コメ年度の最終月)末の繰り越し在庫を調べてみると、少ない年で年間消費量(国内および輸出)の1.5ヵ月分、多い年で2.3ヵ月分で推移している。新米が実際に市場に出回るのは8月だから、7月末には最低1ヵ月の在庫が必要であり、繰り越し在庫が1.5ヵ月とは非常に低い水準である。要するに、需要と供給はほぼ均衡しており、注文生産に近い状況と考えていい。
特選米の主たるユーザーは日本食業界だが、コメは日系食品問屋(JFC、共同貿易、西本貿易など)の主力商品であり、かれらはコメの生産者に強い発言力があるから、生産者が日本食業界への供給を削減することはできない。一方、日本の輸入業者は高値で集荷しようとするから、そこで相場の高騰が発生し、生産者は翌年の生産量を増やすだろう。問題はどれだけ増産できるかである。
一方、カルローズ米の主たる用途はビールの副原料、日本酒㊟の主原料、および一部の家庭用と業務用で、この業界も供給削減には応じられないが、生産量が特選米よりも格段に多いから、日本の輸入業者は一定の数量は集荷できるだろう。しかし、このコメの日本における市場性は未知数である。
㊟ 米国では月桂冠、大関、宝酒造など5社の清酒現地生産が行われており、国内販売だけでなく、欧州・中南米などに輸出されている。原料はもちろん米国産のコメである。










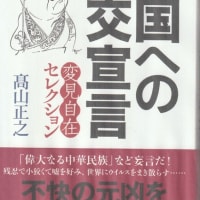








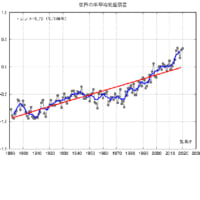
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます