九州王朝実在説を唱えるのは古田武彦氏ばかりではない。知名度はあまり高くないが、青木一参(かずみ)氏もその著書『記紀にいなかった卑弥呼』(平成8年10月 東洋出版)において、独自の九州王朝実在説を展開している。
4世紀に北方騎馬民族が半島南部海岸地帯の倭人居住地に建国した金官加耶が日本列島に侵攻、西の邪馬台国、東の出雲王朝を攻略して、それぞれの国に皇子を派遣し、邪馬台国のあとに貴国㊟、出雲王朝のあとにニギハヤヒ王朝を建国した。その後間もなく、ニギハヤヒ王朝は本国の方針に従わず現地人と混血したので、応神天皇がこれを成敗して、大和朝廷に衣替えした。すなわち、応神が初代天皇である。
注 「貴国」は百済記367年、382年、397年、414年、476年に登場し、『記』にも引用されている。場所は北九州の基山のあたり。
5世紀のはじめに、金官加耶は都を半島の金海から海を渡って、貴国の都大宰府に移し、倭国と名乗った。混乱を招かぬよう、この倭国を私は九州王朝と呼ぶことにする。5世紀に中国に朝貢した「倭の五王」とは、この九州王朝の王たちである。
それまでは九州王朝は大和朝廷よりも上位にあったが、その体制が磐井の乱(527年)で崩れた。磐井の乱は、『記』では九州の一豪族が謀反を起こし、それを大和朝廷が鎮圧したことになっているが、事実は逆で大和朝廷が九州王朝に謀反し、その王を殺害した事件だった。『百済記』には「日本では天皇、皇太子、皇子が同時に亡くなった」と記述しており、『記』も「注」にこの記述を引用しているが、事実は九州王朝の王イワイとその皇太子、皇子が大和朝廷によって殺されたのである。しかし、その皇子の一人「筑紫の君クズコ」は北九州の穀倉地帯を大和朝廷に献上することで命乞いして助かった。
有名な白村江の戦い(663年)では、倭国は百済に援軍を出して唐・新羅の連合軍と戦い惨敗したが、この時の倭国とは九州王朝だった。唐は大和朝廷と裏で手を組んで、日本を分断していたのである。戦後、唐・新羅は九州に進駐し、長い間滞在していた。この時、大和朝廷は旧領土を安堵され、九州王朝の領土の併合も認められた。これが、中国の史書『旧唐書』の倭国日本伝に「あるいはいう、日本はもと小国、倭国の地を併せたり」とある背景である。
白村江の戦いで唐の捕虜となった九州王朝の王サチヤマ(『記』にも登場する)は天智天皇の9年(670年)に唐から脱出し、大和朝廷を倒す準備をしていたが、天智天皇が天智10年(671年)に亡くなったとき、兵を挙げた。これが壬申の乱で、勝利した天武天皇とは、実は九州王朝最後の大王サチヤマだったのである。
さて、大和朝廷の遣唐使だった伊吉連博徳の報告書(『記』に引用されている)によれば、「大和朝廷側の遣唐使と九州王朝側の遣唐使が、唐に滞在していた時に互いに中傷しあって、ともに牢獄に幽閉された」という事件があった。そして、唐から帰国した人々の名を挙げているが、そこに「別に倭種韓智興、趙元宝も今年(天智4年)遣唐使節団ともに帰国した」という記述がある(韓智興と趙元宝はともに九州王朝の外交官の中国名)。「別に倭種」とは、大和朝廷からの派遣ではなく、九州王朝から派遣された人々を意味する表現だった。
すなわち、大和朝廷と九州王朝は並列して存在していたのである。
『記』には天智天皇の在位後半から天武天皇、持統天皇時代まで、毎年新羅が大和朝廷に朝貢し、その接待が筑紫で行われたという記述があるが、戦勝国の新羅が大和朝廷に毎年のように朝貢したとは不自然な話である。実際には新羅の進駐軍が筑紫に滞在していたのである。
その証拠は、考古学の見地からは、北九州のいくつかの寺院跡から出土する新羅系デザインの屋根を飾る丸瓦と平瓦である。そのデザインが7世紀後半の新羅のものであることから、新羅が華麗な大伽藍を建てて、現地人を威圧し、占領軍の威厳を示したのではないか。
また522年から698年まで続いた九州年号は、新羅が九州王朝を引き継いだことを示すのではないか。もう一つの証拠は、日本各地で出土する「評」と記された木簡である。大和朝廷の地方行政単位は「郡」であるが、木簡は「郡」以前に「評」という地方行政単位があったことを意味する。699年を示す「評」の木簡が藤原宮跡から出土したが、これは大宝律令がスタートした701年と符合する。
さて、壬申の乱で天武天皇になりすましたサチヤマは、その事実を唐・新羅に知られることはなんとかして避けたかった。さらに、日本に二つの政権が存在したことが唐・新羅につけこまれ、九州王朝の滅亡をもたらしたことも考えると、強力は統一政権が存在する理論武装が必要だった。そこで浮かび上がったことは、大王は神であり、なんびともその地位を冒すことができない絶対者であるという思想であった。それが『記紀』編纂の動機であって、九州王朝は抹殺されるか、その事跡を大和朝廷のもとしてすり替えることが必要だったのである。
青木説はかなりつじつまが合っているが、私は二つの矛盾点があると考える。
(1) 磐井の乱から白村江の戦いまで140年経過しているが、九州王朝の勢力はかなり弱まっていたのではなかろうか。さらに、唐と大和朝廷が組んでいたことが事実なら、大和朝廷は九州王朝の出陣の邪魔をするよう唐から要請されなかったのだろうか。九州王朝が数万の大軍を白村江に投入することができたのは不思議である。
(2) 大和朝廷が裏で唐・新羅を組んでいたのなら、白村江で敗れた後、「大和朝廷は唐の来襲を恐れて都を内陸の大津に移し、山陰・北九州に防塁を築いた」という通説はどう説明するのか。










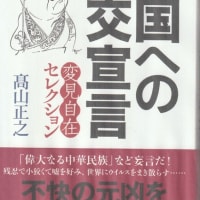








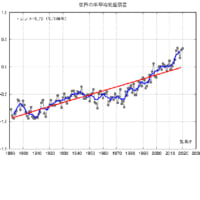
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます