今から20年ほど前、私がロサンゼルスで「フード業界USA」というタイトルの業界紙(日本語・英語の逐語訳)を主宰していた時の話。
某日系ビール会社(A社とする)が新発売したビールの紹介記事を掲載することになった。その新商品のラベルには「生」とDraftという文字があるので、これに焦点を合せようと考えた。当時、日本ではビン入り生ビールは珍しくなかったが、日本人ではない日本食レストラン経営者には興味深い話題のはずである。
ここで生ビールの製法について簡単に説明しておく。ビールは大麦の麦芽を酵母の力によってアルコール発酵させて作る。液体に酵母が残っていると2~3カ月で品質劣化が起きるので、長期保存するには、加熱処理を施すかマイクロフィルターで濾過して酵母を除去しなくてはならない。その後者がビン入りの生ビールである。
さて、原稿を書き始めて、「生」イコールdraftではないことに気付いた。英和辞典を見ると、draftには「下書き」、「草案」、「徴兵制度」、「(野球などの)ドラフト制度」、「すきま風」、「樽から出した(ビール)」など、一見脈絡がない訳語が並んでいるが、ビールの属性を示す訳語は「樽から出した」である。そしてA社のビールは言うまでもなくビン入りで、「樽」とは無関係だからラベルにあるdraftと矛盾する。これをどう説明するか。それはともかく、アメリカ人はdraftに「樽出し」という意味があることを知っているのか。
もう一つ問題がある。日本人は「生」に価値を感じる。生ビールはもちろん、生魚(つまり刺身)、生野菜、生湯葉、生ハム、生卵、生麺など。さらに、生放送、生出演など、食べ物以外でも使われる。だから、日本のビールメーカーは「生」ビールと呼びたいがために、加熱しない酵母除去システムを開発したのだろう。一方、日本語の「生」に当たる英語のrawには「加熱してないから不衛生」というニュアンスがあり、draft beer の紹介文にrawという単語は使えない。
しかも、A社に、加熱処理しないビールは、加熱処理したビールより美味しいのかと聞いてみると、「同じ銘柄で加熱処理したものはないので、較べられない」という歯切れが悪い答えが返ってきた。
それではアメリカ人に「生」をアピールすることは不可能。結局、新商品の紹介記事はdraft には触れずに済ませた。
当時、米国にもMiller Genuine Draftというdraft beer があったものの、draftという単語はあまり一般的ではなかったと思う。私は「なぜgenuine(本物)という文字が入っているのか。 Genuineではないdraft beerがあるのか」という疑問を持った。

ロサンゼルスの郊外、トーランス市の中心地にClaim Jumperという大型レストランがあり、私はそこにある大きなバーをよく利用していた。ある時、カウンターの内側に銘柄別のレバー(引手)が数本あり、バーテンがそのレバーを引いて蛇口からビールを出し、ジョッキに注いでいるのを見た。大型容器に入ったビールがカウンターの下に置いてあるらしい。「これはdraft beerかな」と思い、バーテンに“Is it draft beer?”と尋ねると、“No, tap beer.”という。Tapとは蛇口とか栓と言う意味で、tap waterといえば水道水。口ぶりからして、そのバーテンはdraft beer とは何だか知らないらしい。そこで会話は終わったが、draft beerはプロにとっても日常的単語ではないことはわかった。
話が後先になるが、日本には1950年代にビアホールがあちこちにあり、そこでは生ビールが人気を呼んでいた。工場直送という触れ込みだったから、酵母が入ったままのビールだったのだろう。その「生」人気をビン入りビールに取り込んだのが、1967年にサントリーが開発した「純生」である。他社は「酵母を除去したビールは生と呼べない」と批判したが、1979年に公正取引委員会がサントリーの言い分を認めたことで論争は決着し、他社も一斉に追従して「生」ビール戦争が勃発した。その頂点がアサヒの「生No.1、アサヒスーパードライ」で、空前のヒット商品となり、アサヒは出荷量において一時業界トップに躍り出た。それ以降、日本のビールのほとんどが「生」になった(例外はキリンラガーなどごく少数)。
2002年にキリンが「まろやか酵母」というビールを売り出した。その名の通り、酵母を除去しないビールだが、あまり評判にはならず、数年で消えた。消費者は「生」には好感したが、「酵母」となるとあまりにもアカデミックで、親近感を持てなかったのではないか。
さて、私の著作「アメリカ日本食ウォーズ」(2005年刊)の生ビールに関する章「生ビールを知らないアメリカ人」に次のような一節がある。

Draft beerを日本語に訳したとき、直訳すれば「樽出しビール」になったはずだが、加熱殺菌していないところから、「生」と意訳したのだろう。
当時、私はビン入り「生」ビールは米国で先に開発され、日本のメーカーはその真似をしたとばかり思っていたが、最近になって事実は逆であることに気付いた。
米国における「生ビール」開発の経緯は次のようである。
Miller は1986年にサッポロの技術供与により、加熱しない酵母除去装置を導入した。これは米国産「生」ビールを対日輸出するプロジェクトだったらしいが、詳しいことはわからない。Miller はその装置を国内向けにも使用して、Miller Genuine Draftを開発したのである。当時、アサヒに「本生」という商品があり、Millerは「本」をgenuineと訳したと思われる。拙著の記述はとんでもない間違いで、赤面の至りである。
では、ビールの本場の欧州ではどうなのか。ドイツに駐在したことがある友人数人に聞いてみると、異口同音にドイツではジョッキに注がれたビールは樽から注がれたものであることは当然で、そんなことを考えること自体がナンセンスだという。そして、ビン・缶入りのdraft beerは存在しないし、そもそも英語のdraftと意味が似たドイツ語の単語はあっても、それには「樽出し」という意味はないことがわかった。
英和辞書に「樽出し」という訳語があるので惑わされたが、draftの原義は「素材」とか「原型」ではなかろうか。それならば、「下書き」、「草案」、「ドラフト制度」、「徴兵制度」、「樽出し」の根っこは共通だ。つまり、英語のdraft beer とは「造りたてをそのまま樽詰めしたビール」と解釈していいだろう。それならば、酵母を除去する工程があるとdraft beerと呼ぶにはやや無理があり、その後ろめたさを補うために、genuineという形容詞を入れたのではないか。「純生」も「本生」も同様である。
では、日本には欧州式ビール(つまり厳正な意味での生ビール)を製造する醸造所は存在するのか。酵母を除去する装置が不要であれば、設備投資が少なくて済むから、地ビールに適しているのではないか。そう考えて、ネットで「地ビール」を検索してみると、「酵母が生きている」ことをウリにする地ビールは見つからない。
こうして思考を進めてくると、大きな疑問に突き当たる。それは「われわれが飲食店で飲む『生』ビールは、ビン入り生ビールと同じものではないのか」である。調べればわかるだろうが、知らないままでいる方がいいのかも知れぬ。
たががビール、あまり難しく考えず、美味しく、気分よく、飲めればそれで十分ということにしておく。










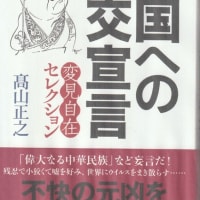








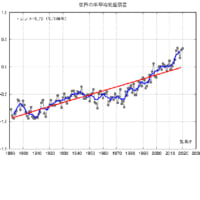
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます