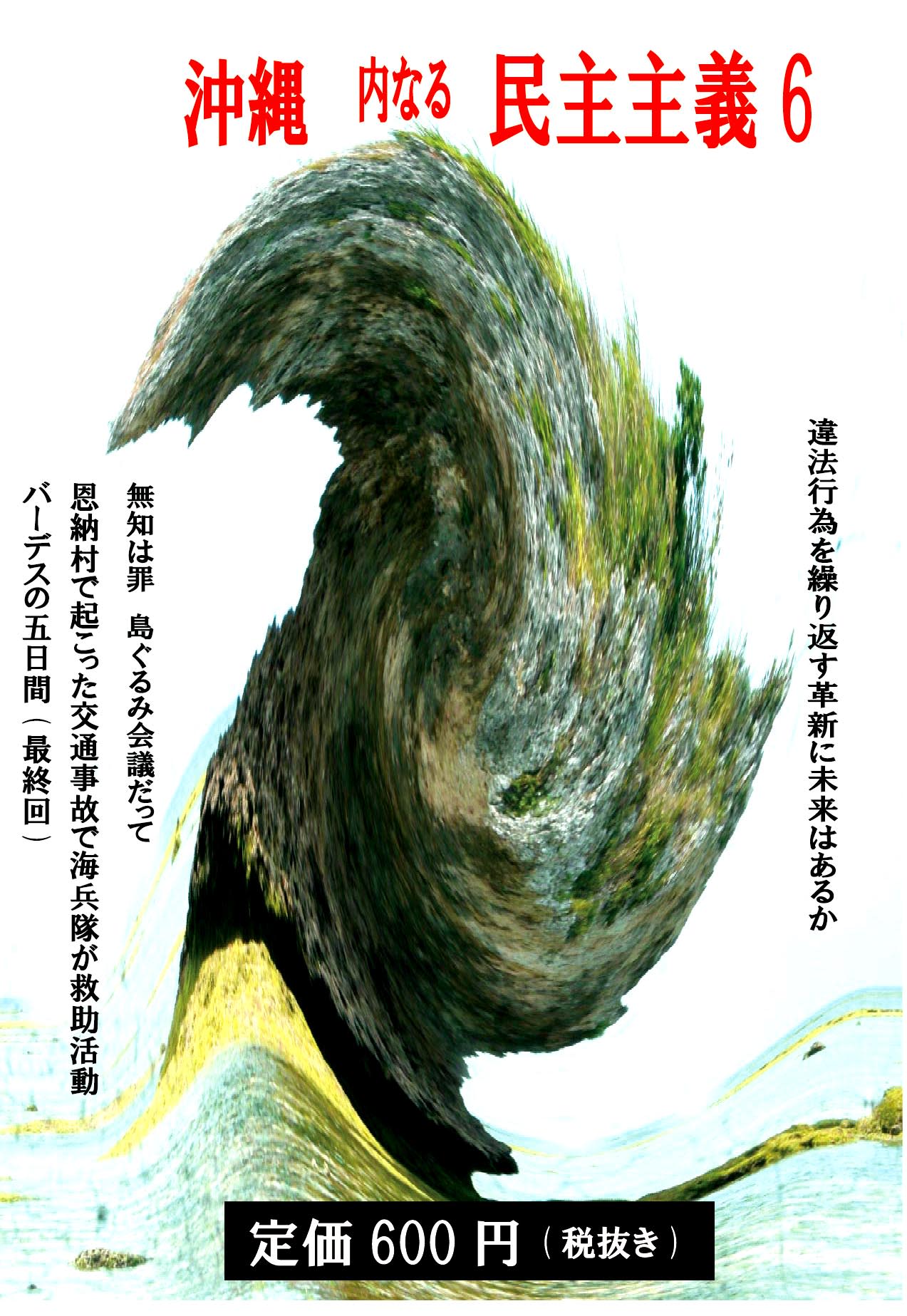よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
米中、香港デモで応酬 オバマ氏「情勢注視」(2014.10.2) ![]()
抗議運動の平和的な収拾への期待も表明した。
米中間で「新しいタイプの大国関係」を模索するなか、中国が「内政干渉」と反発する問題にあえて言及し、人権や民主主義を重んじる米国の原則を譲らない方針を伝えたとみられる。
オバマ氏は、ホワイトハウスで行われた王外相とライス大統領補佐官(国家安全保障担当)の会談で発言した。大統領が他国の外相レベルの会談に同席するのは異例。ホワイトハウスによると、オバマ氏とライス氏は「米国は香港の情勢を注視している」と指摘し、「香港の安定や繁栄に不可欠な開かれた社会システムを米国は常に支持する」との立場を表明した。
これに先立ち、ケリー米国務長官も王氏と会談。冒頭で「我々は香港基本法に基づく普通選挙を支持する」と述べた。中国外務省によると、一連の会談で王氏は「完全に中国の内政であり、外部の勢力が干渉する権利はない」と反論した。
1932年5月15日、海軍青年将校と陸軍士官候補生の一団が永田町の首相官邸を襲撃した。
老首相犬養毅は、「話せばわかる」と青年将校を制した。
だが、「問答無用」の一声と共に射殺された。
「話せばわかる」は、議会制民主主義の本質を端的に表現した言葉だということができる。
その一方、「問答無用」は言論の否定であり議会制民主主義の否定も意味する。
5・15事件が日本の政治史上、重大な意味を持つといわれる理由は、議会制民主主義の事実上の終焉を意味するからだ。
この事件によって戦前の政党政治が事実上終止符を打ち、それ以降の敗戦までの13年間、政党の党首が首相になることは二度となかった。
議会制民主主義を否定し共産党による一党独裁を国是とする中国に対し、沖縄タイムスが「まず対話の場をつくれ」などと寝言のような社説を書いた。
この社説をまじめな気持ちで書いたとしたら沖縄タイムスの記者は自分がバカであることを公表したようなもの。
法を踏みにじり恫喝を生業(なりわい)とするヤクザ国家に順法精神を説くようなものだから。
社説[香港・抗議行動]まずは対話の場つくれ
一国二制度の「高度な自治」が認められている香港で、次期行政長官選挙の制度改革案に反発する市民・学生らが、大規模な抗議行動を続けている。
1日は、中国の建国記念日にあたる国慶節。市民・学生らは国慶節を祝う式典会場周辺に押し寄せ、「香港に真の普通選挙を」と書いた横断幕を掲げ抗議を繰り返した。
市民・学生らの占拠拠点は、行動開始を宣言した9月28日以降、日を追うごとに広がり、九竜地区を含め4カ所に拡大したという。
行政長官は香港特別行政区のトップ。これまでは1200人の選挙委員会メンバーによる間接選挙で選んでいた。全国人民代表大会(全人代)常務委員会は8月末、2017年に実施される行政長官選挙の制度改革案を発表し、普通選挙を導入することを明らかにした。
間接選挙をやめ、1人1票の普通選挙に改めるということは、間接選挙に比べ大きな前進のように見える。しかし、中身は業界団体などから選ばれた指名委員会があらかじめ候補者を2~3人に絞るという仕組みで、誰でも立候補できるというわけではない。
指名委員会のメンバー選びに中国側の意向が強く働くのは確実で、民主派は事実上、立候補すらできない-と学生らは主張する。香港の「高度な自治」の内実が揺らいでいるのである。
民主派が「真の普通選挙」を求めるのは当然の成り行きだ。これに強権的に対処するようなことがあってはならない。
■ ■
1997年の香港返還にあたって香港特別行政区基本法が制定され、「高度な自治」
の名の下で一国二制度の運用が開始された。
今回の行政長官選挙をめぐる大規模な抗議行動で浮き彫りになったのは、一国二制度に基づく高度な自治が具体的に何を指すのかがあいまいで、中国政府の解釈と運用次第では、その中身が空洞化する可能性があることだ。
習近平国家主席は最近、「一国二制度」による平和的な統一が中台統一の最も良い方法だと語ったといわれる(9月27日付朝日新聞)。
行政長官選挙問題に対する台湾の関心は高い。中国政府の今後の対応によっては、中国政府に対する台湾の人々の心理的な警戒心を高める結果にもなりかねない。
実際、台湾では3月、中国とのサービス貿易協定に反発する学生らが、23日間にわたって立法院(国会に相当)を占拠したばかりである。
■ ■
中国政府も香港政府も今のところ、制度改革案を撤回する気はなさそうだ。香港政府の梁振英行政長官は「全人代の決定を受け入れることが対話の前提」だと主張する。
対話を求める市民・学生にとって、制度改革案の丸のみは受け入れがたく、道路占拠や抗議行動が長期化するおそれもある。
こうした事態は、国内治安対策の観点から言論や思想を統制し、民主化の動きを上から力で抑え込むだけでは解決しない。慎重な対応を中国政府に求めたい。
☆
>一国二制度の「高度な自治」が認められている香港で、次期行政長官選挙の制度改革案に反発する市民・学生らが、大規模な抗議行動を続けている。
本気で香港で高度な自治の一国二制度を認められると信じているとしたら、沖縄タイムスはやはりバカだ。
英国から返還されたとき中国は「不渡り手形」を英国と香港住民に渡した。
英国からの返還時に導入された香港基本法が「最終的に普通選挙を取り入れる」としていう約束をしたのだ。
ところが今回中国は、2017年の行政長官選挙から民主派の候補を排除した中国全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会の決定を実行すると発表した。
ヤクザ国家が「高度な自治」を認める民主的制度を認めるはずはない。
>今回の行政長官選挙をめぐる大規模な抗議行動で浮き彫りになったのは、一国二制度に基づく高度な自治が具体的に何を指すのかがあいまいで、中国政府の解釈と運用次第では、その中身が空洞化する可能性があることだ。
社説は中国が法治国家と信じているような書き方だが、中国は憲法でさえも「中国政府の解釈と運用次第では、その中身が空洞化」する人治国家、いや、ヤクザ国家である。
中国は憲法を有するが空洞化しており、見かけだけの法治国家という認識が沖縄タイムスには欠落している。
>習近平国家主席は最近、「一国二制度」による平和的な統一が中台統一の最も良い方法だと語ったといわれる(9月27日付朝日新聞)。
これを民主主義国家では「不渡り手形」という。
どんな法律や約束事も、中国政府の解釈と運用次第では、その中身が空洞化する。
これが共産党一党独裁の中国政府の国民統治の手段だ。
>中国政府も香港政府も今のところ、制度改革案を撤回する気はなさそうだ。香港政府の梁振英行政長官は「全人代の決定を受け入れることが対話の前提」だと主張する。
対話の前提に自分の決定を受け入れることを条件付けするのが中国式対話の常套手段。
裏を返せば自分の言うことを聞かないヤツとは話し合いを拒否する。
これが中国の正体である。
>こうした事態は、国内治安対策の観点から言論や思想を統制し、民主化の動きを上から力で抑え込むだけでは解決しない。慎重な対応を中国政府に求めたい。
言論や思想を統制し、民主化の動きを上から力で抑え込むことで世界第2の超大国にのし上がった中国に対し、それをやめろと要求することは、中国という国自体を解体せよと要求するに等しい。
沖縄タイムスに告ぐ。
ヤクザ集団を解体させる手段は平和的対話ではなく、重武装した警察力による強力な締め付け以外に手段はない、という事実に気が付くべきだ。
■「話せばわかる」と「バカの壁」
「イタズラ小僧と父親、イスラム原理主義者と 米国、若者と老人は、
なぜ互いに話が通じないのか。そこに「バカの壁」が立ちはだかっているからである。」
これは、ふた昔まえのベストセラー養老猛司著「バカの壁」の「まえがき」の一節である。
国家間であれ、会社、家族、個人間であれ、戦争、喧嘩等の争いごと耐えないのが人間社会の常であるが、お互いに話し合いによる平和的解決を主張しても、お互いが理解しあえるのは困難である。
戦争、紛争,諍いが起きる理由は対話の欠如により、 相互理解が不足しているからだと考えがちだが、事実はそんな単純なものではない。
人類の歴史は戦争の歴史、といわれるほど諍いの種は尽きないからだ。
養老猛司著『バカの壁』によると、人間とは「話せば分かる」ものではない、というのが現実で 、同書の帯紙には「『話せば分かる』なんて大ウソ!」と書かれている。
書店向けPOP広告には「バカの壁は誰にでもある」という著者の言葉が記された。
「人間同士が理解しあうというのは根本的には不可能である。理解できない相手を、人は互いにバカだと思う」というのが同書の要点である。
養老先生によると一党独裁の中国と民主化を求める学生の間には越えることの出来ない「バカの壁」が有ることになる。
それに気が付かずに「対話を求める」沖縄タイムスは、やはり本物の大バカものだ!
 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします