14日(水)。わが家に来てから今日で2286日目を迎え、バイデン政権が法人税を現行の21%から28%に引き上げることを検討していることに対し、米経営者団体のビジネス・ラウンドテーブルは12日、企業経営者の98%が「競争力の低下につながる」と回答したという調査結果を発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプ政権が税率を35%から21%に引き下げていたから 元に戻すに過ぎない





昨日、夕食に「鮭のバター焼き」「マグロの山掛け」「生野菜とアボカドのサラダ」「キャベツの味噌汁」を作りました 魚を出来るだけ食べなければ、と思います
魚を出来るだけ食べなければ、と思います






前日に続いて昨夜、東京文化会館小ホールで東京・春・音楽祭「都響メンバーで聴く室内楽」を聴きました プログラムは①ドヴォルザーク「2つのワルツ作品54」(イ長調、ニ短調:弦楽五重奏版)、②同「弦楽五重奏曲第2番 ト長調 作品77」、③R.シュトラウス:歌劇「カプリッチョ」前奏、④同「メタモルフォーゼン(変容)」(R.レオポルト編/弦楽七重奏版)です
プログラムは①ドヴォルザーク「2つのワルツ作品54」(イ長調、ニ短調:弦楽五重奏版)、②同「弦楽五重奏曲第2番 ト長調 作品77」、③R.シュトラウス:歌劇「カプリッチョ」前奏、④同「メタモルフォーゼン(変容)」(R.レオポルト編/弦楽七重奏版)です 演奏は、ヴァイオリン=山本友重、及川博史、ヴィオラ=鈴木学、石田砂樹、チェロ=清水詩織、森山京介、コントラバス=池松宏です
演奏は、ヴァイオリン=山本友重、及川博史、ヴィオラ=鈴木学、石田砂樹、チェロ=清水詩織、森山京介、コントラバス=池松宏です
自席はD21番、センターブロック左から2つ目です。会場は市松模様です 昨日と比べてお客さんの入りが極めて寂しい状況で、後方ブロックはスカスカです
昨日と比べてお客さんの入りが極めて寂しい状況で、後方ブロックはスカスカです 私見ではプログラミングの問題かと思います
私見ではプログラミングの問題かと思います
1曲目はドヴォルザーク「8つのワルツ 作品54」から第1番(イ長調)、第7番(ニ短調)を弦楽五重奏用に編曲した作品です 原曲はアントニン・ドヴォルザーク(1841‐1904)が1879年から翌80年にかけて作曲しました
原曲はアントニン・ドヴォルザーク(1841‐1904)が1879年から翌80年にかけて作曲しました
それぞれ短い曲ですが、ドヴォルザークらしいメロディーに溢れた作品で、第1ヴァイオリンの山本氏を中心に男性奏者6人により温かみのある演奏を展開しました
2曲目はドヴォルザーク「弦楽五重奏曲第2番 ト長調 作品77」です この曲はドヴォルザークが1875年に作曲、翌76年にプラハで初演されました
この曲はドヴォルザークが1875年に作曲、翌76年にプラハで初演されました 第1楽章「アレグロ・コン・フォーコ」、第2楽章「スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第3楽章「ポコ・アンダンテ」、第4楽章「アレグロ・アッサイ」から成ります
第1楽章「アレグロ・コン・フォーコ」、第2楽章「スケルツォ:アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第3楽章「ポコ・アンダンテ」、第4楽章「アレグロ・アッサイ」から成ります
どの楽章もドヴォルザークらしい歌心に溢れた曲想で、時にスラブ舞曲を彷彿とさせる音楽作りに惹き込まれます 特に印象に残ったのは第2楽章のスケルツォです
特に印象に残ったのは第2楽章のスケルツォです 斬り込みの鋭い演奏と哀愁を誘うメロディーの対比に心を奪われます
斬り込みの鋭い演奏と哀愁を誘うメロディーの対比に心を奪われます
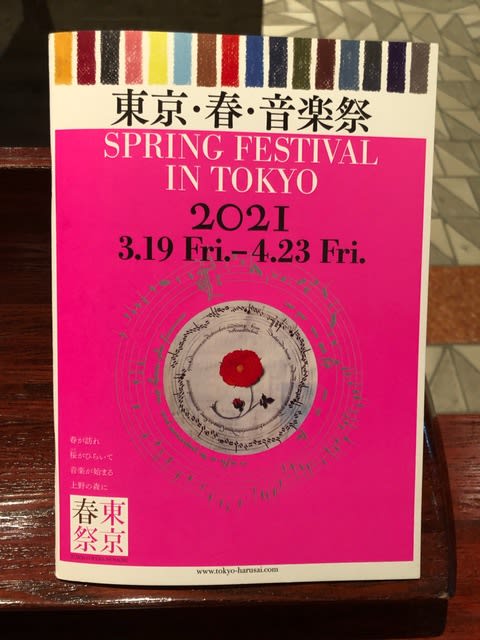
プログラム後半の1曲目はR.シュトラウス:歌劇「カプリッチョ」前奏です この曲はリヒャルト・シュトラウス(1864‐1949)が1940年から翌41年にかけて作曲、1942年にミュンヘンで初演された作曲者最後のオペラの前奏部分で、オペラの冒頭、舞台上で演奏される弦楽六重奏曲です
この曲はリヒャルト・シュトラウス(1864‐1949)が1940年から翌41年にかけて作曲、1942年にミュンヘンで初演された作曲者最後のオペラの前奏部分で、オペラの冒頭、舞台上で演奏される弦楽六重奏曲です なお、このオペラはサリエリの歌劇「まずは音楽、それから言葉」のパロディ―と言われています
なお、このオペラはサリエリの歌劇「まずは音楽、それから言葉」のパロディ―と言われています
この曲ではコントラバスの池松氏が外れ、ヴィオラの石田砂樹とチェロの清水詩織が加わります。やっぱり女性が加わると華やかでいいですね
山本氏の合図で演奏に入りますが、一気にリヒャルト・シュトラウスの世界に引き込む渾身の演奏は流石です あっという間にリヒャルト・シュトラウスの音になっています
あっという間にリヒャルト・シュトラウスの音になっています 弦楽合奏だけで色彩感溢れる演奏が出来るのは見事と言うしかありません
弦楽合奏だけで色彩感溢れる演奏が出来るのは見事と言うしかありません
最後の曲はR.シュトラウス「メタモルフォーゼン(変容)」(R.レオポルト編/弦楽七重奏版)です この曲はリヒャルト・シュトラウスが1944年から翌45年にかけて作曲、1946年にチューリヒで初演された「23の独奏弦楽器のための習作」をR.レオポルトが弦楽七重奏版に編曲したものです
この曲はリヒャルト・シュトラウスが1944年から翌45年にかけて作曲、1946年にチューリヒで初演された「23の独奏弦楽器のための習作」をR.レオポルトが弦楽七重奏版に編曲したものです
この曲は出場者が全員参加します 山本氏の合図で演奏に入りますが、冒頭の音楽はベートーヴェン「交響曲第3番”英雄”」の第2楽章「葬送行進曲」の冒頭4小節を動機としています
山本氏の合図で演奏に入りますが、冒頭の音楽はベートーヴェン「交響曲第3番”英雄”」の第2楽章「葬送行進曲」の冒頭4小節を動機としています この動機が、さまざまに変容(メタモルフォーゼン)して音楽が展開します
この動機が、さまざまに変容(メタモルフォーゼン)して音楽が展開します 聴く側は、さまざまに変化する音楽に身をゆだねるしかありません
聴く側は、さまざまに変化する音楽に身をゆだねるしかありません 7人の渾身のアンサンブルが見事です
7人の渾身のアンサンブルが見事です 演奏を聴いて、なぜ作曲者がわざわざ「独奏弦楽器のための習作」とサブタイトルを付けたか、その意味が分かるような気がしました
演奏を聴いて、なぜ作曲者がわざわざ「独奏弦楽器のための習作」とサブタイトルを付けたか、その意味が分かるような気がしました 一人一人の演奏者がソリストとなって技巧を凝らし、その上で他の奏者との間合いを図りながら極上のアンサンブルを奏でる、まさにそのような演奏でした
一人一人の演奏者がソリストとなって技巧を凝らし、その上で他の奏者との間合いを図りながら極上のアンサンブルを奏でる、まさにそのような演奏でした かねてから都響の弦楽セクションは素晴らしいと言われていますが、それを裏付けるような素晴らしい演奏でした
かねてから都響の弦楽セクションは素晴らしいと言われていますが、それを裏付けるような素晴らしい演奏でした
















