22日(金).昨夕,すみだトリフォニーホール(小)で新日本フィル室内楽シリーズ2010-
2011の第8回公演を聴きました プログラムは前半がベートーベン「弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調」,後半がシューベルト「ビアノ五重奏曲イ長調”ます”」の2曲.早いもので今シーズン最終回です.
プログラムは前半がベートーベン「弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調」,後半がシューベルト「ビアノ五重奏曲イ長調”ます”」の2曲.早いもので今シーズン最終回です.
ベートーベンは1824年5月に交響曲第9番を初演しましたが,その後3年しか生きられませんでした この間に集中して書かれたのが弦楽四重奏曲第12番~16番でした.このうち第14番の「嬰ハ短調」という調整はピアノ・ソナタ「月光」と同じです.こちらも第14番です.全7楽章から成りますが,第1~4楽章,第6~7楽章が休み無く演奏されるので,3楽章形式のような構成になっています.誰の依頼も受けずに作曲したと言われており,純粋な芸術的な欲求から生まれたようです
この間に集中して書かれたのが弦楽四重奏曲第12番~16番でした.このうち第14番の「嬰ハ短調」という調整はピアノ・ソナタ「月光」と同じです.こちらも第14番です.全7楽章から成りますが,第1~4楽章,第6~7楽章が休み無く演奏されるので,3楽章形式のような構成になっています.誰の依頼も受けずに作曲したと言われており,純粋な芸術的な欲求から生まれたようです
演奏は新日フィル第2バイオリン主席の吉村知子が第1バイオリンを務め,ほかに第2バイオリン,ビオラ,チェロの編成ですが,全体を通して,どうもすっきりこないのです とくに第五楽章「プレスト」はアンサンブルがうまくいっていないように思いました
とくに第五楽章「プレスト」はアンサンブルがうまくいっていないように思いました オーケストラのピックアップ・メンバーによる臨時編成四重奏団による演奏の限界を感じました.6月12日にサントリーホールで聴いたアメリカの「パシフィカ・カルテット」で同じ第14番を聞いた時とまったく違った印象を受けました.パシフィカの方は,何の違和感もなくすんなり音楽が響いてきました.それに比べると今回の演奏は日光の手前でした.ん?・・・イマイチでした
オーケストラのピックアップ・メンバーによる臨時編成四重奏団による演奏の限界を感じました.6月12日にサントリーホールで聴いたアメリカの「パシフィカ・カルテット」で同じ第14番を聞いた時とまったく違った印象を受けました.パシフィカの方は,何の違和感もなくすんなり音楽が響いてきました.それに比べると今回の演奏は日光の手前でした.ん?・・・イマイチでした
休憩後のシューベルト「ます」は小中学校の昼食時間を知らせるテーマ音楽としてお馴染みですね この曲は第4楽章で歌曲「ます」のメロディを主題に使っているため,この副題で呼ばれています.バイオリン,ビオラ,チェロ,コントラバスとピアノによる演奏ですが,第1バイオリンを務めるのは,このシリーズで毎回「プレトーク」を担当する第2バイオリンの篠原英和です.コンサート開始が午後7時15分ですが,その前の15分間,ベートーベンの生涯についてわかり易く解説してくれます.この人のトークは一流です.よく音楽家や歴史を知っているし話し方も上手です
この曲は第4楽章で歌曲「ます」のメロディを主題に使っているため,この副題で呼ばれています.バイオリン,ビオラ,チェロ,コントラバスとピアノによる演奏ですが,第1バイオリンを務めるのは,このシリーズで毎回「プレトーク」を担当する第2バイオリンの篠原英和です.コンサート開始が午後7時15分ですが,その前の15分間,ベートーベンの生涯についてわかり易く解説してくれます.この人のトークは一流です.よく音楽家や歴史を知っているし話し方も上手です 演奏で印象に残ったのはピアノの出久根美由樹(いずくね・みゆき)です.長い指を生かして軽快にシューベルトを演奏していました.全体的に,シューベルトの方は全メンバーが生き生きと演奏し,楽しんでいるように見えました
演奏で印象に残ったのはピアノの出久根美由樹(いずくね・みゆき)です.長い指を生かして軽快にシューベルトを演奏していました.全体的に,シューベルトの方は全メンバーが生き生きと演奏し,楽しんでいるように見えました
篠原が「この編成でのアンコール曲はこれしかありません」と言って「ます」の第4楽章を途中から演奏しました.演奏する側も聴く側も楽しめたのではないかと思います
このシリーズの次のシーズンは9月から開始されますが,ベートーベンに代わってブラームスが取り上げられます.すでにシリーズ・チケットは入手済みです.プレトークを含めて今から楽しみです

2011の第8回公演を聴きました
 プログラムは前半がベートーベン「弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調」,後半がシューベルト「ビアノ五重奏曲イ長調”ます”」の2曲.早いもので今シーズン最終回です.
プログラムは前半がベートーベン「弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調」,後半がシューベルト「ビアノ五重奏曲イ長調”ます”」の2曲.早いもので今シーズン最終回です.ベートーベンは1824年5月に交響曲第9番を初演しましたが,その後3年しか生きられませんでした
 この間に集中して書かれたのが弦楽四重奏曲第12番~16番でした.このうち第14番の「嬰ハ短調」という調整はピアノ・ソナタ「月光」と同じです.こちらも第14番です.全7楽章から成りますが,第1~4楽章,第6~7楽章が休み無く演奏されるので,3楽章形式のような構成になっています.誰の依頼も受けずに作曲したと言われており,純粋な芸術的な欲求から生まれたようです
この間に集中して書かれたのが弦楽四重奏曲第12番~16番でした.このうち第14番の「嬰ハ短調」という調整はピアノ・ソナタ「月光」と同じです.こちらも第14番です.全7楽章から成りますが,第1~4楽章,第6~7楽章が休み無く演奏されるので,3楽章形式のような構成になっています.誰の依頼も受けずに作曲したと言われており,純粋な芸術的な欲求から生まれたようです
演奏は新日フィル第2バイオリン主席の吉村知子が第1バイオリンを務め,ほかに第2バイオリン,ビオラ,チェロの編成ですが,全体を通して,どうもすっきりこないのです
 とくに第五楽章「プレスト」はアンサンブルがうまくいっていないように思いました
とくに第五楽章「プレスト」はアンサンブルがうまくいっていないように思いました オーケストラのピックアップ・メンバーによる臨時編成四重奏団による演奏の限界を感じました.6月12日にサントリーホールで聴いたアメリカの「パシフィカ・カルテット」で同じ第14番を聞いた時とまったく違った印象を受けました.パシフィカの方は,何の違和感もなくすんなり音楽が響いてきました.それに比べると今回の演奏は日光の手前でした.ん?・・・イマイチでした
オーケストラのピックアップ・メンバーによる臨時編成四重奏団による演奏の限界を感じました.6月12日にサントリーホールで聴いたアメリカの「パシフィカ・カルテット」で同じ第14番を聞いた時とまったく違った印象を受けました.パシフィカの方は,何の違和感もなくすんなり音楽が響いてきました.それに比べると今回の演奏は日光の手前でした.ん?・・・イマイチでした
休憩後のシューベルト「ます」は小中学校の昼食時間を知らせるテーマ音楽としてお馴染みですね
 この曲は第4楽章で歌曲「ます」のメロディを主題に使っているため,この副題で呼ばれています.バイオリン,ビオラ,チェロ,コントラバスとピアノによる演奏ですが,第1バイオリンを務めるのは,このシリーズで毎回「プレトーク」を担当する第2バイオリンの篠原英和です.コンサート開始が午後7時15分ですが,その前の15分間,ベートーベンの生涯についてわかり易く解説してくれます.この人のトークは一流です.よく音楽家や歴史を知っているし話し方も上手です
この曲は第4楽章で歌曲「ます」のメロディを主題に使っているため,この副題で呼ばれています.バイオリン,ビオラ,チェロ,コントラバスとピアノによる演奏ですが,第1バイオリンを務めるのは,このシリーズで毎回「プレトーク」を担当する第2バイオリンの篠原英和です.コンサート開始が午後7時15分ですが,その前の15分間,ベートーベンの生涯についてわかり易く解説してくれます.この人のトークは一流です.よく音楽家や歴史を知っているし話し方も上手です 演奏で印象に残ったのはピアノの出久根美由樹(いずくね・みゆき)です.長い指を生かして軽快にシューベルトを演奏していました.全体的に,シューベルトの方は全メンバーが生き生きと演奏し,楽しんでいるように見えました
演奏で印象に残ったのはピアノの出久根美由樹(いずくね・みゆき)です.長い指を生かして軽快にシューベルトを演奏していました.全体的に,シューベルトの方は全メンバーが生き生きと演奏し,楽しんでいるように見えました
篠原が「この編成でのアンコール曲はこれしかありません」と言って「ます」の第4楽章を途中から演奏しました.演奏する側も聴く側も楽しめたのではないかと思います

このシリーズの次のシーズンは9月から開始されますが,ベートーベンに代わってブラームスが取り上げられます.すでにシリーズ・チケットは入手済みです.プレトークを含めて今から楽しみです














 「ソーシャル・ネットワーク」と「ウォール・ストリート」の2本立てを観ました
「ソーシャル・ネットワーク」と「ウォール・ストリート」の2本立てを観ました

 この映画で使用されていた唯一のクラシック音楽は(記憶に間違いなければ)ボート競走のシーンで流れていたグリーグの「ペールギュント」の「アニトラの踊り」です.何故この曲なのか意図はわかりません
この映画で使用されていた唯一のクラシック音楽は(記憶に間違いなければ)ボート競走のシーンで流れていたグリーグの「ペールギュント」の「アニトラの踊り」です.何故この曲なのか意図はわかりません


 早速チェックしてみると,1通目が息子からで午前8:31「音楽つけっ放しでいいの?」,2通目が娘からで同9:18「音楽かけっぱなしでいいの?」でした.どうも部屋のFMラジオをつけっ放しで家を出てきたようです
早速チェックしてみると,1通目が息子からで午前8:31「音楽つけっ放しでいいの?」,2通目が娘からで同9:18「音楽かけっぱなしでいいの?」でした.どうも部屋のFMラジオをつけっ放しで家を出てきたようです 」と返信しておきました
」と返信しておきました

 」と言うのです.
」と言うのです. ウイーンからはウインナ・ワルツが,ハンガリーからはチャールダーシュが生まれたわけです
ウイーンからはウインナ・ワルツが,ハンガリーからはチャールダーシュが生まれたわけです
 プログラムに挟み込まれたスリップによると開演14:00.第1幕:約80分,休憩25分,第2幕:約65分,休憩25分,第3幕:約75分,終演予定19:00とあります.要するに5時間かかるわけね
プログラムに挟み込まれたスリップによると開演14:00.第1幕:約80分,休憩25分,第2幕:約65分,休憩25分,第3幕:約75分,終演予定19:00とあります.要するに5時間かかるわけね 話の筋は,要するに毒薬を飲んで死ぬはずだったトリスタンとイゾルデが,イゾルデの侍女ブランゲーネの気転によって媚薬を飲んだために愛し合うようになり,苦しんで,結局は死んでいくという他愛のないもの.それに5時間かけるわけです,ワーグナーという人は
話の筋は,要するに毒薬を飲んで死ぬはずだったトリスタンとイゾルデが,イゾルデの侍女ブランゲーネの気転によって媚薬を飲んだために愛し合うようになり,苦しんで,結局は死んでいくという他愛のないもの.それに5時間かけるわけです,ワーグナーという人は
 しばらくすると船の舳先が現れて,登場する歌手やオーケストラ,さらには聴衆までもが船に乗って航海しているような錯覚を覚えます
しばらくすると船の舳先が現れて,登場する歌手やオーケストラ,さらには聴衆までもが船に乗って航海しているような錯覚を覚えます それに比べてトリスタン役のデッカーは押さえ気味です
それに比べてトリスタン役のデッカーは押さえ気味です 特筆すべきはイゾルデの侍女ブランゲーネ役の藤村美穂子の素晴らしさ
特筆すべきはイゾルデの侍女ブランゲーネ役の藤村美穂子の素晴らしさ ワーグナーの聖地バイロイトで認められた実力者であればこそでしょう.この第1幕を観る限り,紅白歌合戦をやったら文句なく”赤の勝ち”です
ワーグナーの聖地バイロイトで認められた実力者であればこそでしょう.この第1幕を観る限り,紅白歌合戦をやったら文句なく”赤の勝ち”です 彼が第1幕で押さえ気味に歌っていたわけがここでわかりました.この第3幕に賭けていたわけね
彼が第1幕で押さえ気味に歌っていたわけがここでわかりました.この第3幕に賭けていたわけね 当日はウイークデーだったので,5時半に仕事が終わってから初台のオペラパレスに駆けつけましたが,なにせ開演が午後4時ですから最初から遅刻覚悟でした.それでも途中から入れてもらえることを期待して,5時10分に会場に着いたのですが,何と第1幕が終わるのが6時15分ということで,”休憩時間まではロビーのモニター・テレビでご鑑賞ください”と冷たくあしらわれてしまいました
当日はウイークデーだったので,5時半に仕事が終わってから初台のオペラパレスに駆けつけましたが,なにせ開演が午後4時ですから最初から遅刻覚悟でした.それでも途中から入れてもらえることを期待して,5時10分に会場に着いたのですが,何と第1幕が終わるのが6時15分ということで,”休憩時間まではロビーのモニター・テレビでご鑑賞ください”と冷たくあしらわれてしまいました 2時間もあれば通常のコンサート1回分が終わってしまいます.
2時間もあれば通常のコンサート1回分が終わってしまいます. ということです.今日の公演では,隣の席のおばあさんが第1幕に間に合わず,第2幕からお見えになりました.80分をロビーで過ごされたわけですね.お疲れさまでした
ということです.今日の公演では,隣の席のおばあさんが第1幕に間に合わず,第2幕からお見えになりました.80分をロビーで過ごされたわけですね.お疲れさまでした

 を書いています.
を書いています. 」
」
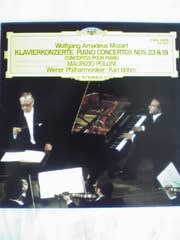
 ”いい重いでになる”なんて洒落ている場合ではありません.まあ,チラシを見るのも楽しみのひとつではありますが
”いい重いでになる”なんて洒落ている場合ではありません.まあ,チラシを見るのも楽しみのひとつではありますが
 最初の出だしからメリハリのある演奏スタイルでストラディバリを駆使して美しいメロディーを奏でていました
最初の出だしからメリハリのある演奏スタイルでストラディバリを駆使して美しいメロディーを奏でていました






 経理ミスなどを含む申告漏れの総額は約9,000万円で,同国税当局は重加算税など約3,000万円を追徴課税した.諏訪内さんはすでに修正申告した.関係者によると,諏訪内さんはコンサートの報酬など国内で得た収入は申告していたが,海外公演の報酬の一部を申告していなかった
経理ミスなどを含む申告漏れの総額は約9,000万円で,同国税当局は重加算税など約3,000万円を追徴課税した.諏訪内さんはすでに修正申告した.関係者によると,諏訪内さんはコンサートの報酬など国内で得た収入は申告していたが,海外公演の報酬の一部を申告していなかった 諏訪内さんは「海外所得に対する見解の相違と,事務手続きの不備による申告漏れを税理士から指摘され,3月に修正申告した」とコメントしたーというものです.
諏訪内さんは「海外所得に対する見解の相違と,事務手続きの不備による申告漏れを税理士から指摘され,3月に修正申告した」とコメントしたーというものです. 演奏者は中国生まれでドイツ在住の女性ピアニスト,サー・チェン.彼女は四川で音楽の勉強を始め,ダン・シャオイのもとで学んだとのこと.数年前にショパン・コンクールで優勝したユンディ・リと同じ先生だと,どこかで読んだ記憶があります.彼女も2000年のショパン・コンクールで4位に入賞していますので,相当の実力者といってもいいでしょう
演奏者は中国生まれでドイツ在住の女性ピアニスト,サー・チェン.彼女は四川で音楽の勉強を始め,ダン・シャオイのもとで学んだとのこと.数年前にショパン・コンクールで優勝したユンディ・リと同じ先生だと,どこかで読んだ記憶があります.彼女も2000年のショパン・コンクールで4位に入賞していますので,相当の実力者といってもいいでしょう 」といった印象でした.古典派よりもロマン派の方が向いているのではないか,と思いました.
」といった印象でした.古典派よりもロマン派の方が向いているのではないか,と思いました.



